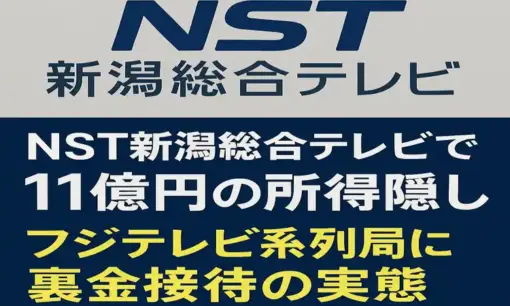2025年4月13日、大阪・関西万博がついに開幕。だがその初日、雨と混雑、通信障害と行列の連鎖が来場者を翻弄し、「並ばない万博」を掲げた運営の理想は脆くも崩れ去った。
祝祭の幕開けは混乱とともに――夢洲に続いた“人の帯”
2025年4月13日午前9時、大阪・関西万博が開幕した。会場のある夢洲には、早朝から家族連れや学生団体、海外からの観光客が列をなして到着し、開場前から熱気と期待が渦巻いていた。だが、希望に満ちたはずの開幕は、すぐに混雑と混乱に塗り替えられていく。
開門と同時に、各パビリオンを目指して来場者が一斉に走り出した。人気のアメリカ館では「月の石」をひと目見ようと、開場からわずか30分で数百人規模の行列ができ、係員の「ゆっくり歩いてください」という声がかき消されるほどの勢いだった。
昼時になると混雑はさらに深まり、飲食エリアでも異常事態が発生。くら寿司は正午前にして「8時間待ち」、スシローは「279組待ち」と表示され、SNSには「昼食難民」の声があふれた。ある母親は「ここまで来て寿司を食べるのに夜まで待つとは思わなかった」と苦笑いを浮かべた。
だが、笑顔が消えたのは午後になってからだ。雨が強まり始めると、退場を急ぐ人々が夢洲駅へと殺到し、列は駅まで数百メートルにも及んだ。足元はぬかるみ、傘をさしても防ぎきれない風が容赦なく吹き付けた。夢洲はまさに、“行列の島”と化していた。
「並ばない万博」の理想が崩れた理由とは
万博の理念は、「いのち輝く未来社会のデザイン」。その実現には、デジタル技術の活用とスムーズな来場体験が前提とされていた。だが現実は違った。午後に降り出した雨とともに帰路につく人々が集中し、唯一の最寄り駅・大阪メトロ夢洲駅では入場制限が実施された。
「駅の入口まで、2時間もかかった」とSNS上では悲鳴のような投稿が相次ぎ、警備員の誘導に従う長い列が、会場内をぐるりと取り囲んだ。大阪メトロはこの万博に向けて中央線を「万博ダイヤ」へと改正し、ピーク時間帯には1時間あたり最大13万3000人の利用を見込む体制を敷いていた。列車は2分30秒間隔で24本、子ども団体専用の「子ども列車」も最大12本運行されるなど、大規模輸送体制が整えられていた。
しかし、それでも混雑を抑えきれなかった。アクセスが大阪メトロ中央線に事実上一本化され、しかも夢洲には自家用車の乗り入れが原則禁止されていることが、公共交通機関への過度な依存という構造的な限界を浮き彫りにした。
通信障害と案内不足が生んだ“情報の迷子”
現場ではさらに、想定外の混乱があった。通信障害である。スマートフォンを使ったデジタル地図の利用が前提とされていたが、ネット接続が不安定で、多くの来場者が地図アプリにアクセスできなかった。
その結果、紙の地図を求めて案内所に長蛇の列ができた。SDGsの観点から紙地図は有料とされていたが、環境配慮の建前よりも「今、道に迷っている」という目の前の現実が優先された。「紙の地図が一番早い」と漏らした男性の手には、折りたたまれたA3の地図が握られていた。
「どこに並んでいるのか分からなかった」「スタッフも場所によっては把握していなかった」との声もあり、情報提供の一元化の欠如が指摘されている。
予測されていた“雨のリスク”に備えはあったのか
午後3時を過ぎると、空は急速に暗くなり、風雨が強まり始めた。夢洲の象徴でもある大屋根リングの下に人々は避難したが、構造上の理由から強風を防ぐことは難しく、屋根の下にいても横殴りの雨で衣服が濡れた。
天候リスクは事前に想定されていたはずだった。会場は海に囲まれた人工島であり、春先は天候の急変が多い地域である。それにもかかわらず、屋内で待機できるスペースは限られており、飲食や休憩を取るにも長蛇の列。傘を差していても濡れながら並ぶ来場者の姿は、「未来の社会を体現する場」としての理想から大きく乖離していた。
「なぜ、こんなに風が抜ける設計なのか」「一時避難できるテントもほとんどなかった」。そう不満を漏らしたのは、都内から訪れた親子連れの父親だ。体を冷やした小さな子どもを抱えながら、彼は「安全ではない」と感じたという。
気候変動が常態化する現代において、災害級の雨風は“突発”ではなく“織り込み済み”であるべきリスクだ。設計思想にその認識が十分に組み込まれていたかどうかが、今後改めて問われるだろう。
世界の万博に学ぶ、“人の流れ”への備え
さらに、展示パビリオンの準備遅れも来場者の期待を裏切った。FNNプライムオンラインによれば、インド、チリ、ネパール、ベトナム、ブルネイの5カ国のパビリオンは開幕日に開館できなかった。内装工事が間に合わなかったという。158カ国・地域が参加する国際博覧会において、この事実は計画と実行の間に深い溝があることを物語っている。
他国の事例に学ぶべき点は多い。たとえば2020年のドバイ万博では、来場者の導線に合わせて複数の鉄道路線やシャトルバスが戦略的に配置され、敷地内外に小規模な乗降拠点を分散させることで、混雑を一点に集中させない設計がなされていた。デジタルとフィジカルの融合だけでなく、移動そのものを快適にするインフラ設計こそが、“未来社会のデザイン”の土台として重要視された。
ある運営関係者は「初日の課題を真摯に受け止め、改善していきたい」と語ったが、今後は来場者の体験そのものが、万博の評価を左右する重要な要素となるだろう。