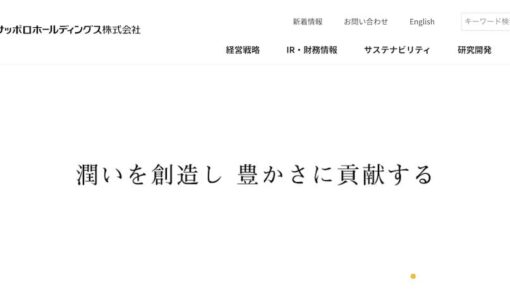日本テレビの人気番組「月曜から夜ふかし」で発言がねつ造された問題に、総務相が異例の苦言。テレビ報道の信頼性が根本から問われている。
インタビュー発言のねつ造が発覚 「中国ではカラスを食べる」は虚構だった
JR新宿駅東南口。人がひっきりなしに行き交うその場所で、日本テレビのバラエティ番組「月曜から夜ふかし」の取材クルーが街頭インタビューを行っていた。3月24日、その模様が放送されたが、そこに映っていた中国出身女性の発言が“ねつ造”であったことが、後日、明らかになった。
「中国ではカラスを食べる。とにかく煮込んで食べて終わり」と字幕で紹介された内容は、実際には女性が一切口にしていないものだった。スタッフが別の話題で話していた音声を切り貼りし、編集で“作り上げた”構成だったという。
総務相が異例の言及 政府が放送内容に懸念を表明
3月28日、村上誠一郎総務相は記者団に対し、「日本テレビは国民の知る権利を満たす等の放送事業者の社会的役割を自覚し、適切に対応していただきたい」と述べ、厳しい視線を投げかけた。番組側は27日に公式サイト上で謝罪文を掲載し、日本語と中国語の両言語で経緯を説明。「テレビメディアとして決してあってはならない行為」と自らの非を認めた。
編集現場にあった過度な“撮れ高”主義と緩いチェック体制
なぜ、こうした捏造が起きたのか。番組関係者によると、原因のひとつは過度な“撮れ高”主義にあるという。街頭インタビューでは数百人に声をかけ、その中から使えるのはほんの一部。制作現場では「面白さ」が至上命題となり、編集の正当性より“笑いの演出”が優先されていた。
もうひとつの要因は、異文化理解に乏しい体制だ。かつては中国人スタッフが編集チェックに加わっていたが、今回の件ではその役割が失われていた。もしチェック体制が機能していれば、女性の発言を誤って翻訳・編集する事態は防げた可能性がある。
信頼失った番組にSNSで批判殺到 「もう見ない」との声も
この問題に対する世間の反応は激しい。SNSでは「完全な捏造」「人種差別を助長している」「テレビ全体が信用できなくなる」といった声が相次いだ。中には「今後、どんな街頭インタビューも疑ってしまう」という反応もあり、番組が長年築いてきた信頼が一夜にして崩れた格好となった。
番組は2012年のスタート以来、素人の言動をユーモラスに取り上げる構成で人気を博してきた。桐谷さんやフェフ姉さんといった名物キャラクターも生んできたが、今やその「素人いじり」スタイル自体に限界が問われている。
相次ぐ不祥事が露わにするテレビ業界の構造的課題
日テレに限らず、テレビ業界全体が大きな転機を迎えている。直近ではフジテレビでも、番組制作における不適切な対応が報じられ、視聴者やスポンサーから厳しい声が寄せられた。ネットを中心とした情報環境の変化により、テレビが長年頼りにしてきた“信頼のブランド”が失われつつある中、各局は透明性や倫理性の確保という新たな課題に直面している。
また、過去にはTBSの報道番組においても編集内容に疑義が呈され、訂正放送やBPO審査に至った例がある。こうした前例と今回の問題とを照らし合わせれば、単発的な失敗ではなく、業界に横たわる構造的な緩みとして捉えるべき事態であることが浮き彫りになる。
とりわけ、バラエティと報道の境界が曖昧な番組では、視聴者の受け取り方とのギャップが大きくなりやすい。編集の自由と事実の尊重、そのバランスが問われる時代に、テレビが何を守り、どう変わるのかが注視されている。
放送継続と番組の行方 メディアの自浄作用と視聴者のリテラシーが試される時代に
日本テレビは31日の放送を予定通り行うと発表したが、今後の展開は不透明だ。BPO(放送倫理・番組向上機構)への審査申し立てが行われれば、より厳しい検証が始まる。内部でも「番組終了もあり得る」との声が漏れており、13年続く人気番組が、今まさに大きな岐路に立たされている。
本件は一バラエティ番組の過失にとどまらない。報道と娯楽のあいまいな境界、視聴者が「どこまで信じてよいか」を問う深刻な問題である。AIによる自動生成コンテンツやSNS情報の氾濫が進む中で、テレビというマスメディアが最後に拠り所とすべきは「信頼」そのものである。
いまこそ、放送の現場が真摯に問い直すべきは、誰のための番組であるかという根源的な命題である。そして我々視聴者自身も、メディアに頼りきるのではなく、自ら問い、調べる姿勢を持たねばならない時代にある。