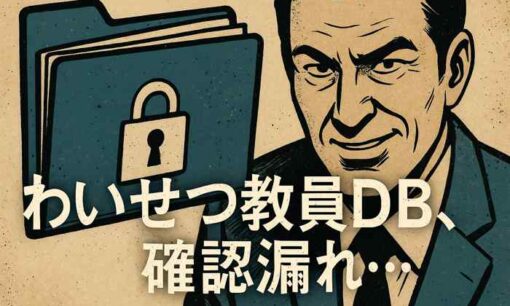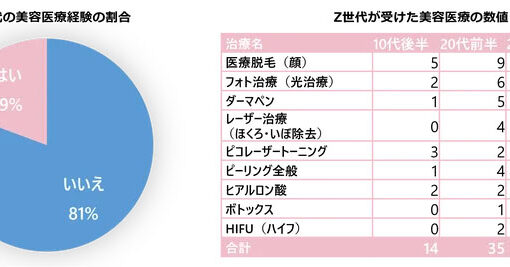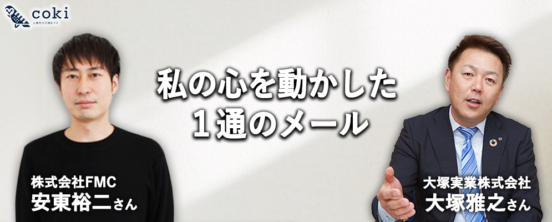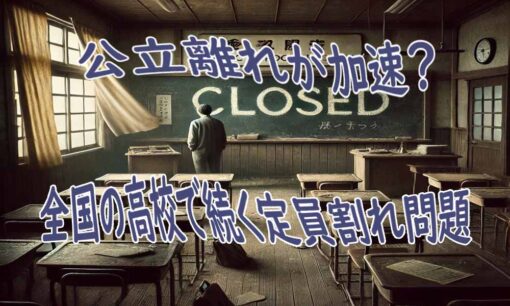オンライン診療の規制違反が相次いでいる。医師が診察せずに薬を処方したり、初診で向精神薬を提供するなどのケースが確認され、厚生労働省は規制強化に向けた法改正を進める方針だ。安全性確保が急務となっている。
医師不在の診療、ずさんな処方が横行
スマートフォンを活用したオンライン診療の拡大に伴い、医療機関のずさんな運用が問題となっている。特に、医師が診察せずに薬を処方する事例や、初診での向精神薬提供など、医師法や厚生労働省の指針に抵触する恐れのあるケースが増えている。
関東地方に住む50代女性は、精神面の不調を訴え東京都内のクリニックにオンライン診療を申し込んだ。しかし、診察を行ったのは医師ではなく看護師であり、短時間の会話の後に睡眠薬の処方を勧められた。女性は少量の服用を希望したものの、1か月分からしか出せないと告げられ、届いた薬を服用するとめまいが発生。副作用の説明もなく、不安を感じて服用を中止したという。
厚生労働省の指針では、基礎疾患の情報が未把握の患者に対して8日分以上の薬を処方することを禁じている。しかし、同省が2023年1月から3月に調査した結果、指針違反の疑いがある事例が1740件確認された。
利便性の裏に潜むリスクと信頼問題
現代では新しい病院を選ぶ際、口コミを参考にすることが一般的となっている。対面診療でも医師の対応に良し悪しがある中、オンライン診療では医師との距離をより一層感じやすい。画面越しの診察では症状を正確に伝えづらく、不安を抱く患者も少なくない。そのため、医師と患者の信頼関係を築くための工夫が求められる。
オンライン診療は患者の負担軽減や医療アクセス向上の観点から導入が進められた。特に離島やへき地での利用が期待され、2018年には公的医療保険の適用対象となった。コロナ禍では感染リスクを避ける目的で初診からのオンライン診療が特例的に認められ、2022年以降は恒久化された。
しかし、利便性の向上と引き換えに、診療の質が低下する問題が浮上している。対面診療では当然行われるべき触診や聴診がオンライン診療では難しく、医師と患者の間に十分なコミュニケーションが取られないケースもある。
全国の消費生活センターには、2023年度だけでオンライン診療に関する相談が258件寄せられた。これは2021年度の5倍にあたり、ダイエット目的の処方など不適切な対応が増加していることが示されている。
厚生労働省が動く、今後の規制強化は
厚生労働省は、オンライン診療の適正化に向けて法改正を視野に入れている。具体的には、初診での診療範囲の厳格化、医師と患者双方の身分確認の義務化、処方可能な薬剤の規制強化といった施策が検討されている。医療機関側にも、診療の質を維持しつつオンラインの利点を活かす工夫が求められる。
オンライン診療の利便性を損なわず、適切な医療提供を実現するためには、国の指針を厳守し、患者との十分な対話を確保することが不可欠だ。患者自身も、オンライン診療のリスクを理解し、慎重に利用する姿勢が求められる。