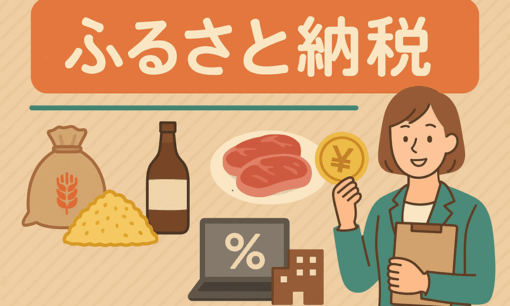工藤建設株式会社(東証スタンダード、コード番号1764)は2月4日、同社が受注した複数の工事において不適切な原価管理が行われていたことを公表した。社内調査委員会による調査の結果、原価の付替えが行われていたことが明らかになったほか、特定の取引先に対する過払いの可能性や、一部の関係者がキックバックを受け取っていた疑いも浮上した。
これを受けて同社は、過年度の財務諸表および連結財務諸表の修正を行う方針を示した。
社内調査委員会の調査結果
工藤建設は2025年1月7日、社内調査委員会を設置し、事実関係の調査を開始した。調査報告書によれば、特定の工事において本来の原価が他の工事へと付け替えられていたことが判明。さらに、ある取引先に対して本来の出来高を超えた支払いが行われており、それに関連して特定の関係者が不適切な利益を得ていた可能性が指摘された。
財務面への影響も大きい。同社によれば、2023年6月期から2025年6月期にかけての財務諸表に修正が必要となり、特に2024年6月期の第2四半期以降、大幅な赤字が発生している。2024年6月期の完成工事高は前年同期比で約15億円減少し、最終的な損失は約45億円に上る見込みだ。
不祥事の背景と企業ガバナンスの問題
調査では、社内のガバナンス体制にも問題があることが浮き彫りになった。具体的には、内部監査のチェック機能が不十分だったことに加え、原価管理に関する意思決定のプロセスが曖昧であったことが指摘されている。さらに、経営管理部の監視機能が弱体化していたことも、不正を長期間にわたり看過する要因となったと考えられる。
再発防止策と今後の対応
同社は、再発防止策として経営管理部門の強化や監査体制の見直しを進める方針を示した。具体的には、経理・財務部門の監査機能を強化し、原価管理の透明性を高めるほか、リスク管理委員会の活動を活性化することで、不正行為の発生を未然に防ぐ体制を整える。また、監査室の人員を増員し、内部監査の厳格化を図るとともに、役職員に対するコンプライアンス研修を強化するとしている。
しかし、これまでの経営体制の問題を受けて、市場では厳しい見方もある。過去の不祥事対応を見る限り、同社のガバナンス改革が実効性を伴うかどうかは不透明であり、今後の対応が注視される。
工藤建設とはどのような企業か
工藤建設は1966年、工藤浄水工業所として創業し、1971年に現在の社名に変更した。神奈川県横浜市に本社を構え、建設事業、不動産事業、介護事業を展開している。同社は「生活舞台創造企業」を掲げ、街づくりを中心に事業を展開してきた。特に建設事業では、戸建住宅の設計・施工に加え、公共施設の建設やリノベーションにも力を入れている。
創業者の工藤五三(ゆきみつ)氏(1934年生まれ)は、自衛隊員や保線作業員を経て、1966年に工藤浄水工業所を創業。ゼロから事業を築き上げ、神奈川を拠点とするゼネコンへと成長させた。2003年には介護事業にも進出し、現在は有料老人ホームの運営も手掛けている。
一方で、近年の経営環境の変化に対する対応は鈍く、CSR(企業の社会的責任)に関する取り組みも限定的である。同社のコーポレートサイトでは、直近のCSR関連のリリースが2023年10月の「省エネ住宅現場見学会」開催にとどまっていたことからもあまり開示に積極的な会社ではないようだ。
有価証券報告書のサステナビリティ欄の記載も見てみたが、2024年7月よりサステナビリティ推進委員会を立ち上げ、サステナビリティへの対応を本格化させる方針を示してはいた。これまで同社はサステナビリティへの取り組みに消極的とされていたが、今後の企業価値向上に向けた動向が注目される。
有報によると、従業員の健康経営には力を入れているようだ。2023年2月には横浜市が認証する「横浜健康経営認証クラスAAA」の事業所として認定されたことが開示されている。これは、企業が従業員の健康増進を経営戦略の一環として推進し、長期的な企業成長と結びつける取り組みを行っていることを示す一例と言えるだろう。また、同社は社員が心身ともに健康でイキイキと働ける職場環境を整えることを重視し、健康増進活動を積極的に推進している。
今後、同社は不祥事の影響を最小限に抑え、信頼回復を図ることが求められるが、企業価値の向上には長期的な視点での経営改革が不可欠となるだろう。