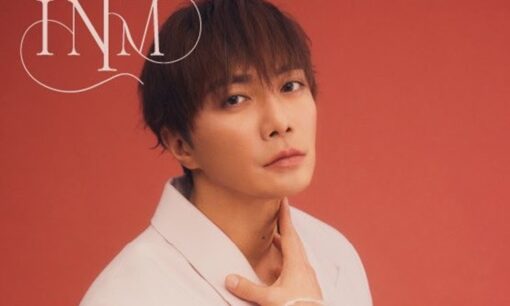農林水産省は、コメ価格の高騰を受け、政府備蓄米の早期放出を決定した。江藤拓農相は7日の閣議後記者会見で、早ければ来週中にも数量や価格などの詳細を公表する意向を示した。コメの流通円滑化を目的とした備蓄米の放出は、実施されれば初めてのこととなる。
政府の狙いと備蓄米放出の影響
農水省によると、今回の備蓄米放出は、米価の高騰が消費者の購買行動に影響を及ぼす可能性があるための対応策である。江藤農相は「これ以上高くなると、コメ自体を消費者が選択しなくなる」と危機感を示した。政府が備蓄米を放出する場合、全国農業協同組合連合会(JA全農)などの集荷業者に売却する形となる。供給量が増えれば市場価格の安定化が期待されるが、一方で過度な値下がりを防ぐため、放出量と同量を1年以内に買い戻す条件が付与される。
なぜ備蓄米は必要なのか
備蓄米は、災害や不作などの緊急時に備えて政府が保管している米であり、国民の主食である米を安定的に供給し、市場価格を調整する役割を担っている。備蓄米制度は、1993年に発生した「平成の米騒動」をきっかけに1995年に開始された。備蓄米の目的には、凶作や不作の際に消費者に安定した供給を行うこと、米の市場価格を調整し急激な変動を抑えること、そして豊作時に過剰な供給を防ぎ市場の均衡を保つことが含まれる。運用は食糧法に基づき、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」に従って行われている。
米価高騰の背景にあるもの
2024年産のコメは、生産量が前年比で18万トン増えたものの、JA全農などの集荷量は昨年12月末時点で約21万トン減少している。これは、小規模業者がさらなる米価上昇を見越して高値で買い集めたり、一部の農家が販売を控えたりしているためとみられる。農水省は、こうした流通の停滞が米価高騰を招いていると判断し、備蓄米の放出を決断した。
また、米価の高騰の背景には、政府の減反政策がある。減反とは、農家に補助金を支給し、意図的に生産を抑制することで米価を維持する制度である。1993年の平成の米騒動の際も、冷夏による不作が直接の原因とされていたが、根本には減反政策による生産抑制があった。当時の潜在的な生産量は1300万トンあったが、減反により1000万トンに制限され、不作によってさらに783万トンにまで減少した。現在も水田の4割が減反対象となり、年間生産量は700万トン以下に抑えられている。そのため、需給の余裕がなく、天候や市場の変化によって価格が大きく変動しやすい状況にある。
備蓄米放出の具体的な動き
政府は、2024年夏の令和の米騒動以降続くコメ価格の高騰を受け、1月に備蓄米の運用を見直した。農水大臣の判断で、流通の滞り時には備蓄米を売り渡せるようにした。江藤農水相は「やると決めたら早くやった方が良い」と述べ、迅速な対応を進める方針を示した。
農水省は、来週にも入札で売り渡す数量を示し、その後JAなどの集荷業者を対象に入札を行う予定である。備蓄米が放出されれば、流通の円滑化を目的とした初のケースとなる。これにより米価の高騰が抑制されるかが注目されている。
専門家の見解では、産地での調達価格が下がり始めており、備蓄米の放出により店頭価格が3〜4割安くなる可能性があると指摘されている。ただし、スーパーマーケットの在庫がまだ多く残っているため、販売価格の低下には時間がかかる可能性も示唆されている。
減反政策は今後も続くのか
政府が備蓄米を放出する事態に至っても、減反政策を継続する可能性は高いと考えられる。減反は長年、農家への補助金を通じて生産量を抑制し、米価を安定させる目的で運用されてきた。過去の政策変更を見ても、一時的な価格変動があっても大規模な見直しには慎重な姿勢を維持してきた経緯がある。
また、減反の継続は農業団体や政治的な圧力とも密接に関係している。農家の経営安定や特定の地域経済の維持にとって重要な手段とされており、これを廃止すると市場の不安定化を招く恐れがあるとされる。特に、備蓄米の放出はあくまで短期的な対策であり、長期的な生産調整の枠組みとしての減反政策を即座に撤廃する動きにはつながりにくい。