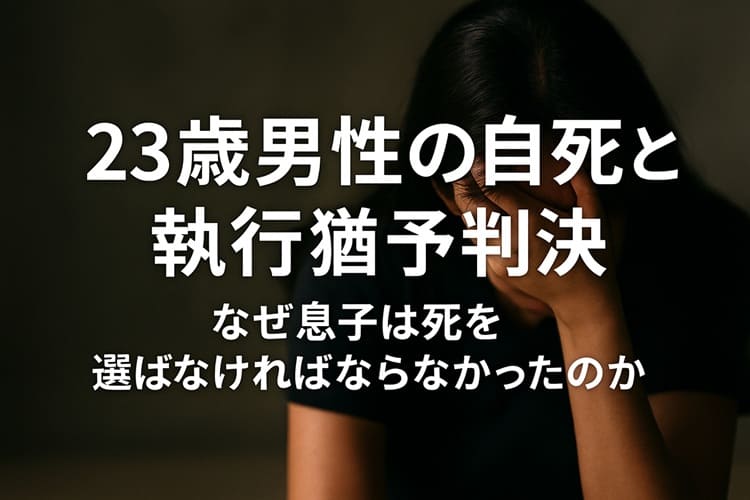
福島県相馬市で23歳の青年・金子丈(たける)さんが繰り返し暴行を受けた末に自死した事件で、主犯格の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。
暴行と自死の因果関係は「証拠がない」と退けられたが、遺族の心に残るのは深い悔恨とやり場のない怒りだ。司法が突き付けた判断は、はたして社会の正義に照らして妥当なのか。SNSでは厳罰を求める声が噴出している。
23歳の命が突然絶たれた夜 母に届いた「産んでくれてありがとう」
今年4月16日午後6時ごろ、丈さんから母親のスマートフォンに一通のメッセージが届いた。
「産んでくれてありがとう」。突如として送られた言葉に、母親は胸騒ぎを覚え、すぐに電話をかけたが応答はなかった。
警察署に駆け込み捜索願を出そうとした直後、「ダムに車が入っていった」との通報が入った。引き揚げられた車は丈さんのものだった。午後9時、病院で対面した息子の姿は無残に変わり果て、顔は大きく腫れ上がり、鼻の骨は折れていた。母親はその光景を「人の顔ではなかった」と語る。
幼いころから命を慈しんだ青年 穏やかな生活の裏で続いていた暴行
丈さんは地元の高校を卒業後、水産加工関連の仕事に就き、静かに日々を送っていた。幼い頃から生き物を大切にし、クワガタを育て、捨て猫を抱えて帰るような優しい少年だった。家族と釣りに出かけては、釣れた魚の大きさを笑い合った。4月下旬には、父親とプロレス観戦に行く約束もしていた。
しかし、その穏やかな日常の裏で、丈さんは昨年11月から4月までの間に4回もの暴行を受けていた。
県警の捜査によって明らかになった事実は、複数人による繰り返しの集団暴行だった。人気のない場所に呼び出され、殴られ、コンクリートに投げつけられる暴力は、肉体と精神を確実に削り続けた。これまでに関与した6人が逮捕され、暴行が組織的で長期に及んでいた実態が徐々に判明していく。
主犯格の20歳男 4度逮捕、執拗な暴行と証拠隠滅の疑い
捜査が進むにつれ、主犯格とされた相馬市の20歳の男が、事件の中心に位置していたことが次第に浮かび上がった。逮捕は計4度に及び、いずれも丈さんへの暴行の容疑だった。
警察関係者によると、暴行は単発的な衝突ではなく、あらかじめ呼び出しの連絡を入れ、複数人で待ち構え、逃げ道を塞ぐ形で行われていたとみられる。こうした「支配と恐怖の構造」が成立していたことこそが、今回の事件の深刻さを際立たせている。
特に、丈さんが命を絶った4月16日にまで暴行が繰り返されていた事実は重い。未明と午後という二度の呼び出しに応じさせ、暴力を振るったとされる行為は、単なる衝動や一時の感情的対立では説明しきれない。捜査関係者は「相当な執着と支配欲が背景にあった可能性がある」と語る。友人関係であったはずの相手を繰り返し追い詰める心理は、常識では測りきれない異質さを帯びている。
男は被告人質問で、女性関係のトラブルを動機として語った。
だが、捜査資料によれば、その「理由」は周囲の証言と整合しない部分もある。暴行の頻度、時間帯、参加人数、そしてその場での言動は「トラブル」という言葉の範疇をはるかに超えていた。理不尽で暴力的な上下関係を作り上げ、丈さんを従わせようとする意図が透けて見える。
さらに、犯行の様子が記録されていた可能性があるドライブレコーダーを処分していた疑いも判明した。こうした行為が偶発的なものではなく、「まずいと思うことは隠す」という犯罪的な判断力が働いていたことを示している。証拠隠滅は、暴力そのものが計画性と悪質性を帯びていた可能性を示唆する重要な要素だ。
丈さんは一度も、家族にも友人にも暴行被害を相談していない。支配と恐怖が長期化するなかで、被害者本人が「逃げられない」と思い込まされる構造が生まれやすい。男は、丈さんの弱さや優しさにつけ込み、逃れられない心理的な檻を作り上げていたのではないか。
警察が6人を逮捕した背景には、主犯格の男を中心とする“加害の連鎖”が存在していたと推察される。
法廷で男は「けがをさせ申し訳ない」と頭を下げた。しかし、この言葉を真摯な反省と受け取ることは難しい。裁判を通じて明らかになったのは、反省よりも保身、責任よりも逃避を優先する姿であり、暴力の連鎖に対する自覚が乏しいという厳しい現実だ。
丈さんの死は偶然ではなく、長期的かつ深刻な暴力の果てに訪れた「必然」だったのではないか。暴力を軽く見る風土、被害者が声を上げられない環境、そして加害者が軽い処分で社会に戻ることを許す仕組み――今回の事件は、地域社会と司法が抱える構造的な問題を露呈している。
この20歳の男が行った行為は、単なる「傷害」ではない。人間の尊厳を踏みにじり、恐怖で縛り付け、精神を破壊する連鎖的な暴力だった。司法がこうした暴力にどう向き合うのか、社会はその判断を厳しく見ている。
裁判所が示した「因果関係なし」 遺族を置き去りにした執行猶予判決
地裁相馬支部は1日、暴力行為等処罰法違反と傷害の罪に対し懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。岩田真吾裁判官は「傷害の程度は重篤とは言えず、実刑を選択する事案とは認め難い」と述べた。
暴行と自死の因果関係は「証拠上認められない」。そこに裁判所の判断は収れんした。
だが、遺族の思いは違う。
母親は意見陳述で震える声のまま訴えた。「暴行が精神的に追い詰めた。被告の行為がなければ息子は死ななかった」。
父母は「精神の摩耗は証拠に表れない。息子がどれほど孤独でどれほど恐怖を抱えていたか、誰にも分からない」と語った。その嘆きは、司法の枠組みからこぼれ落ちる人間の痛みそのものだ。
SNSが沸騰した「執行猶予判決」への批判 社会が求めるのは何か
判決が報じられると、SNSでは厳しい批判が殺到した。
「執行猶予は軽すぎる」
「暴行された側の人生は戻らないのに、加害者は社会に戻れるのか」
「遺族の痛みをどう考えているのか」
特に、丈さんの顔が腫れ上がり骨折するほどの暴行と、その日のうちに命が絶たれた事実を前に「因果関係なし」とされる判断には、理解を示す声はほとんど見られない。
暴力は人を追い詰める。精神に与えた傷が法廷で「証拠」として扱われないとしても、たった一つの暴行が人生を破壊することは、誰もが知っている。遺族は「暴力の残酷さを知ってほしい」と訴える。
司法は加害者の更生を重視する。しかし、社会は被害者と遺族の救済と尊厳の回復を求めている。今回の判決が突き付けたのは、その深い断絶である。































