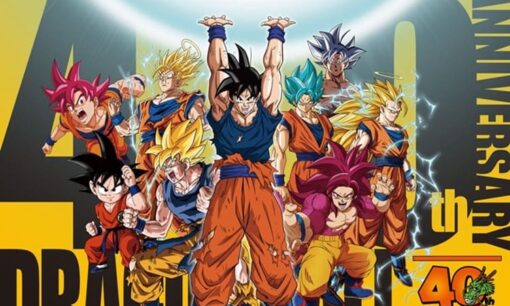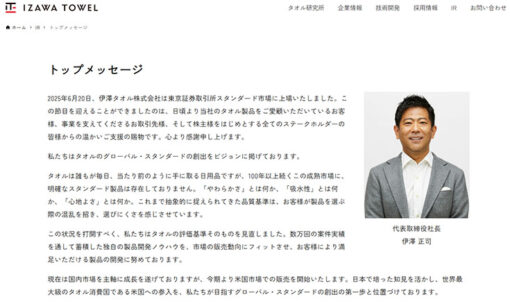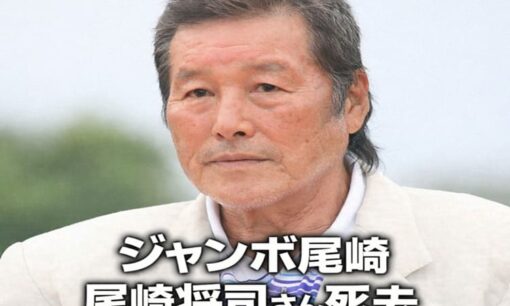ブラジル・ベレンで開催された国連気候変動会議(COP30)が、会期を延長した末、11月22日に閉幕した。議論の核心であった「化石燃料からの脱却」の工程表策定は白紙となり、国際協調は機能不全に陥った。
さらに、会議中に会場内で実際に火災が発生するなど、その内実は地球の危機を暗喩する「炎上」状態だった。
この国際政治の機能不全を尻目に、Appleやソニーといった民間企業は「2030年再エネ100%」を掲げ、脱炭素へのアクセルを踏み込む。この民間主導の「グリーン急進主義」は本当に世界の構造を変える力を持つのか。
本誌は、政治の失敗の裏側にある日本の政策の深層と、再エネを巡る技術論争を徹底的に追った。
COP30「大火災」が暗喩した国際協調の断絶
今回のCOP30の混乱を象徴するのは、閉幕直前の20日午後に会場内で発生した大火災だ。電気機器からの出火とみられる炎は天井まで燃え上がり、火元が「中国ブースの近く」だったことが、ブラジル観光大臣によって明らかにされている。
最大排出国である中国は交渉当事者として参加していたものの、そのブース付近で火災が発生したことは、国際的な排出削減議論が抱える困難と、最大の排出国が直面する責任を暗喩しているかのようだった。
一方、排出量2位の米国(トランプ大統領)は会議を「詐欺」と切り捨て、国際的な枠組みから背を向けて欠席するという状況が、まさに「国際協調の場が炎上し、機能不全に陥っている」現実を象徴していた。
「決裂回避」の裏で骨抜きにされた合意
会議の焦点だった「化石燃料からの脱却に向けた工程表」の策定は、産油国などの強硬な反対により、最後まで合意に至らず白紙撤回に追い込まれた。
採択された合意文書は、温室効果ガス排出削減の加速や途上国への資金支援強化を盛り込んだものの、すべてが抽象的な「努力目標」に後退。途上国が求める資金援助も、先進国の負担嫌いから「35年までに3倍にするための努力を求める」という水準にまで後退した。
この「決裂回避」のための合意に対し、パナマやコロンビアの代表からは「押しつけられた合意は間違っている」と、公然と怒りの異論が噴出する大荒れの閉幕となった。
「半世紀も続いた日本のガソリン暫定税率廃止ですら、与野党の合意に半世紀かかった。それを思えば、世界200カ国がたった2週間で化石燃料の『廃止』に合意できると本気で考えていた方が甘かったのかもしれない」と、ある国際政治評論家は皮肉る。
結局、ここ最近のCOPは、「何も決めないことを、なんとか決める」ための、国際的なアリバイ作りの場と化しているだけなのだ。
日本の「責任回避戦略」が映す葛藤
実際に、日本がCOP30で脱化石燃料の工程表策定声明に加わらなかったのは、国内のエネルギー事情と「コスト」のジレンマを解決できていないことの裏返しともいわれている。
日本の発電における化石燃料の割合は依然高く、政府がCCS(CO2回収・貯留)や水素・アンモニア混焼といった技術を推進するのは、「日本の既存の火力発電技術やインフラを最大限活用し、エネルギー自給率を急激に下げないための、現実的な(あるいは消極的な)選択」という側面を持つ。
一方で、ガソリン暫定税率廃止でガソリン価格が下がり、消費拡大による「脱炭素に逆行」するリスクも抱えている。
この「曖昧戦略」の裏には、再エネ拡大による系統電力の安定化コストに対する根強い懸念がある。太陽光や風力の間欠性を補うための蓄電池や導線といった安定化の費用は膨大であり、これが電気料金に転嫁されることへの国民的な抵抗も無視できない。
「国民には安価なガソリンを配り、企業には再エネを自主的に頑張らせる。国は責任を曖昧にし、財界と国民の顔色を伺う『八方美人』政策に終始している」という批判も当然の帰結だ。
ただし、日本が強みを持つペロブスカイト太陽電池や、農地の上にパネルを設置するソーラーシェアリング(営農型太陽光)といった次世代技術の開発は進んでいる。
日本の「曖昧戦略」は、この技術的な優位性を活かして時間を稼ごうとする、「技術で解決する」という希望と、「現状維持」という抵抗が混在した姿なのだ。
企業を突き動かす「投資家の圧力」と「グリーン経済」
結局、国際政治が停滞し、国主導の政策が迷走する中で、脱炭素を牽引するのは民間企業のR&Dしかないのかもしれない。
Appleやソニーグループが取引先にまで再エネ100%を要求するのは、単なる理想論ではない。現在、国際金融市場では、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく開示やサステナブルファイナンスの流れが主流となり、投資家からの「気候リスク回避」圧力は無視できない。
ここで無視できないのが、中国の貢献だ。ドイツ開発評価研究所のケビン・モール評価員によると、「中国が再生可能エネルギーのコスト低下、太陽能製品の入手可能性の向上、ならびに電気自動車技術の普及推進において顕著な貢献を果たした」との発言もあった。企業の競争は、特定の国の技術革新に大きく依存しているのが現状だ。
自然エネルギー財団の石田雅也研究局長がTBSの「サンデーモーニング・風をよむ」で指摘したように、地政学リスクが高まる中、再エネは化石燃料よりも中長期視点では、「価格も量も安定的に見込める」という経済合理性に基づいている。
>「化石燃料に依存した事業を続けていると、コストの変動リスクを長期的に負う。(中略)価格も量も安定的に見込める再エネを使っていく」
従来、この企業主導の潮流は、脱炭素市場における先行者利益を確保する狙いとともに、「国の政策を待つのではなく、自らが積極的に活動して国の政策を変えていく」という、政治を動かす意思を伴っていると期待されていた。
再エネ「急進」が招くコストと資源戦争の懸念
ただ、この企業主導の再エネ一辺倒の動きにさえ、懐疑的な専門家は多い。企業努力に期待が寄せられていた「ハズ」だったが、その裏側は依然としてコストと供給リスクに晒されている。
安定供給とコストの壁について日本の専門家が懸念するのは、性急な導入が電気代高騰を招き、国民生活を圧迫するリスクだ。企業が再エネの調達を急ぐほど、初期投資がかさみ、その費用は最終的に消費者に転嫁される。「経済全体が疲弊すれば、脱炭素への国民的な理解も遠のく」(経済アナリスト)という警告も出ている。
地政学リスクと資源の偏りで脱炭素を真に機能させるには、排出量取引制度(ETS)や炭素税といった「カーボンプライシング」(炭素の価格付け)が不可欠だ。これが世界的に機能していないことが、「化石燃料への言及回避」を許し、再エネ導入を企業の「善意」や「投資家の圧力」に依存させている構造的な問題となっている。
実際に、日本では、2013年にJ-クレジット制度がスタートしてから、東京証券取引所によるカーボン・クレジット市場がはじまっているが、一方で、「実際に購入している」という企業はほとんどなく、お寒い現状であることは誰の目にも明らかである。
さらに、再エネ設備に不可欠なレアアースやリチウムなどの採掘・加工・供給網が特定の国に偏ることで、化石燃料への依存から新たな資源の「鎖国」に繋がるのではないかという懸念も存在する。
日本メディアの「無批判」と「環境正義の切り捨て」
何より、再エネをはじめとしたサステナビリティは、国民の関心が薄い。メディアもまた、それに右習えのようだ。最低限取り上げておくといった体であり、世間のサステナ疲れを象徴するようである。
まぁ、景気のいい話ではなく、大概が利益を生み出すプロフィットセンターの話ではなく、コストセンターの話であり、過激な環境活動家、人権活動家たちの気持ち悪さばかりが悪目立ちし、SDGsの欺瞞なども指摘されるに、まっとうな国民なら「あほらし」となるのは納得せざるを得ないだろう。
さて、今回のCOP30の合意を巡る報道のスタンスは、国際社会でも割れているようだ。アメリカでは「産油国の勝利、地球の敗北」といった批判的なニュアンスが強いが、日本国内の報道は、その批判的な伝え方が希薄な傾向にある。
この「無批判」な姿勢は、日本のメディアが誰の側に立っているかを雄弁に物語っている。事実を淡々と伝える姿勢は、温暖化の被害を被る開発途上国の人々や生態系の側を置き去りにしているというか、究極的な意味で自分ごととは程遠く、ポーズだけは一丁前のことなかれ主義そのものである。
日本の狙いは、合意が骨抜きになったことでまた「化石燃料への言及」を避けることができ、先送りできたということにつきるだろう。本質的には「化石燃料に言及しない脱炭素なんて、まやかしに過ぎない」のだろうが、先進国と途上国の間で利害が纏まるハズもなく、現実問題、先送りしていくしかないのだ。
一部の過激な論調では、先進国が追加の資金負担を嫌い、「損失と損害(ロス&ダメージ)基金」などによる途上国への支援を後退させたことは、「環境正義」を切り捨てた代償として批判されるべきとの声もある。ただ、それが我々国民の生活の負担として表れてまで、途上国を助けたい者など、実生活の苦しみとは無縁な裕福な偽善者のソレでしかいないだろう。
COP30は、国際協調が機能せず、気温上昇の限界目標である1.5°目標の達成が絶望的な状況であることを示した。この瀬戸際で、性急な「再エネ正義」を叫ぶ企業と、安定性を重視し、化石燃料の延命を図る国家。そしてその現状を「無批判」に報じるメディア。
この三者の構造が続く限り、世界の平均気温は「2.5〜3度上昇する」という悲観的な予測から逃れることはできないだろう。COPの会場で起きた火災がサステナを取巻く全ての現況を暗喩しているようだった。