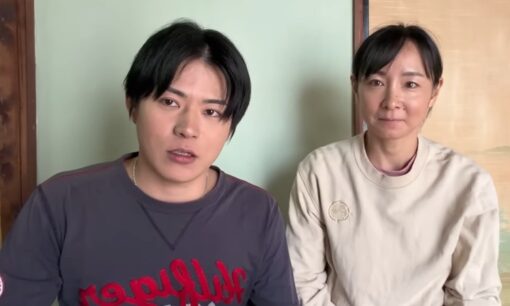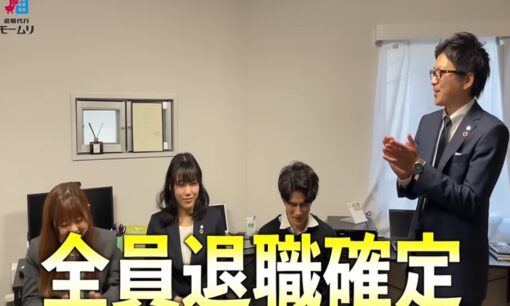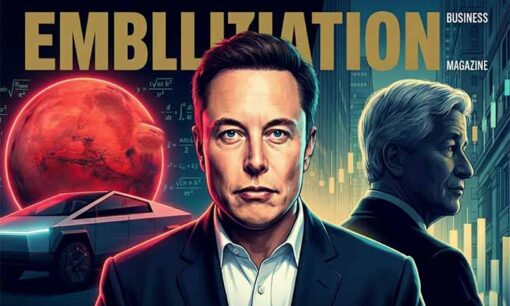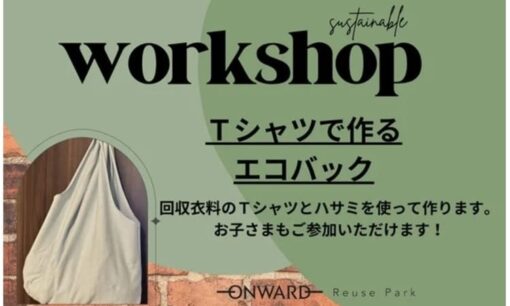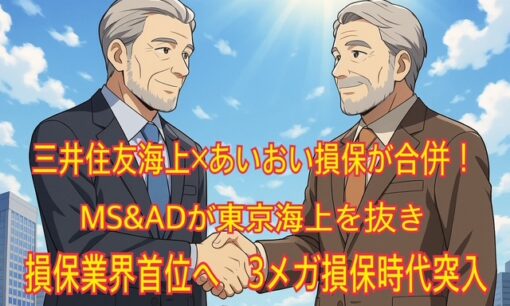元日本共産党衆議院議員の池内さおり氏(43歳)が2025年10月30日にX(旧Twitter)へ投稿した発言が、大炎上を巻き起こしている。
高市早苗首相とドナルド・トランプ前大統領の会談シーンを引用し、「高市氏をみながら、『現地妻』という悲しい言葉を思い出す」と投稿したのだ。
「現地妻」という言葉は、植民地主義の時代に女性を男性の従属物とみなした蔑称として使われてきたものであり、女性差別的・侮辱的な表現として定着している。
池内氏は11月4日に謝罪投稿を行ったが、「誤解を招く表現であった」という釈明が再び批判を招き、炎上は止む気配を見せない。
発言の経緯と炎上の火種
池内氏は愛媛県松山市出身で、1982年9月15日生まれの43歳。中央大学法学部を卒業後、21歳で日本共産党に入党。
2014年の衆議院選挙(比例東京ブロック)で初当選を果たし、内閣委員会や法務委員会に所属。ジェンダー平等やLGBTQ支援、性暴力問題の解決を訴えてきた。
「女だからとあきらめる人生にはしたくない」という信念を掲げ、女性の尊厳を守る政治家として活動してきた人物でもある。
その池内氏が10月30日に投稿した内容は、まさにその理念を裏切るものだった。
高市首相がトランプ氏と握手を交わす写真を引用し、「腰に手を回され満面の笑顔で受け入れる」姿を批判的に描写。
「日本が対米屈従の構造にある」と訴える文脈だったが、「現地妻」という言葉の使用によって発言の主旨はかき消された。
SNSでは即座に拡散され、「女性の尊厳を踏みにじる」「フェミニズムの看板を自ら汚した」といった非難が殺到した。
「現地妻」という言葉の暴力性
「現地妻」とは、戦前の植民地支配下で、外国人男性が現地女性と関係を持つ際に使われた差別的表現だ。
そこには「支配する側とされる側」という構図が明確にあり、女性を対等な存在ではなく従属的立場として描く蔑称的意味が込められている。
この言葉を政治家が用いたこと自体が、女性差別や植民地主義的意識の再生産にあたるとの指摘が相次いだ。
ある社会学者はこう述べる。
「『現地妻』という言葉は、女性を性的・政治的に“利用される存在”として扱う発想そのものを象徴しています。
ジェンダー平等を訴えてきた政治家が使えば、批判されて当然でしょう」。
池内氏は過去に「すべての人が自分らしく生きられる社会を」と訴えてきたが、今回の発言はその理念を自ら踏みにじった形となった。
謝罪文が引き起こした“第二の炎上”
11月4日朝、池内氏はX上で謝罪投稿を行った。
「高市総理を現地妻であるなどということを意図して書いたものではありませんでしたが、誤解を招く表現であったことをお詫びいたします」と述べたが、反応は冷ややかだった。
問題視されたのは、「誤解を招く」という言葉だ。
SNS上では、
「誤解なんかじゃない。あなたの投稿そのものが差別的だった」
「『意図していない』では済まされない」
「高市首相に直接謝罪すべきだ」
といった厳しい意見が並び、謝罪文が火消しどころか新たな炎上を生んだ。
さらに、「フェミニズムを掲げる政治家が、女性を侮辱する構図を利用した」との批判も相次ぎ、池内氏の政治的信頼性は大きく揺らいだ。
SNSで拡大した“信頼の崩壊”
今回の炎上がこれほどまでに拡大した背景には、SNS特有の「共感と怒りの連鎖」がある。
池内氏の発言は、フェミニズムを軽視する層だけでなく、女性の権利を重んじる立場の人々からも非難を受けた。
つまり、「敵」だけでなく「味方」からも見放されたのである。
「人権を叫ぶ人ほど差別に鈍感だ」「フェミニズムが政治の道具になっている」といった声も多く、運動そのものの信頼を損ねる結果となった。
謝罪後の11月5日現在も、SNSでは「意図がないならなぜ投稿したのか」「説明責任を果たせ」という声が続いており、炎上は収束していない。
政治家の発言がここまで波紋を広げるのは、ネット社会において言葉が“事実”よりも速く、強く拡散されるからにほかならない。
言葉の責任とフェミニズムの岐路
政治家の発言は、もはや個人の意見ではなく「公的メッセージ」である。
特にジェンダー平等や差別問題を扱ってきた人物にとって、言葉の重みは倍増する。
池内氏の「現地妻」発言は、差別を批判する側が無意識のうちに差別的構造を再生産してしまう危険を露呈させた。
今回の炎上は、政治家が「理念を掲げる者ほど、言葉の責任を負う」ことを突きつけた事件でもある。
言葉は武器であり、誤用すれば信念そのものを打ち砕く。
謝罪で済む問題ではなく、今後は政治家一人ひとりが発信の背景にある歴史や構造を深く理解する姿勢が問われている。