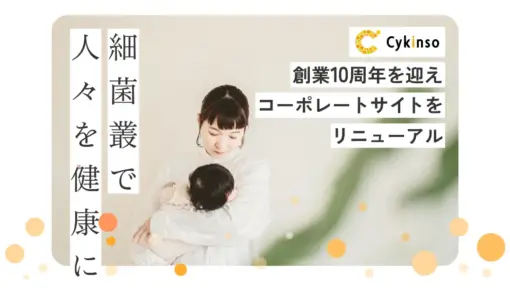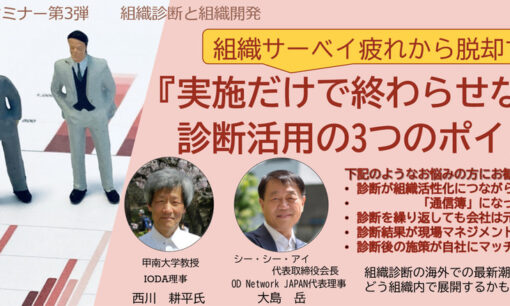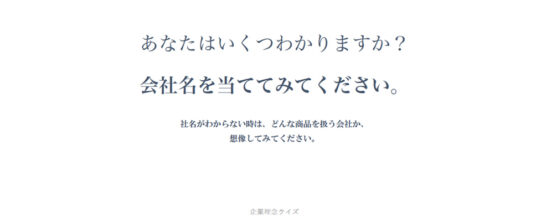経済安保担当相・小野田紀美氏が、地元での週刊誌取材に「迷惑行為」と抗議した。
「怖い」「気持ち悪い」と訴える地元の声、そしてそれをSNSで可視化する政治家。
一方で、旧来メディアは「取材の自由」を掲げ続ける。
報道とSNS。二つの言葉の武器が交錯する時代が、いま浮かび上がっている。
岡山に届いた「SOS」 抗議のきっかけは一本の電話から
秋晴れの岡山。
穏やかな町に、ざわめきが走った。
「週刊誌の人が来た」「どこで個人情報が漏れたのか分からない」。
地元住民や同級生たちの不安の声が、小野田紀美氏のもとへ相次いで届いた。
10月26日夕方、彼女は自身のX(旧Twitter)を更新する。
「取材に応じないと、なぜ断るのか理由を述べるよう言われ、追い詰められるように感じる方もいたそうです。このような迷惑行為に抗議します」
投稿は瞬く間に拡散。
「#小野田紀美」「#週刊新潮」がトレンド入りした。
政治家の発言が、全国規模の議論を呼び起こすまでに要した時間は、わずか数時間だった。
“見えなかった取材”が見える時代に
かつて、報道は現場でのみ語られた。
記者がドアを叩き、名刺を差し出す。それが「誠実な取材」とされた時代。
だがいま、取材する側の行動も、取材される側の恐怖も、すべてSNSで可視化される。
Yahoo!ニュースのコメント欄には、怒りと違和感が渦巻いた。
「地元の人に恐怖を与える取材は報道ではない」
「公開されていない連絡先にアクセスするのは個人情報保護法違反の疑いがある」
「もう昭和ではない。令和の取材を考えるべきだ」
記者がペンを構える一方で、市民はスマホを掲げ、リアルタイムで情報を検証する。
報道の“非対称性”は、すでに崩れ始めているのだ。
SNSで声を上げる政治家たち
政界でも、沈黙を破る動きが広がっている。
日本維新の会・藤田文武共同代表は、小野田氏の投稿を引用しこう述べた。
「悪質な週刊誌の取材方法。一般の人が怖いと感じるやり方でも強引になんでもあり。行き過ぎたやり方には抗議し、必要に応じてオープンにする」
「取材方法をオープンにする」。それは、報道と政治の新たな駆け引きの始まりを意味する。
記者が権力を監視するだけの時代から、政治家が報道を監視する時代へ。
SNSは、権力の向きを双方向に変えてしまった。
オールドメディア vs ネット世論
かつて情報は一方通行だった。
新聞が書き、テレビが伝え、読者は黙って受け取る。
だがいまは違う。
取材対象者も、一般市民も、自らの言葉で語れる時代。
その声が瞬時に広がり、メディアの姿勢を映す“鏡”となる。
ネット上にはこんな意見も。
「SNSがあって良かった。なければ泣き寝入りだったかも」
「報道の自由と個人の自由、どちらが重いのかを考える時期に来ている」
報道とSNSは対立しているようで、実は同じ「公共空間」を共有している。
そこに求められるのは、敵対ではなく透明性だ。
“岡山のジャンヌ・ダルク”が映した時代の鏡
米国人の父と日本人の母を持ち、岡山で育った小野田紀美氏。
2016年の参院選で初当選し、2022年には公明党の支援を受けず圧勝。
信念を貫く姿勢から「岡山のジャンヌ・ダルク」と呼ばれてきた。
高市早苗首相の新内閣で初入閣したばかりの彼女が、最初に直面したのは「報道との戦い」だった。SNSが政治を変え、取材の倫理を問い直す時代。
小野田氏の抗議は、個人の発言を超えて、「誰が真実を語るのか」という、社会全体の問いを浮かび上がらせている。