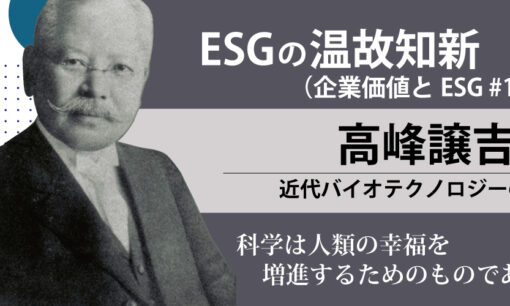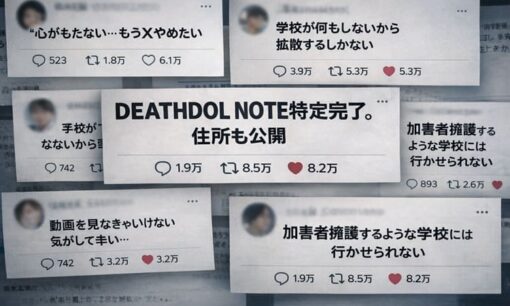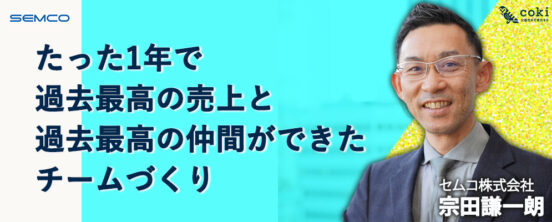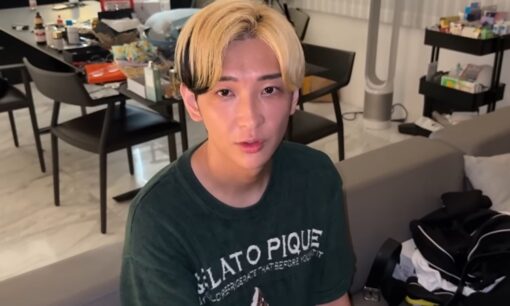半世紀前に誕生したぬいぐるみ「モンチッチ」が、再び脚光を浴びている。
SNSでの拡散をきっかけに、タイや韓国の若者の間で人気が急上昇。
いま、浅草や原宿の店先には観光客の列ができるほどだ。
懐かしさと新しさを併せ持つ、日本発の“かわいい”が世界を魅了している。
浅草の昼下がり、外国人が写真を手に並ぶ
平日の昼下がり、浅草の仲見世通りには、カメラやスマートフォンを手にした外国人観光客の姿が絶えない。
その一角にある雑貨店の前では、若い女性がスマホの画面を見せながら、英語で店員に尋ねていた。
「このぬいぐるみ、ありますか?」
画面には、茶色い毛並みとそばかすのある小さな人形。
指先にちょこんとくわえられたおしゃぶりが、どこか懐かしい。
棚の在庫を探した店員は首を横に振り、「すぐに売り切れてしまうんです」と答えた。
その言葉に、がっかりした表情の観光客がスマホを胸に抱く。
その瞬間にも、別の客が同じ写真を見せながら列に加わっていた。
浅草の通りに、かつて昭和の子どもたちを夢中にさせたぬいぐるみが、再び息づいている。
SNSが火をつけた“第3次ブーム”
ブームの火種は、海の向こうから届いた。
タイの著名人がモンチッチを抱いた写真をSNSに投稿すると、瞬く間に拡散。
「かわいい」「日本で買いたい」といったコメントが相次ぎ、タイ国内では売り切れが続出した。
その熱はやがて韓国へ広がり、人気グループのメンバーが紹介したことで、若者の間で一大トレンドに。
原宿では、ぬいぐるみやキーチェーンがバッグのアクセサリーとして売れている。
2年前に比べて売上は約20倍に伸びたという。
SNSで見た写真を手がかりに日本を訪れ、浅草や原宿の店舗を“聖地巡礼”のように巡る観光客も少なくない。
売上は3.7倍、継続が生むブランド力
モンチッチを生み出したメーカーの2024年2月期売上は6億円。
翌期には22億円(前年比3.7倍)に跳ね上がり、2026年には35億円に達する見込みだ。
半世紀を経てもなお進化を続ける理由は、ただの「懐かしさ」ではない。
このキャラクターは、1974年に誕生。
翌年にはヨーロッパへ輸出され、瞬く間に世界中で愛された。
やがて一度はブームが沈静化したが、90年代に復活。
その後も、海外の展示会出展や各国との代理店ネットワークを通じて、現在は16カ国・地域で展開されている。
製造元の担当者は「流行に任せず、市場に居続けることが大切」と語る。
やめない勇気が、ブランドを強くしてきたのだ。
「昭和のかわいい」が令和の癒しに
モンチッチが再び注目を集めた背景には、世界的なレトロ可愛いブームがある。
大きな瞳や派手な色ではなく、少し素朴で守ってあげたくなる表情。
完璧すぎない造形に、見る人の心がほっと緩む。
SNS上でも「懐かしいのに新しい」「癒やされる」といった声が相次ぐ。
一方で、製造元は伝統を守るだけでなく、地域とのコラボレーションにも積極的だ。
50周年の節目には、ぬいぐるみが“広報大使”となり、全国各地の祭りや展示会に登場。
ぬいぐるみが街を盛り上げるユニークな地域活性の象徴として、新たな役割を果たしている。
葛飾に立つモンチッチ像
東京都葛飾区の下町には、モンチッチの原点を感じさせるスポットがある。
新小岩駅北口の駅前広場には、2体のモンチッチモニュメントが並び、訪れる人々をやさしく迎えている。
2022年に公開されたこの像は、モンチッチ誕生の地・葛飾を象徴する存在だ。
モンチッチは1974年、葛飾区西新小岩の玩具メーカーで誕生したキャラクターである。
区は「モンチッチに会えるまち かつしか」を掲げ、地域ぐるみでブランド発信を続けている。
近くの西新小岩五丁目公園は“モンチッチ公園”として整備され、遊具やサインにもキャラクターのデザインがあしらわれた。
休日には、家族連れや観光客がモニュメントの前で写真を撮る姿も見られる。
ぬいぐるみとしてだけでなく、まちのシンボルとしても息づくモンチッチ。
その笑顔は、いまも地元の人々の暮らしの中に生き続けている。
「続けること」が文化を育てる
世界のキャラクター産業では、世代や国境を越えて愛される存在を「エバーグリーンIP」と呼ぶ。
ポケモン、ハローキティ、そして今、モンチッチもその仲間入りを果たそうとしている。
世界のキャラクター市場は、2024年時点で約25兆円。
2031年にはその1.6倍に拡大すると予測されている。
大企業だけでなく、中小メーカーが守り続けてきたIPも、いまや日本のソフトパワーを支える大切な資産だ。
浅草でモンチッチを手に取る外国人観光客の笑顔を見ていると、50年前に生まれた小さな命が、国や世代を越えて息づいていることを実感する。
それは、モノづくりの国・日本が誇る、もう一つのものづくりなのかもしれない。