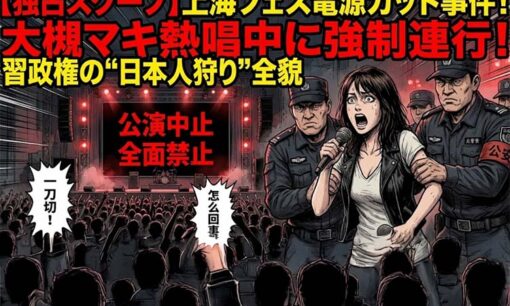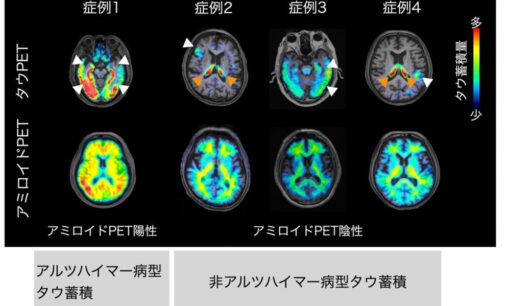男性の育休取得率はここ数年で飛躍的に伸びている。2019年には1割に満たなかった取得率が、2025年には36.3%と3倍以上に増加した。しかし「取った」ことと「役に立った」ことの間には、大きな溝がある。妻の評価と夫の認識のズレ、そして「とるだけ育休」と呼ばれる現象。いま、家庭と社会に何が起きているのか。
男性育休の取得率は上昇中、それでも残る「とるだけ育休」問題
9月19日。暦の上で「育休を考える日」とされるこの日、積水ハウスが毎年発表する「男性育休白書」が公表された。2019年の男性育休取得率は11.3%。それが2025年には36.3%にまで伸びた。背景には法改正による「産後パパ育休」の創設や、企業による取得推進がある。数字だけ見れば大きな前進だ。
ただし平均取得日数は全国で14.6日。わずか2週間あまりにすぎない。トップは沖縄県の30日、次いで石川県が22.1日、東京都が21.6日と続く。一方、地方都市の多くでは全国平均を下回り、取得期間が短い傾向がある。統計の中に、地域ごとの温度差が透けて見える。
街頭インタビューが映す現実
地方都市の駅前で、スーツ姿の20代男性は足を止め、こう語った。
「結婚はまだなんですけど、もし取れるなら取りたいです。小さい頃から子どもの成長を見守れるのは大きな魅力です。ただ復帰した時に会社が受け入れてくれる環境があるかが大事ですね」
一方、ベビーカーを押す30代女性は少し笑みを浮かべた。夫が5か月育休を取ってくれたという。
「最初の3か月は特に大変でした。そばにいてくれて本当に助かりました。精神的にも支えになって、一緒に乗り越えていると感じられたんです」
だが、その隣で夫は苦笑する。
「確かに、休憩したい時間もありました。妻がフルで家事・育児をしているときに、自分がソファで休んでいるのを見られて、イラッとされたこともあります。でも、戸惑いながらも一緒にやっていくのは貴重な経験でした」
街の声から浮かぶのは、育休を「取った」ことと「役立った」ことの間に横たわる溝だ。
「とるだけ育休」から「手探り育休」へ
白書によると、育休を取った男性の53.6%が「何をすればいいか分からなかった」と回答している。実際に「とるだけ育休だった」と自覚する男性も35.5%。妻側からも「夫はとるだけだった」との評価が39.5%に達した。
しかし最近は新しい言葉が使われ始めている。それが「手探り育休」だ。やる気はあるものの、実際にはどう動けばいいか分からず試行錯誤を繰り返す姿を指す。かつての「取るだけ」から、いまは「手探り」へと時代が変わりつつある。
妻の評価と夫の幸福感に潜むギャップ
では、夫はどの程度家事や育児を実践しているのか。調査では、食事作りやおむつ交換など28項目に分けて妻に評価してもらった。結果、妻から「とるだけ」と評価された夫の実践数は平均6.4項目。一方、「とるだけではない」と評価された夫は10.1項目を実践していた。
興味深いのは、夫が感じる幸福感との乖離だ。地方都市の多くでは、妻からの評価は全国平均を下回る一方で、夫の幸福度は上位に位置しているケースが目立つ。つまり、妻の「やっていない」という視点と、夫の「幸せだ」という感覚が噛み合っていないのだ。
ギャップを埋めるカギは夫婦のコミュニケーション
積水ハウス ダイバーシティ推進部の横山亜由美部長はこう指摘する。
「男性は『自分はやっている』と思っているのに、妻からすると『全然やっていない』と評価される。この乖離は全体的な傾向です。まずは育休中に、しっかり家庭内でコミュニケーションを取ることが大切です」
事前に「何をどう分担するのか」「どんな時間を過ごしたいのか」を話し合うだけで、育休が意味ある時間に変わる。単なる“制度の数字”ではなく、“家庭の質”を高める取り組みが求められている。
行政と企業の新しい支援策
地方都市でも行政や企業が独自の支援策を始めている。ある自治体は2025年4月から「育休応援手当」を導入し、1か月以上の育休を取得した同僚の業務を引き受けた職員に対してボーナスを上乗せする仕組みを整えた。
また、大手電力会社も「育児サポート応援金」をスタート。1か月以上の育休取得者がいる職場に対して、人数に応じて支援金を配分する。10人の職場なら年間12万円が支給される。このようにチーム全体で子育てを支える新しい発想が広がりつつある。
「とるだけ」から「共に育む」へ
男性の育休は、数値の上では確実に広がっている。だが、その内実は「とるだけ」「手探り」という言葉が示す通り、まだ過渡期にある。
大切なのは、育休を「取ること」ではなく「どう過ごすか」。妻の本音と夫の幸福感、その間にあるギャップを埋める唯一のカギは、夫婦が向き合い言葉を交わすことだ。育休は家族を育てる時間でもある。数字の先に、家庭の物語が問われている。