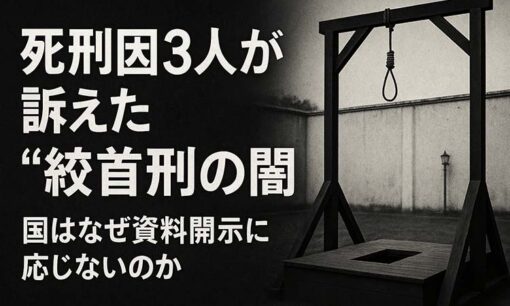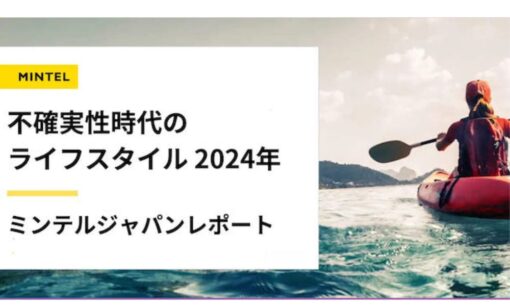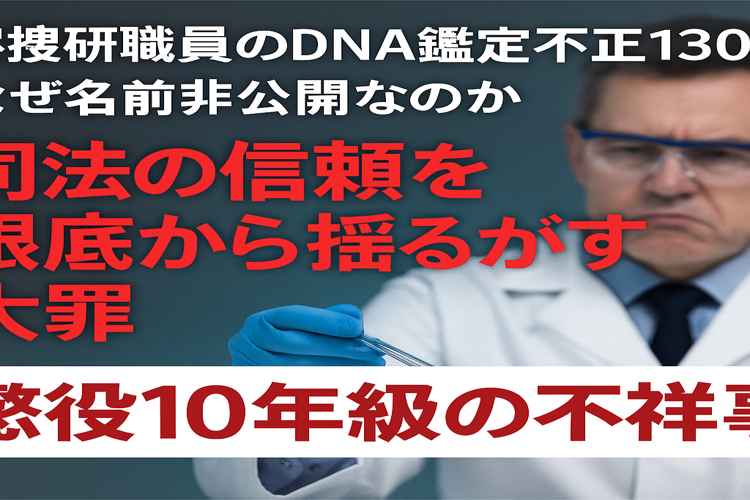
佐賀県警の科学捜査研究所(科捜研)に勤務していた40代の男性職員が、DNA型鑑定をめぐり7年間にわたって不正を繰り返していたことが明らかになった。実際には鑑定を行わなかったにもかかわらず、鑑定を実施したかのように報告し、使用したガーゼなどの資料を紛失して依頼元に別のものを返却していた。件数は計130件に上り、懲戒免職処分となった。
「上司に良く見られたい」動機
当該職員は不正の理由について、「上司に仕事ぶりをよく見せたかった。作業の遅さを指摘されるのを避けたかった」と説明した。年齢や名前は公表されておらず、処分は免職にとどまった。しかし、刑法の観点から見れば懲役10年級の重罪に値する行為であり、司法制度の根幹を揺るがす前代未聞の不祥事である。
佐賀県警の井上利彦首席監察官は会見で「2017年6月から昨年10月までの間、DNA型鑑定において不適切な行為が行われた。申し訳ない」と謝罪した。不正の一部は刑事事件の証拠として用いられていたが、県警は「捜査や公判に支障はなかった」と強調した。
裁判への影響と社会的損失
不正に関わる鑑定資料の一部は、すでに証拠として裁判に提出されている。佐賀県警は「再鑑定の結果、支障は確認されていない」と説明するが、それは組織防衛の論理に過ぎない。実際には、過去の判決の正当性が疑われ、再審請求や補償問題に発展する可能性を孕んでいる。冤罪があった場合、その被害者は人生を取り戻せない。司法の信頼は国民生活の基盤であり、その毀損は国家全体の信用をも失わせる。社会的損失の大きさは計り知れず、謝罪だけで収束させることは到底できない。
組織の責任と処罰の不均衡
不正は2017年から2023年まで7年間にわたり続いた。なぜチェック機能が働かなかったのか。上司は「気づかなかった」と弁明するが、長期にわたる放置は組織ぐるみの怠慢といえる。科捜研の所長を含む幹部の監督責任は免れず、体制そのものが問われる事態だ。
一方で、職員本人は「上司からの指摘を避けたかった」「仕事ぶりを良く見せたかった」と動機を語るが、そんな理由で行われた不正が人の人生を左右した。これほどの行為が免職と謝罪だけで済まされるのは、社会常識から大きく逸脱している。民間企業であれば倒産に直結する不祥事であり、司法機関ならばなおさら厳罰が当然である。本件職員には実刑、少なくとも懲役10年程度が妥当だという指弾が社会から相次いでいる。
SNSで広がる批判
SNS上でも、この不祥事に強い批判が広がっている。あるユーザーは「科捜研は裁判で絶対証拠になっている。130件もあれば冤罪が存在する可能性は高い。クビと謝罪だけで済む話ではない。再審を行い、この職員は懲役刑に処すべきだ」と投稿した。
また別の投稿では「上司に認めてもらいたくてやる不正のレベルをはるかに超えている。7年も気付かなかった上司も無能だし、問題を内々に処理するのは異常だ。民間企業なら倒産するほどの不祥事なのに、警察だと職員の名前も年齢も公表されない。世も末だ」と憤りが示された。
信頼回復は容易でない
今回の不正は、刑事事件の根幹を支える科学鑑定の信頼性を揺るがす重大な問題である。捜査機関の内部管理の甘さ、組織としてのチェック体制の不備が露呈した格好だ。県警は再発防止を誓うが、一度失われた信頼を回復するのは容易ではない。司法の信頼を揺るがす罪の重さを直視しなければ、再発防止も社会的信頼回復も成し得ない。