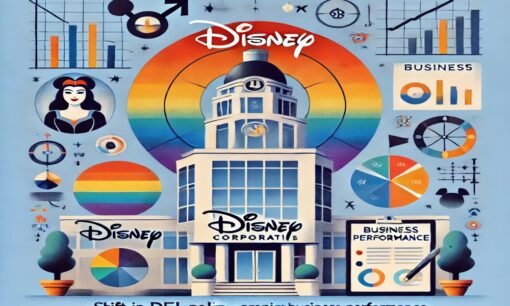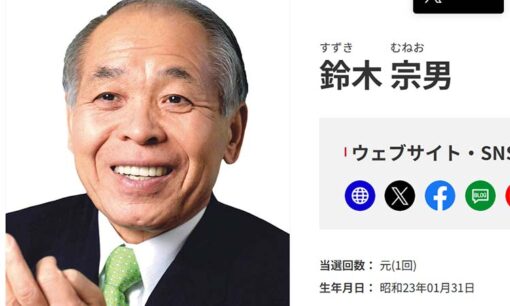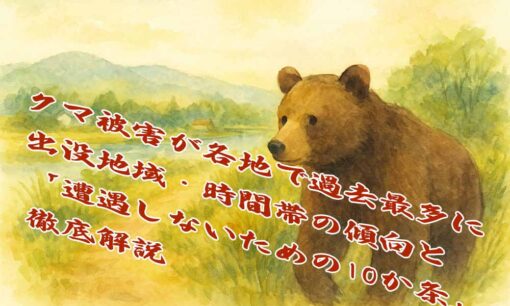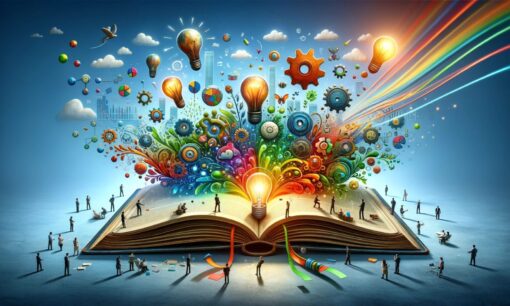日本航空(JAL)の64歳の国際線機長がホノルル滞在中に飲酒し、アルコール検査記録を改ざんしていたことが明らかになった。乗務直前までアルコールが体内に残っていたにもかかわらず、検査機器の日時を変更して「問題なし」に見せかけようとした行為は、個人のモラルを超えた深刻な組織的課題を突きつける。1985年の日航123便墜落事故から40年、安全最優先を掲げてきたはずのJALで、なぜ飲酒問題が繰り返されるのか。
ホノルルでの「一杯」が招いた事態
問題の機長は現地時間8月27日午後、ホテルの自室でアルコール度数9.5%のビールを3本飲んだ。翌28日はホノルル発中部国際空港行き便の乗務予定。午前7時以降、自主的にアルコール検査を約60回繰り返したが、呼気からは依然としてアルコールが検出された。正午過ぎのホテル出発時点でも基準を下回らず、本人が会社に申告したことで事態が発覚した。
JALの調査によれば、機長は検査機器の日時を自らの休日に変更し、あたかも乗務に影響がないかのように装っていた。過去にも10回以上、同様の改ざんを行っていたと説明している。
「要注意者リスト」もすり抜け
JALは昨年12月、メルボルン発成田行き便の飲酒問題を契機に、パイロットの現地滞在中の飲酒を禁止し、さらに「飲酒リスクの高い要注意者リスト」を導入していた。今回の機長もその対象者だった。8月には産業医面談を受け、「禁酒する」との誓約をしていたという。
しかし、結果は裏切られた。制度があっても監視の目が十分に及ばず、本人の自主性に依存する仕組みの脆弱さが露呈した。
個人のモラルか、依存症という病か
多くの読者が指摘するのは、単なる「気の緩み」ではなくアルコール依存症の可能性だ。
- 乗務直前まで飲んでしまう衝動
- 発覚を防ぐための記録改ざん
- 産業医面談後も繰り返す行為
これらは依存症の典型的な特徴に重なる。依存症は意思の強弱で解決できる問題ではなく、治療と組織的な支援が不可欠だ。JALが再発防止策を打ち出すたびに問題が続く背景には、「個人のモラル欠如」以上の構造的課題がある。
再雇用パイロットと高齢化の影
もうひとつ見逃せないのがパイロットの高齢化だ。
JALでは定年を60歳とし、身体検査基準を満たせば再雇用を認めている。今回の機長は64歳で、再雇用組だった。経験豊富なベテランである一方、体力・健康面のリスクは増す。ストレスや疲労のコントロールが難しくなり、酒に頼るケースも考えられる。
航空評論家の間では「再雇用の基準や支援体制を見直す必要がある」との指摘も出ている。
形骸化した「自主検査」
今回の問題では、検査の形骸化も浮き彫りになった。
現在は出勤前にパイロット自身が検査し、結果を記録する方式が中心だ。しかし、今回のように日付を改ざんできるのであれば意味をなさない。
読者からも「体温検査の自己申告と同じで形式的」「第三者が立ち会わなければ改ざんは防げない」との声が多い。コストや運用負担は増すが、安全を最優先するなら抜き打ち検査や対面確認を導入するしかない。
繰り返される不祥事と「安全文化」の揺らぎ
JALの飲酒問題はこれが初めてではない。
- 2024年4月、米国で機長が飲酒して騒ぎ便が欠航
- 同年12月、メルボルン発成田行き便で出発遅延、隠蔽も発覚
- そして2025年8月、ホノルルでの今回の事案
そのたびに再発防止策を発表してきたが、効果は限定的だった。
1985年、日航123便墜落事故で520人が犠牲となった。以降、JALは「空の安全憲章」を掲げ、「安全最優先」を企業文化の中核に据えてきたはずだった。しかし、飲酒問題の頻発は、その誓いが現場レベルで徹底されていない現実を示す。
信頼回復の条件とは
利用者にとって最大の関心は「次に同じことが起きない保証はあるのか」という点だ。
必要とされるのは、
- 抜き打ちを含む検査体制の強化
- アルコール依存症への治療支援制度
- 高齢パイロットの勤務実態の見直し
- 社外の監査や透明化による信頼回復
中川由起夫常務は会見で「約束を破ったことを非常に重く受け止めている」と謝罪した。しかし、謝罪だけでは信頼は戻らない。
安全文化の再生に向けて
今回のJAL機長による飲酒・検査記録改ざん問題は、個人のモラルの欠如だけでなく、アルコール依存症の可能性や自主検査の形骸化、さらには高齢化と再雇用制度の課題など、複数の要因が絡み合っていることを示した。
そして何よりも、過去に悲惨な事故を経験し「安全最優先」を掲げてきたはずのJALの組織文化そのものが揺らいでいることを浮き彫りにしたと言える。
123便事故から40年が経ついま、空の安全を守るための誓いを空虚な言葉にしないためにも、利用者の不安に正面から応える抜本的な改革と、安全文化の再生が求められている。