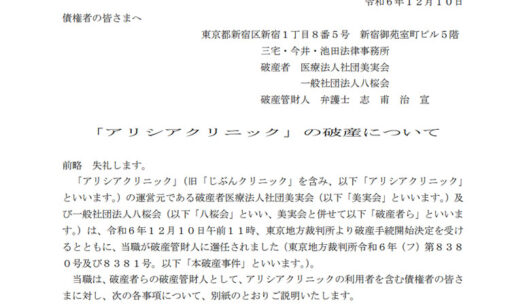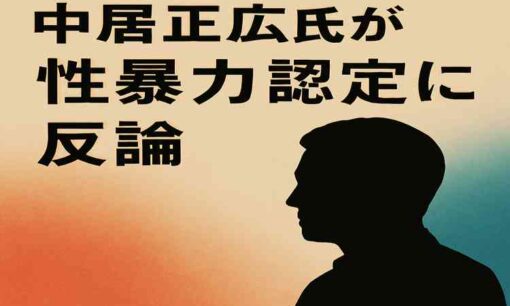7月30日、大阪湾沿岸に津波注意報が発令された際、大阪・関西万博の会場では津波の到達予想時刻を過ぎた午後0時7分にようやくアナウンスが行われた。
日本国際博覧会協会(万博協会)は「情報発信の調整に時間を要した」と釈明し、対応の遅れを認めて陳謝している。
安全確保を掲げる万博の対応に、来場者からは不安の声も上がった。未来社会の象徴として位置づけられる国際イベントが抱えた、災害対応の課題とは。
津波注意報の発令と会場内の対応経過
今回の津波注意報は、同日午前9時40分ごろ、ロシア・カムチャツカ半島沖で発生した地震を受けて大阪府などに発令されたもの。
これを受けて万博協会は午前10時に石毛博行事務総長を本部長とする災害対策本部を設置。30分後には会議を開き、会場内の安全性が確保されているとして、イベントの通常運営を決定した。
夢洲にある万博会場は地盤を8メートルかさ上げしており、予想される津波の高さ(1メートル)よりも十分に高い設計となっている。このため、防災実施計画に基づいて通常通りの運営が続けられた。
一方で、海抜ゼロメートル地点にある桟橋の使用停止や、水上交通の運航中止、周辺地域におけるシャトルバスの停止措置など、会場外の交通面では一部に制限が生じた。
「正午に到達」の予想を超えて、午後0時7分のアナウンス
注目を集めたのは、場内放送のタイミングが正午の津波到達予想時刻より7分遅れたことである。
アナウンスが行われたのは午後0時7分。協会側はこれについて、「大阪府や市と連携し、来場者が安心できるよう調整していた結果、遅れた」と説明した。
しかし、注意報発表から2時間以上が経過していたことや、情報伝達が予想到達時刻を超えてから行われた事実に対し、SNS上などでは「万博の防災体制に不安を感じた」という声も見られた。
協会は「防災計画に従った対応だったが、情報提供のあり方については改善の余地がある」と陳謝している。
災害時に求められる、誰にでも届く情報伝達
現代では、スマートフォンに緊急警報(エリアメール)が自動で届く仕組みがあることから、来場者の多くが津波注意報を認識していた可能性は高い。
しかし、全来場者がスマートフォンを所持しているとは限らず、高齢者や子ども、外国人観光客、聴覚障害者など、デジタル通知に依存できない人も少なくない。
「スマホがあるから大丈夫」とする認識では、災害対応として不十分ではないのか。
また、「どのような津波予想で、どのタイミングで放送すべきか」といった判断基準や責任体制の明確化も、今回のようなケースでは欠かせない要素となる。
「未来社会のデザイン」にあるべき災害対応とは
大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、先進的な技術や共生社会のあり方を示す国際イベントとして期待されている。
だが今回の情報伝達遅れは、その理念と現実対応との間にあるギャップを露呈する結果となった。
過去の大規模災害では、情報の遅れが被害拡大の一因となったことが繰り返し指摘されている。にもかかわらず、到達予想時刻を過ぎてからの放送という対応は、「未来社会」を掲げながら、過去と同じ課題を残していると批判されても無理はない。
万博という公共性の高い空間での災害対応は、来場者の命と直結する。防災体制の見直しはもちろんのこと、情報伝達における即時性と多様性への対応が求められている。
今後の改善に向けて
万博協会は今回の件を受け、「発信手段の改善と手順の見直しを進める」としている。
スマートフォン通知、場内アナウンス、多言語対応、アプリ連携、視覚情報など、複数の情報伝達チャネルを統合した災害対応システムの構築が必要だ。
国際イベントにふさわしい安全体制が整備されるかどうかは、今後の信頼構築に直結する。未来を語る場であるからこそ、現在の対応が試されている。