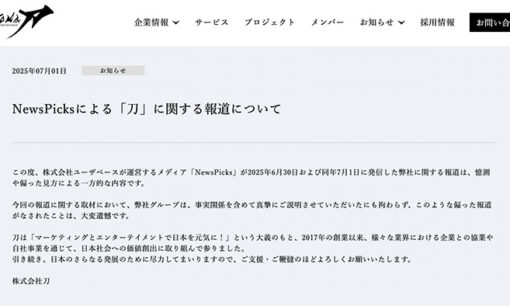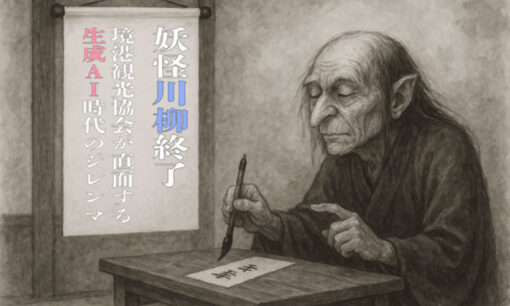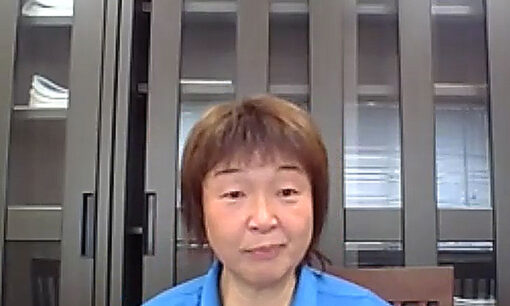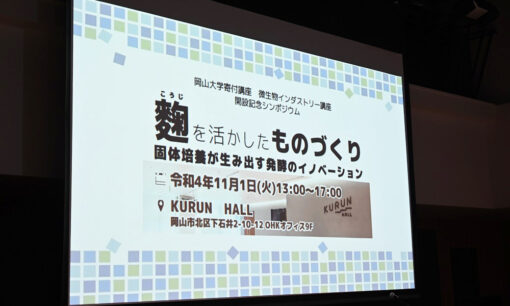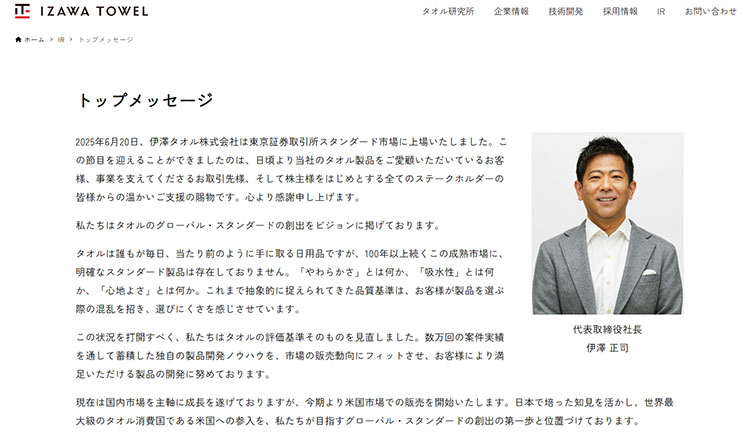
タオル業界で異例の成長を遂げ、2025年6月には東証スタンダード市場に上場したばかりの伊澤タオル株式会社。アマゾン限定ブランド「タオル研究所」やセブンプレミアム向けOEM「極ふわ」などで、日用品分野に革命を起こしてきたこの企業に、今、労働環境をめぐる重大な疑惑が持ち上がっている。
週刊文春が報じたのは、同社の伊澤正司社長による“パワハラ朝礼”の実態だった。
朝礼で社員たちを痛罵し、いびり倒す、極道さながらな音声が週刊文春電子版で開示されているが、音声を聞いているだけで、家にあるタオル研究所のタオルをゴミ箱に捨てたくなるほど、激しいパワハラ音声に驚愕する。
一方で、伊澤タオルは、業界の常識を覆す革新と理念を武器に、製品力と信頼を築き上げてきた企業でもある。読者が報道を見て抱く疑問「本当にブラック企業なのか?」「技術や製品は信用できるのか?」「社長はどんな人物なのか?」に対し、本稿では、事実と経緯を整理することで答えていきたい。
伊澤タオルとは?
伊澤タオルは1970年に大阪・泉佐野で創業。父から事業を引き継いだ2代目の伊澤正司氏は、父の死とともに未経験のまま経営を担うことになった。多くの取引先が離れていったが、「贈答品ではなく、生活者が自分で選んで買う実用タオルに徹する」という父の言葉を守り続けた。
逆風の中で同氏がたどり着いたのが、製造代行という新たなビジネスモデルだ。小売が求める細かなロット指定に応じる一方で、生産効率と品質の両立を徹底追求。その過程で、研究開発を開始し、信州大学や京都工芸繊維大学との連携により、「柔らかさの数値化」「新撚糸の開発」などの技術革新を実現した。
代表作である「♯003 ボリュームリッチ」や「♯022 新しいやわらかさ」は、柔らかさと耐久性を兼ね備えた製品として高く評価され、アマゾンでは累計販売枚数2,000万枚を超え、現在も売れ続けている。
タオル業界のスタンダードを目指していたが……
伊澤氏は「洗剤にはアタック、肌着にはヒートテックがあるのに、タオルには定番がない」と語る。彼の掲げるミッションは「タオルのグローバルスタンダードの確立」だ。
その思想は、単なる製品開発にとどまらない。信州大学と共同開発した柔らかさの5段階指標、今後導入を予定する吸水性の指標など、物性を数値化することで、消費者が「選びやすい」製品を実現してきた。
疑惑の朝礼、その実態
しかし、その開発力と成長の影で、同社の社内には異様な緊張が張り詰めていた。週刊文春が報じたのは、週に一度の朝礼における社長の暴言・恫喝・差別的表現の存在だった。
音声には「精神障害ちゃうか」「何年生きる気やねん」「座るな、立て!」などの罵声が記録され、未達成の営業目標を理由に長時間の“吊るし上げ”が行われていた様子が伝えられている。さらには、有給取得に事前の“お許し”が必要だったことや、コロナ禍での出社強制、在宅勤務の否定など、法令違反の可能性が指摘された。
実際、社員の口コミサイトなどでも「社長のワンマン体制」「部署は形式的に分かれているが、実際の決裁はすべて社長判断」「賞与が低く、他社平均に比べて不満が多い」など、労働環境の厳しさを裏付ける声が多数寄せられている。報道で公開された社長の実際の罵倒音声もあわせ、疑念は一層強まっている。
こうした朝礼の様子は、パワハラの定義に完全に合致すると指摘されており、非上場のオーナー企業であれば「そういう社風」で済まされていたとしても、上場企業としてのコンプライアンス基準からすれば、到底看過できるものではない。
社長の反論と姿勢
記者の直撃取材に対し、伊澤社長は「私はそういう人間ではない」と否定。朝礼における発言についても「恨みを持っている人が話しているのではないか」と述べ、自身の認識とは異なるとした。また、有給やコロナ出社の件についても「そんなことはない」と回答している。詳しくは週刊文春の報道を読んでいただきたいが、一方で、上場審査には6年を要し、第三者の調査が行われたことを強調し、「すでに精査された事項」と主張してもいるが、音声が開示された今となっては社長の主張は空しく響く。
伊澤タオルは、女性比率7割という職場構成や「妥協しないものづくり」を掲げ、採用基準にも「人のせいにしない人」を求めるなど、表向きには高い理念を掲げている。
しかし、朝礼の音声や元社員の証言が事実であれば、その運営手法は理念との矛盾を抱えていることになる。製品は“柔らかさ”を標榜しながら、現場は“硬直”した恐怖管理で動いていたのではないか。
問われる説明責任と今後
スタンダード市場に上場後、早々に週刊誌でパワハラが報じられた背景には、上場プロセス中にも被害を訴えた社員の存在があった可能性を否定できない。通常、上場が間近に迫るロードショー期間中には、昔働いていた社員などが「あんな会社を上場させてなるものか」と怒り心頭で、労基問題や内部通報、匿名の告発ビラなどを作り、関係者の間で飛び交うのが通例だ。今回のように、音声という客観的証拠が存在するにもかかわらず、東証や主幹事証券がこの問題をスクリーニングできなかったとすれば、「目をふさいだのではないか」という疑念すら湧いてくるが、はたしてどうだったのか。
技術も、成長も、理念も確かに本物だ。だがそれが実現される現場で、社員が適切な扱いを受けていたかは、別の問題である。
上場企業である以上、伊澤タオルには社内の実態を真摯に受け止め、調査・説明責任を果たす義務がある。社外の目線から独立した第三者委員会の設置や再発防止策の徹底など、外形的な対応が求められる段階に入っている。理念として掲げる“業界標準”の確立とは、製品だけでなく、経営そのものにも適用されなければならない。
さて、恫喝の音声流出という事態を考えると、どう考えても伊澤正司社長のリングに、“白いタオル”が投げ入れられた状態といえ、上場企業としての信頼に関わる致命傷と言えようが、ファミリービジネスである伊澤タオルのこと、この先どうなるのだろうか。