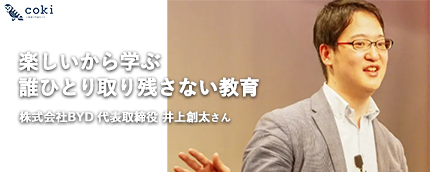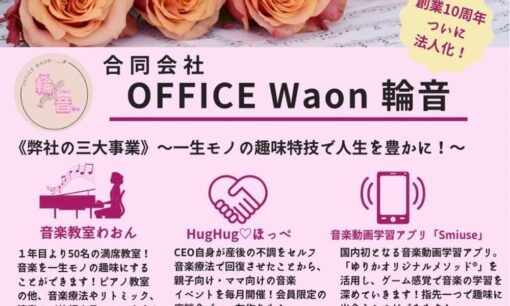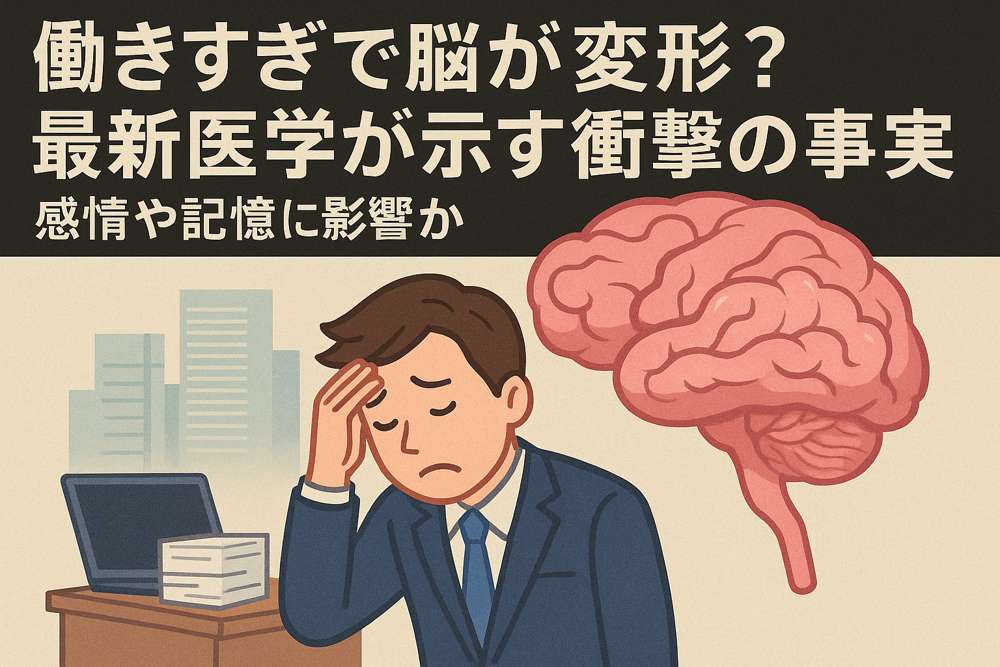
「長時間働くと体が壊れる」とはよく言われるが、最新の医学研究によれば、過重労働は脳の構造すら変えてしまう可能性があるという。特に認知や感情制御を担う脳の領域に変化が見られたとの報告が、韓国・延世大学の研究チームによって示された。本記事では、研究の詳細と共に、“働きすぎ”が現代のビジネスマンに与えるリスクについて掘り下げていく。
働きすぎは脳に何をもたらすのか
韓国・延世大学校の研究チームが実施した最新の研究が注目を集めている。彼らは医療従事者110名を対象に、週あたりの労働時間と脳の構造変化の関係を調査。その結果、週52時間以上働く「過重労働群」では、脳の認知機能や感情制御に関与する領域に明確な構造的変化が見られたという。
この研究は、英国の専門誌『Occupational & Environmental Medicine』(2025年5月)に掲載されたものであり、過重労働が脳構造に与える影響についての初の神経画像研究の一つとされている。
長時間働いている人の脳の変化
今回の研究では、長時間働いている人の脳に、ある変化が見つかった。それは「灰白質(かいはくしつ)」と呼ばれる脳の一部の体積が、普通に働いている人より大きくなっていたというものだ。
たとえば、「中前頭回(ちゅうぜんとうかい)」という考えたり計画を立てたりするのに関わる場所では、普通に働いている人より19%も大きくなっていたという。
数字だけ見ると「なんだか成長しているみたいで良いことでは?」と思ってしまうかもしれない。
しかし、脳の一部が大きくなることが、必ずしも良いこととは限らないのだ。
研究チームによると、これは脳がストレスに耐えようとして無理をしている状態かもしれないという。つまり、「働きすぎでつらいけれど、なんとか頑張って対応しよう」と脳ががんばった結果、こうした変化が起きている可能性があるのだ。
実際、うつ病や不安症の人の脳にも、似たような変化が見つかっている。だからこそ、こうした脳の変化は「病気の前触れ」になる可能性もあると考えられている。見た目にはわからないけれど、脳の中では、働きすぎによるダメージが静かに進んでいる。そんな危険性が、この研究から読み取れるのである。
なぜ脳が変わるのか?背景にある「ストレスと回復不足」
働きすぎによって脳の構造が変わってしまう。そんな現象の裏には、実は「ストレス」と「休息不足」が深く関係している。
慢性的なストレスが脳に与える影響
まず、長時間労働が続くと、心も体も休まらない状態、つまり「慢性的なストレス」を感じるようになる。ストレスを感じると、コルチゾールというホルモンが体の中で多く分泌される。
このコルチゾールは、もともとは体を守るために必要なホルモンで、短期間なら問題ない。しかし、長い間ストレスが続いてコルチゾールが出っぱなしの状態になると、逆に体に悪影響を与えるようになる。特に脳にとっては、このコルチゾールの多すぎる状態が危険だとされている。
たとえば、記憶や学習に関わる「海馬(かいば)」という部分では、コルチゾールの影響で神経細胞が弱ってしまうことがある。さらに、ストレス状態が続くと脳全体の情報処理に関わるネットワーク(神経回路)にも負担がかかり、思考力や集中力の低下にもつながる。
休めないと脳が回復できない
もうひとつの大きな原因が、「回復の時間が足りない」という問題だ。
脳も体と同じで、使いすぎると疲れる。そして、しっかり休むことでしか元の状態に戻ることはできない。ところが、長時間労働が続くと、十分な睡眠やリラックスの時間が取れず、脳が“疲れたままの状態”で動き続けることになる。
このような状態が長く続くと、脳は「もう限界だ」と判断し、本来とは違う形に変わってしまうことがある。これが、研究で見つかった「脳の構造の変化」だと考えられている。
脳の“可塑性”が落ちるとどうなる?
脳には「可塑性(かそせい)」という性質がある。これは、環境の変化に合わせて、脳の働きや形が柔軟に変わる能力のことだ。たとえば、新しいことを学んだときや、失敗から立ち直るときに、この可塑性が大きな役割を果たしている。
しかし、ストレスや睡眠不足が続くと、この可塑性が弱まってしまう。つまり、変化に対応する力が下がってしまい、柔軟に考えたり、気持ちを切り替えたりするのが難しくなる。
結果として、気分が落ち込んだり、イライラしやすくなったり、集中力が続かなくなったりする。このような状態が続くと、うつ病などの精神的な病気につながるリスクも高くなる。
小さな無理が、脳にとっては大きな負担に
毎日ほんの少しだけ残業をする、週末も少し仕事を片付ける。そうした積み重ねが、自分では気づかないうちに脳に負担をかけている可能性がある。疲れが取れない、眠ってもすっきりしない、ミスが増えた、、そんなサインが出てきたら、それは脳からの「休ませて」というメッセージかもしれない。
過重労働がもたらす他の健康リスク
働きすぎが脳に及ぼす影響は、その氷山の一角に過ぎない。世界保健機関(WHO)と国際労働機関(ILO)による2021年の報告書では、年間74万5千人が過重労働による脳卒中や心疾患で死亡しているとされる。また、厚生労働省が発表した「過労死等の労災補償状況」(2023年度)によると、精神障害に関する労災請求件数は2,000件を超えており、年々増加傾向にある。
こうした統計が示すのは、単なる“疲れ”ではなく、長時間労働が確実に身体と精神の両面にリスクを及ぼしているという事実である。
「週52時間超」は境界線 あなたは大丈夫か?
韓国で用いられた「週52時間」という閾値は、日本の厚労省が示す過労死ライン(週60時間)とも近い水準である。つまり、「平日は毎日2時間残業、さらに休日に3〜4時間働く」といった働き方は、すでにリスクゾーンにあるということだ。
特に営業職や管理職、クリエイティブ系などの裁量労働制が適用される業種では、実際の労働時間の把握が困難なケースも多く、本人が気づかないうちに過重労働に陥っていることも少なくない。
脳を守る働き方改革とは何か
コロナ禍以降、週4日勤務制やリモートワークといった柔軟な働き方が一部で進んでいるが、その導入は企業ごとに温度差がある。だが今回の研究結果は、単なる労働生産性やワークライフバランスの話ではなく、「脳の健康を守るための施策」として働き方を見直す必要性を改めて突きつけている。
企業が従業員の健康を守ることは、離職防止や生産性向上にも直結する。健康経営を掲げる企業が増えるなか、今後は神経科学の知見を取り入れた労働時間マネジメントの導入が求められる時代になるかもしれない。
脳を回復するためには
働きすぎやストレスで疲れてしまった脳を元に戻すには、特別な治療や薬を使わなくても、日常生活の中で取り入れられる「回復の習慣」が大きな意味を持つ。以下に紹介するのは、科学的にも効果が認められている、基本的だがとても重要な脳の回復方法である。
睡眠をしっかりとる
脳を休ませるうえで最も効果的なのが睡眠である。眠っている間に脳は記憶を整理し、ストレスを処理するなどの“修復作業”を行っている。6〜8時間の睡眠が理想とされるが、眠れないときは環境を整えることが重要だ。スマホの使用を控え、明かりを落とし、入浴などでリラックスしやすい状態をつくると良い。眠れない自分を責めず、目を閉じて休むだけでも脳には一定の回復効果があるとされている。
オフの時間を意識的につくる
仕事や勉強が終わっても頭が働き続けていると、脳は休まらない。大切なのは、意識的に“仕事モード”から離れる時間を設けることだ。業務の後はパソコンやメールから距離を置き、仕事と完全に切り離すことが脳の回復につながる。散歩や音楽、料理、スポーツなど、自分が没頭できる趣味に集中することで、脳の緊張がほぐれ、気持ちも整いやすくなる。五感を使った体験が、脳にとって心地よい刺激になるのだ。
まとめ:脳の“静かな悲鳴”に耳を傾ける時
「最近、ミスが増えた」「怒りっぽくなった」「記憶力が落ちた」。それは、単なる疲労ではなく、脳からの警告サインかもしれない。今回の研究は、そうした「脳の声」を、科学的に明らかにしようとしたものだ。働きすぎが、ただの“疲れ”ではなく、脳の形や働きそのものを変えてしまうかもしれない。それが、私たちに突きつけられた事実である。表面的には見えなくても、脳に深刻な影響を与える力を持っており、働き方を見直すことは、単に「楽をすること」ではなく、自分の脳と心を守るためにとても大切な行動だ。
過重労働による脳構造の変化は目に見えないが、確実にあなたの感情や記憶、判断力に影響を及ぼす可能性がある。脳は一度損なわれると回復が難しい。だからこそ、日々の働き方を見直し、「脳を守る習慣」を今から始めることが、将来の自分を守る最大の投資になるだろう。
【参照】
・Too Much Work Could Be Literally Reshaping Your Brain(science alert)
・Overwork and changes in brain structure: a pilot study(BMJ Journals)