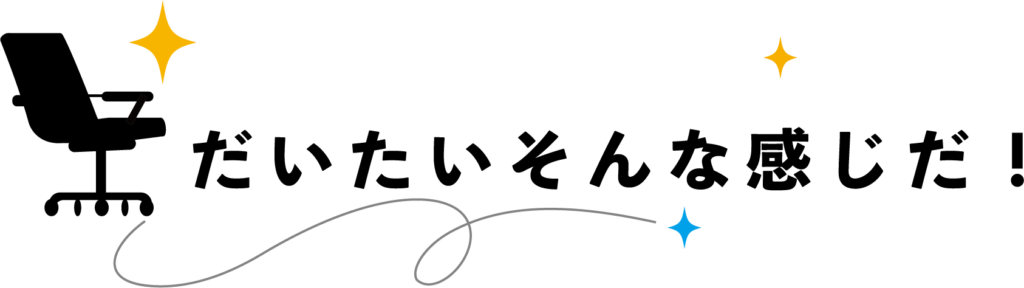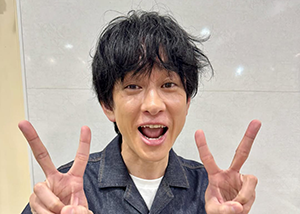最近の経済現象をゆる~やかに切り、「通説」をナナメに読み説く連載の第9回!
強いぞ、日本の映画館!
一時期、街の映画館がどんどん消えていくので、日本の映画文化が失われていくと日本中の映画通がやきもきした時代があったが、どうしてどうして。割と最近の2019年には映画館入場者数はなんと過去最高を記録しているのだ。
この数年は新型コロナで軒並み閉じた空間での人の集合が規制されたため、映画業界はさすがに風前の灯となっているかと思いきや、かなり健闘している。
無論コロナ禍で三密が禁止された時期、2020年21年の実質入場者数は半減したものの、国民がコロナ対応に順応し、22年は19年の8割程度まで復活した。
これはすごいことだと言える。海外に目を転じると、21年にアメリカの中堅映画館チェーン「Alamo Drafthouse(アラモ・ドラフトハウス シネマ)」が、22年には世界2位の館数を誇るイギリスの「シネ・ワールド」が破産法適用を申請しているし、お隣の中国では映画館だけではないが、20年に5328の映像関連会社が倒産しているからだ。とくにコロナ禍中では(コロナ自体は現在も進行中だが)、NetflixやAmazonプライムビデオ、ディズニー、Huluなど軒並み配信系制作会社が伸長し、コンテンツ制作も映画館で上映されるより、自宅のPCやタブレットからサブスクリプションで視聴できることを前提にしたコンテンツ制作が主流になっていったからだ。
NetflixやAmazon、ディズニーといった巨大資本を傍目に、日本の映画館が数を減らさず売上を伸ばしているのは実に誇らしいではないか。
衰退していた日本の映画事情を支えた背景の1つには、シネコン(シネマコンプレックス)というスタイルが登場したことがある。街中の単館の映画上映ではなく、複数の“箱”をセットで持つシネコンは、観客の趣向にあった複数の人気作品を上映できるところがミソである。それが各地のショッピングモールなどに付いたりして、買い物ついでに寄れたり、映画のついでに買い物ができたりするので、利便性と自由度が格段に向上した。
向上したのは、“箱”の環境もある。臨場感溢れるサラウンド方式のみならず、ストーリーに合わせて椅子が前後左右にうねったり、雨が落ちてきたり、霧が現れたり、その霧を風が吹き飛ばし、明るい光が射したかと思うと、高貴な香りまで漂ったりするのである。
封切りの時には監督や出演者がスクリーンの前で挨拶したり、対談をしたりするイベントも当たり前化した。熱狂的なファンを集め、スクリーンに向かって一緒に声を上げたり、ペンライトやサイリウムを振ることも珍しくなくなった。
つまり映画館は努力しているのである。もちろんコンテンツメーカーも頑張っている。
2000年代後半から増えた制作本数と、スクリーン数
一般社団法人日本映画製作者連盟のデータによれば、2000年代後半までは映画館でかけられる本数は年間600〜800本で推移していたが(もうちょっと前は500本前後)、2012年に突然983本と1000本に迫ると、翌年には1117本と一気に1100本台に突入した。以降1100本から1200本台をコンスタントに維持している(コロナが席巻した2021年以外)。これだけの本数が世に出ているということはアウトプット、すなわち映画館数が増えたことに連関しているのは言うまでもない。2005年まで2500面くらいだったスクリーン数は2006年には3062面と3000を超え、直近の2023年では3653面まで増えている。
自称「映画評論家」のワタシにとっては喜ばしい限りだ(観てる本数からすると、多分「映画好き」くらいだが…まあ“自称”だからいいのである。ただ気になるのはそのうちの3244面がシネコンであることだ。
単館の名画座的な映画館がほぼ駆逐されてしまった感があり、メジャーではない佳作や往年の名作を観る機会が減っていることは、由々しき問題だ。もちろん、ネトフリやアマプラでこうした名作を観ることは可能だが、やはり思索を巡らせながら味わうには単館系が良い、と断言してしまうのはワタシがオヤジだからだ。
監督は誰でもなれるわけでもないから、“自称監督”が居酒屋で増殖する

もう1つ、単館系が減ってしまうと困るのは、映画評論家を気取って蘊蓄を語れなくなるという問題があるからだ。かつて映画通と呼ばれる人はすべからく映画評論家と同義だった。つまりわかったようなふりをしてキャスティングからライティングから、セリフまわしから、「あーでもない、こーでもない」、やれ「美術は何々組がいい」とか、いきつけの飲み屋で“一席打つ(ぶつ)”のが習い性だったからだ。
それにしても日本人は自称映画評論家が多い。なぜか。そこには日本人の、とくにオヤジたちの抑圧された願望があるような気がするのはワタシの見立てである。
つまり「自分は到底そんな立場でディレクションしたりマネージングする立場になれないから、一流の俳優を動かすことを夢想することに悦びを見出してしまおう」という代替心理である。
考えてみれば、対戦ゲームやシミュレーションゲームの大半は、優秀な戦士や部下を集めて指示を与え、超人を育成して秘密の宝を見つけたり、お姫様を奪い返したりするたぐいだ。
さするに監督願望というのは時代や年代を超えてオヤジのみならず若者たちにも脈々と流れている不断の願望なのだと思う。
監督願望は、なにも映画に限ったことではなく、プロ野球やプロサッカーでも当てはまる。むしろそっちのほうが熱狂的である。
ワタシの学生時代の友人の一人は熱烈な西武ファンで、毎回試合を録画し、自分でスコアをつけていた。先発ピッチャー、先発メンバーが誰で、中継ぎ、抑え、代走が誰で、各選手のカウントとその結果はもちろん、気温や天気まで記録していた。
それは高校時代からやっている趣味だと言っていた。
そして、言うのである。「あそこで代打はなかったな、絶対」。
監督でもないのに。
彼はそれで肝心な大学の単位を落としてた。
そんな監督でもないのに当の監督以上に情熱を注ぐオヤジたちが、今日も盛り場のカウンターやテーブルに群がっている。
監督業は語るより学べ、会社で。
閑話休題。時代は移り変わり、いまや誰もが手軽に起業できる時代となった。ある銀行の調査では日本では30人に1人が社長だそう。もはや、カフェや居酒屋で監督やマネージング論を語るだけでなく、社長としてその独自の監督論で培ったノウハウを存分に発揮できる時代となったのだ! いでよ、若者! いでよオヤジ!
で実際に社長となったらどうかというと、軽々に監督論は語れなくなるのだ。だって下手に「あ〜だ、こうだ」というと、「結果も出せずに、語るんじゃねーよ」と手痛いしっぺ返しを受けるからね。
事実、いろいろな社長に他社の評論をお願いすると、ほとんど辞退する。語るのはコンサルとアナリストと巷のおばちゃんである。
とはいえ、否、だからこそ経営者が映画監督のマネージングや人の使い方について学んでもらいたい。なぜなら、人財や資本、設備、時間など何かと限られた企業経営において、優れた映画の制作は極めて共通する部分があるからだ。
なかでも『エレファントマン』や『ブルーベルベット』、連続ドラマの『ツイン・ピークス』で知られるデヴィッド・リンチの考え方は、多くの中小企業に取り入れてもらいたいと思う。
彼の美学は多くの俳優を魅了している。ツイン・ピークスに出演した女優のグレイス・サブリスキーはリンチについて、「とにかく彼は他の監督と違った」と語っている。「ふつう、監督には自分のイメージがあってそのイメージ通りに撮影がいかないと、『どうしてこうならないんだ!』と俳優やスタッフに向けて癇癪を起こすの。でもリンチは現場で起こる不測の事態を全部ドラマや映画の中に取り入れていくの」。
たとえば、照明係がちゃんと準備をしていたけれども、本番になったらパチパチと点滅して照明が付かなくなっても、「直さなくていいから」と言って、逆にそれを上手く利用してそのまま使うとか、撮影用のセットのテーブルをきれいにしておくように言われていたのにテーブルが汚れていると、「それは拭かなくていい」と言って、そのまま活用して撮影するという。
カルトっぽい作風と気難しそうな風貌からは、そんな融通無碍な撮影法をするとは思えないリンチだが、実際はまるでトラブルやアクシデントを楽しむように作品を作り上げている。
なぜそんな撮影が可能なのか。そこには彼の美学が反映されているからだ。
リンチはことあるごとに言う。「人生は美しい偶然の連続だ」と。つまり、日々起こるさまざまなトラブルやアクシデントすら「美しい偶然」なのだと。このリンチの考え方こそ、限られた条件のなかで奇跡のような美しい作品生み出す源泉なのである。
経営も同じである。人間の営みの美しい偶然が生み出しているのだ。そう思えば、今後起こるさまざまなアクシデントやトラブルにも自在に対応できるはずだ。何より無用な癇癪が減り、ものごとに冷静に対処できる。
経営を進化させたいなら、リンチの言葉を服膺するといい。
イマドキのビジネスはだいたいそんな感じだ。