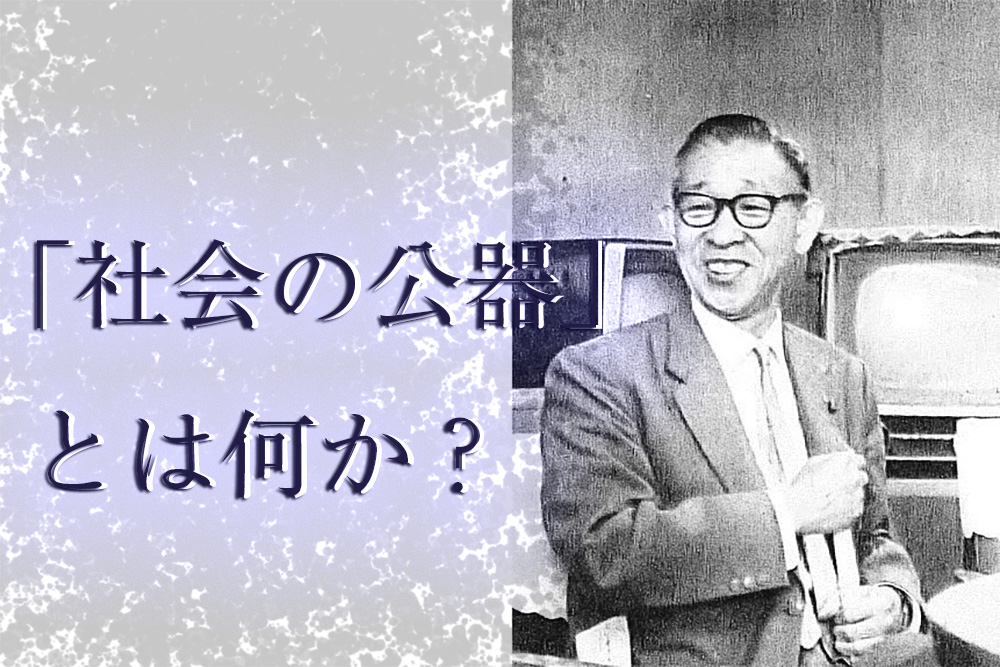
パナソニックの創業者、松下幸之助は企業にはひとつの責任があると説きました。それは企業の業種業態にかかわりません。事業規模の大小にもかかわりません。どんな企業も「おおやけのもの」という意識を持つべきとの想いを込めて「企業は社会の公器(コウキ)たれ」と言いました。
松下幸之助の考え方を紐解いていくと、企業活動そのものが社会貢献と考えていた節が見受けられます。
SDGsやESGなど持続可能な社会づくりが大きなキーワードとなっている今日に再評価されていい考え方と言えます。
サステナブルが言われるいまだからこそ、古くて新しい、この松下幸之助の考え方を紹介します。そして、一人ひとりが企業活動の本質的な意義とは何かを考えることができる時間にしたいと思います。
社会の公器とは何か?
そもそも、松下幸之助が説いた「企業は社会の公器たれ」という言葉はどこで使われたのでしょうか。これは「企業は誰のものか?」という企業所有論の嚆矢(こうし)であり、会社経営の普遍的な本質を学ぶことができる名著『企業の社会的責任とは何か?』の中に、その言葉を拾うことができます。
松下幸之助は、企業の本質的な役目について以下のように語っています。「社会の足らざるところを補い、これを潤沢に作りだすことで、世の貧困を失わせるものでなければならない」。こうした企業の責任を一言で言い表したのが「企業は社会の公器」という言葉です。
少し長いですが、該当箇所を引用します。
まず基本として考えなくてはならないのは、企業は社会の公器であるということです。つまり個人のものではない、社会のものだと思うのです。企業には大小さまざまあり、そこにはいわゆる個人企業もあれば、多くの株主の出資からなる株式会社もあります。そういった企業をかたちの上、あるいは法律の上からみれば、これは個人のものであるとか、株主のものであるとかいえましょう。
『企業の社会的責任とは何か?』松下幸之助著
しかし、かたちの上、法律の上ではそうであっても、本質的には企業は特定の個人や株主だけのものではない、その人たちをも含めた社会全体のものだと思います。
会社の所有者は、本質的には、特定の個人や株主だけのものではない。そうではなく、その人たちも含めた社会全体のもの。この考え方が、「社会の公器」の根底にある考え方になります。
そして、この考え方があるからこそ、経営者は自社を取り巻く多様なステークホルダーに目を向ける必要がでてきます。なぜなら、ビジネスをするためのありとあらゆるリソースが、社会からの預かりものだからです。経営者のものではありません。この前提に立つからこそ、お客様や社員、株主だけではなく、サプライヤーや地域住民、地球といった多様なステークホルダーに対しても、自社がどのようにして貢献していけるかを考える必要がでる、と松下幸之助は説きました。
社会の公器の原点。近江商人と石田梅岩

ところで、浅草寺の雷門は、松下幸之助による寄贈ということを知っていますか?下から覗くと、でかでかと「松下電器」の社名が書いてあります。実は寄贈に至るまでの経緯が面白いんです。
話は関西の会社である松下電器産業のお膝元に通天閣というシンボルタワーができた時に遡ります。この通天閣の一番メインの広告を関東の会社である日立製作所が抑えてしまったことを松下幸之助は悔しがったそうです。なぜ松下電器が出せなかったのだと怒り、当時の広報担当者は左遷されてしまったとか。そののち、意趣返しとして、東京のシンボルである浅草寺に寄贈をしたのだと、実しやかに言われています。
この話は、片一方の当事者に聞いた話なので、結構リアルな裏事情と言えます。松下幸之助の在りし日の人間味溢れる人となりが伝わるエピソードですね。
さて、本題に戻りましょう。企業は社会の公器なり、という松下幸之助の考え方は彼オリジナルのものなのでしょうか?
企業活動=社会貢献と言い切ったのは、松下幸之助が初めてになると思います。ただ、ビジネスは自社だけが儲ければ他はどうでもいいのだという株主至上主義のような考え方ではなく、多様なステークホルダーに利益を還元するべきという、今日的な言い方でいうところのステークホルダー資本主義的な考え方の起点は、松下幸之助がオリジナルで言い始めた考え方ではないようです。
例えば、渋沢栄一が説いた合本資本主義も同じように公益を説いていました。さらに時代を遡り、江戸時代や中世時代にまで行っても、その考え方のルーツが見て取れます。そして、この考え方は何も日本特有のものではありません。アメリカでもおそらくどの国でも昔は当たり前のように受け止められていた考え方なのだと思います。
日本でいえば、中世時代、いまの滋賀県にあたる近江地方に「近江商人」と呼ばれる商人たちが住んでいました。彼らが説いた有名な考え方に「三方よし」と呼ばれるものがあります。
いい商売の極意とは何か? それは、売った当人に利益があって、買った人も喜ぶこと。さらには世間にとってもいいのがビジネスだと。近江商人はそう考えたようです。それが「売り手よし。買い手よし。世間よし」という言葉です。この三方よしの考え方は、いまも多くの日本企業の理念に受け継がれています。総合商社の伊藤忠やお茶の伊藤園などが三方よしの会社として有名です。
また、江戸時代には、商人の神様と呼ばれる人がいました。のちに石門心学と呼ばれる学問体系を説いた石田梅岩(いしだ・ばいがん)です。彼も、いい商売とは「真の商人は、先も立ち、我も立つ」そう説いたようです。
このように会社は多様なステークホルダーの利益を考えなければならないという考え方は、いろいろな人が持っていた考え方になります。
松下幸之助を起点に過去を見てみました。今度は松下以後の社会で、ビジネスの社会貢献性がどう考えられていたのかを見ていきましょう。
CSRとは? 社会貢献のカタチの変遷

ところで、松下幸之助の説いた「社会の公器」と今日の企業が認識している一般企業の社会貢献の在り方には幾つかの誤解があると言われています。
企業の社会貢献というと、ひと昔前まで、CSR(Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任)という言葉が想起されるものでした。このCSRですが、皆さんのなかにも、「儲かっている企業がやればいい活動」と捉えられている人がいるのではないでしょうか。
CSRが残念だったのは、さながら「企業経営の添え物」といった体で解釈されてしまったことです。CSRは特定の社会貢献活動を寄付・応援をすれば十分事足りるもの。こんな屈折した考え方が浸透していきました。この「儲からない慈善活動」という誤解のせいで、伝統的な日本型経営の価値観では自然と備わっていた利他の精神の重要性が下がっていったように思います。
松下幸之助が伝えたかった本意を読み解くと、「企業活動=(そのものが)社会貢献」を指します。この文脈上、CSRも「経営そのもの」と考える方が望ましかったはずでした。
誤解が発生した理由は何なのでしょうか。2つ理由があると言われています。
1)CSRの「Responsibility」の部分 を「責任」と訳し、その範囲を主にコンプライアンスに限定させたために起こったものと言われています。
2)誰の目にもわかりやすい社会貢献活動やボランティア、寄付が持て囃されたためです。残念ながら、表層的な善行の方が理解しやすいですよね。多くの人から賞賛を得られる行為をみんな真似るわけです。こうしてCSRはいつしか具体的なアクションそのものを指すようになりました。
そして、儲かっている企業のみが、利益やリソースに余裕がある限りでやればいい社会貢献といった意味に誤認されて、一般に広まっていったのです。
こうした前提を考えると、「本業でのCSR」や「CSRからCSV」といった言葉が言われること自体が、誤解が社会に蔓延していることを示していることがわかりますね。そして、この誤解は今日にも続いています。
プライム市場に上場している企業が主に発行する統合報告書やサステナビリティレポートの内容を見ていくと、依然として、その多くが活動報告に重点を置いている点からも見て取ることができます。
CSVが説きたかったもの
やはり、CSRは「経営そのもの」と考えるべきでした。続いて、流行ったものがあります。マイケル・E・ポーター教授が説いたことで有名なCSV(Creating Shared Value 共有価値の 創造)です。この概念が次に流行りだしますが、それも本業と本業以外の活動という分け方がされている点で松下幸之助の考え方とは異なるものと言えます。
ちなみに、CSVは、2011年にハーバード大学のマイケル・ポーター教授とマーク・R・クラマー氏が発表した概念です。論文のなかで、CSVは、「社会のニーズや問題に取り組むことで社会的価値を創造し、かつ経済的価値も創造されるというアプローチである」と定義されています。
このCSVという概念の登場によって、従来のCSRはより限定的に捉えられてしまう傾向に拍車がかかりました。
松下幸之助の考えるところを本質論で語れば、企業活動に本業も本業以外の活動などという区分けは必要ありません。ありとあらゆる組織が、自社の存在意義の達成のために存在しているはず。そう考えていた節があります。
SDGsの起源

CSR・CSVと時代を経て、今日の社会2022年となりましたが、「社会貢献」という言葉で現在想起されるのは、(日本においては)やはりSDGsになると思います。SDGsが何かという説明はここでは避けます。
言いたいことは、現代にいたってやっと、企業活動=社会貢献(社会のお役に立つこと)という松下幸之助の意識と重なる部分が増えてきたように思います。
さて、ここでSDGs 成立までの経緯を簡単に紐解きましょう。SDGsは、もともと1987年に起源を遡ることができます。当時、グロ・ハーレム・ブルムントラント首相(ノルウェー)という人がいました。このブルムントラントは、国連で「環境と開発に関する世界委員会」の委員長を務めていました。
ブルムントラントは、1987年に「我ら共有の未来」と題する報告書(ブルムントラント・レポート)を発表します。この報告書が画期的でした。なぜなら、従来は、開発に関する問題はそれぞれ個別で議論されていたのです。ブルムントラントは、開発の話は環境問題と一緒に考えていかなければならない問題だよねと説いたのです。今では、多くの方が口にする「持続可能な開発」という言葉もここではじめて言及されました。
どんな開発をしていっても、緑豊かな自然や青々とした海、大気などの地球環境を守らなければ、それは人間の生活を豊かにするものにはならないという提言でした。
ブルムントラント・レポートの理念は、1992年のリオデジャネイロで開催された地球サミットに受け継がれていきます。ここから今にまでつながるCOP(気候変動枠組み条約締約国会議)が始まります。さらに、京都議定書やパリ協定につながっていく気候変動対策のラインがひかれた瞬間でした。
そして、この概念がSDGsの前進のMDGsに繋がります。MDGsは開発途上国を豊かにできるかを考えるものでした。それに対して、SDGsは先進国も含めた世界の全ての国が取り組むアジェンダです。
SDGsが国内では浸透し、事業規模の大きな会社でもESGがほぼ義務化された今日。ここにきてやっと企業各社は、自社が取り組む重要課題(マテリアリティ)を公言するようになりました。そして、SDGsの何番に取り組むということを宣言することが一般視されるようになりました。
それでもまだまだ、SDGsやESGに取り組む企業は数少ないのが現状です。
松下幸之助の考えに世界が追いつく日。SDGsの浸透
中小企業におけるSDGsの実施率は、1割というデータさえあります(エヌエヌ生命調べ・2021年)。上場企業において、ESGの統合報告書を書いている割合も3800社のうち、718社しかありません。(ディスクロージャー&IR総合研究所調べ・2022年2月)。まだ、これが現実です。
松下幸之助が説いた企業活動=社会貢献という考え方はSDGsの広がりをもって浸透するようになりました。ただし、すべての企業がこの考え方を当たり前のものと捉えるようにはまだなっていません。
しかし、SDGsに至るまでの変遷を考えると、人類は少しずつ前進しています。
松下幸之助が説いた企業活動=社会貢献が当たり前の世の中は、あともう少しでやってくるように思えてなりません。人や土地、資源といったものは全て、社会からの借りもの・預かりものという認識を持ち経営すること。社会からの預かりものだからこそ、ビジネスで利益が出た際に、経営者のみが恩恵に預かるのではなく、関わるすべてのステークホルダーに還元しなさいという意を込めた考え方。
このステークホルダー資本主義的な考え方が社会実装される日を思い描きたいですね。

















