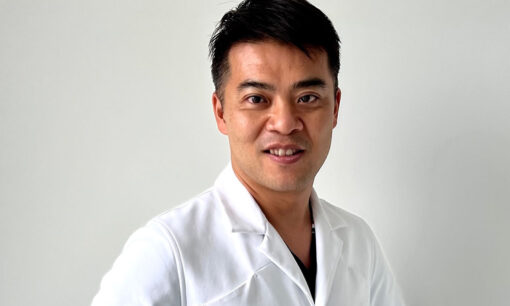2026年の幕開けは、スーパーゼネコン・鹿島建設にとって、あまりに過酷なものとなった。1月23日、天野裕正社長が心不全のため都内の病院で急逝。74歳だった。さらにそのわずか10日前には、元副社長で常任顧問を務める重鎮も、不慮の事故で世を去っていたのだ。
相次ぐ悲劇と、緊急事態の中で発表された「76歳会長の社長兼務」という異例の人事。業界関係者の間では、この一連の流れが、名門・鹿島における「創業家支配の完全なる終焉」を決定づけたと囁かれている。
盟友を失う前の予兆?
天野社長の訃報が流れる10日前の1月12日。神奈川県伊勢原市の大山(1252メートル)で、ある痛ましい事故が起きていた。登山道で下山中に体勢を崩し、帰らぬ人となったのは、鹿島の元副社長・野村高男氏(72)。妻と二人での登山中の出来事だった。野村氏は天野氏と同年代。共に現場の最前線で鹿島を支えてきた実力者であり、現在は常任顧問として社を見守る立場だった。
「立て続けに二人の重鎮が鬼籍に入るとは……。社内の動揺は計り知れません」(元鹿島社員)
この「負の連鎖」の中で、トップ不在という危機に直面したのが、会長の押味至一氏(76)だ。27日付で社長を兼務することが発表されたが、その決断の背景には、本来ならそこにいるはずのある人の不在が影を落としている。
幻となった「プリンス」の登板
前出の元鹿島社員は、声を潜めてこう語る。「5年前、2021年の社長交代時も、社内の一部で本命視されていたのは石川さんでした。しかし、当時社長だった押味さんは、現場叩き上げで腹心の天野さんを選んだ。今回、その天野さんが倒れた。年齢的にも66歳の石川さんにとって、『社長就任』はこれがラストチャンスだったはずです」
しかし、蓋を開けてみれば、選ばれたのは古希をとうに過ぎた押味氏の再登板だった。「石川氏の年齢もネックですが、それ以上に『もう創業家には頼らない』という現場の空気が決定づけられた瞬間でした。もはや鹿島は、創業家の会社(ファミリービジネス)ではなくなったのです」(経済誌記者)
「骨を拾う」ことをやめた一族
なぜ、プリンスは選ばれなかったのか。その深層には、かつて新潮など週刊誌メディアなどで指摘された「創業家はもう骨を拾わない」という構造的な変化がある。
時計の針を1993年のゼネコン汚職事件に戻そう。宮城県知事らが逮捕されたこの事件で、鹿島からも当時の副社長・清山信二らが逮捕されている。元鹿島関係者が、ゼネコンの古い「血の掟」を解説する。
「かつてのゼネコン経営は、表の技術と裏の談合、この両輪で回っていました。談合は会社利益のための『必要悪』であり、誰かが泥をかぶらなければならない。その際、万が一逮捕されても、残された家族の面倒を見、出所後の生活を保障する。つまり『骨を拾ってくれる』絶対的な権力者が必要でした。それが創業家の最大の役割だったのです」
汚れ役を厭わない猛烈な営業マンたちが、リスクを冒して危ない橋を渡れたのは、背後に「骨を拾ってくれる親分(創業家)」がいたからに他ならない。
「守るのは社員ではなく資産」
しかし、時代の変化とともにコンプライアンスが叫ばれ、「談合禁止令」が浸透すると、創業家はそのスタンスを大きく変えた。「93年の事件以降、創業家は『汚れ役』から距離を置き始めました。逮捕されるようなリスクのある社員を擁護するのではなく、自らの一族の資産とブランドを守ることに舵を切ったのです」(同前)
骨を拾ってくれる人がいなくなった組織で、誰が火中の栗を拾うのか。皮肉なことに、創業家の重石(おもし)が取れた押味体制下ではリニア中央新幹線を巡る談合事件など不祥事が相次いだ。「かつてなら創業家の威光で統制できていた部分が、タガが外れてしまった。営業マンが個人の判断で暴走し、塀の内側に落ちても、創業家は沈黙を守るだけ。これでは求心力が維持できるはずがない」(同前)
創業家支配の完全なる終焉
押味氏は2021年の社長退任会見で、前年(2020年)に亡くなった創業家出身の相談役・鹿島昭一氏との秘話を東洋経済で明かしている。押味氏は生前の昭一氏に対し、後継者問題を含め何度も相談を重ね、暗に「大政奉還」を打診したこともあったという。しかし、昭一氏は「中核である建設業をしっかりやるべきだ」と、創業家の復帰を強く固辞したとされる。結局、鹿島は本家の跡取りであった鹿島光一元取締役が外れた時点でファミリービジネスであることをやめていたのかもしれない。
そして今回、石川洋氏という最後のカードも切られることはなかった。これは、鹿島が「創業家という精神的支柱」を失い、他の上場企業と同様、純粋な「事業会社」になったことを意味するのではないか。
「押味会長の再登板は、創業家に『大政奉還』する道が断たれた今、自ら蒔いた種を含め、鹿島のすべてを背負って立つという覚悟の表れでしょう。骨を拾う者がいないなら、死ぬまで戦うしかない。それがサラリーマン社長の孤独な末路です」(同前)
悲劇の1月を経て、名門ゼネコンはどこへ向かうのか。その行方は、老練な会長の双肩にかかっている。