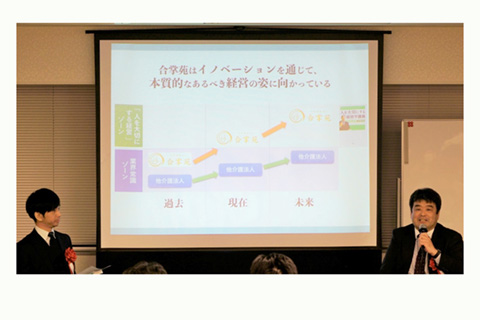イオンファンタジーが運営する屋内プレイグラウンド「ちきゅうのにわ」で、ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)の店舗で廃棄されていた“コーヒーかす”を再利用するアップサイクル体験が実施された。遊びながらSDGsを学ぶサステナブル教育として、親子連れを中心に注目が集まっている。
コーヒーかすが“資源”に生まれ変わる KFCとイオンファンタジーの共創イベント
イオンファンタジー(本社・千葉市美浜区、藤原徳也社長)は、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(本社・横浜市、遠藤久社長)と協働し、全国の「ちきゅうのにわ」店舗で「コーヒーグラウンズで消臭剤をつくろう!」を開催した。期間中、約700人の子どもたちが参加し、KFC店舗で出るコーヒー抽出かすを“資源”として再利用するプロセスを体験した。
ワークショップでは、子どもたちが巾着袋に自由に絵を描き、その中に乾燥させたコーヒーグラウンズを詰めてオリジナルの消臭剤を完成させる。香ばしいコーヒーの香りが漂う会場では、親子で笑顔を交わしながら、廃棄物が新しい命を得る瞬間を実感していたという。
“コーヒーグラウンズ”とは? 廃棄物を「再定義」した発想の転換
「コーヒーグラウンズ」とは、抽出後に残るコーヒー粉のことである。従来は“コーヒーかす”として扱われてきたが、その栄養価や吸着性などの特性が見直され、全日本コーヒー協会により近年「コーヒーグラウンズ」と呼称されるようになった。
この取り組みは、単なる廃棄物削減にとどまらない。日常のなかにある“見過ごされた資源”を再評価し、再利用へとつなげる社会的実践である。KFCとイオンファンタジーの連携は、異業種協働によるサステナビリティ活動の好例として、今後の企業間連携モデルの一つになりそうだ。
「遊びながら学ぶ」SDGs教育 “ちきゅうのにわ”が描く未来
イオンファンタジーが展開する「ちきゅうのにわ」は、0歳から12歳までを対象にした屋内プレイグラウンドである。自然や地球をモチーフにした空間デザインのもと、子どもたちは遊びながら環境や命の大切さを体験的に学ぶことができる。
同社はサステナビリティ経営のマテリアリティとして「脱炭素社会」「循環型社会」「生物多様性の保全」を掲げており、今回のような体験型プログラムはその理念を象徴するものといえる。
今後も11月には「コーヒーグラウンズでおえかきをしよう」、12月には「カプセルとコーヒーグラウンズでアート作品をつくろう」といった新企画が控える。こうした連続的なイベントを通じて、子どもたちは“遊び”の延長で環境問題を自分ごととして考える機会を得ている。
サステナビリティを“感覚”で理解させる試み
教育現場でSDGsが掲げられて久しいが、子どもたちにとって「持続可能な社会」は抽象的な概念にとどまりがちだ。その課題を、イオンファンタジーは“体験”というアプローチで解決しようとしている。手で触れ、匂いを感じ、作品を持ち帰ることで、環境保全の重要性を五感で理解できるのだ。
「コーヒーかすがゴミじゃない」――そう気づいた瞬間、子どもの中に芽生える新しい価値観。その変化こそ、同社が掲げる「遊びと学びの融合」が生み出す本質的な教育効果といえる。
廃棄物を“教材”に変える企業の哲学
KFCとイオンファンタジーの協働は、企業の社会的責任を体験価値として届ける新しい形を示している。単なるCSR活動ではなく、参加者の行動変容を促す教育的な仕組みとして設計されている点が特徴だ。
イオンファンタジーの試みは、企業活動が地域社会にどう貢献できるかという問いへの一つの答えであり、遊び場という“日常の入り口”を通して持続可能な未来への意識を広げている。こうした動きが全国に波及すれば、日本発のサステナブル教育モデルとして海外にも展開できる可能性がある。