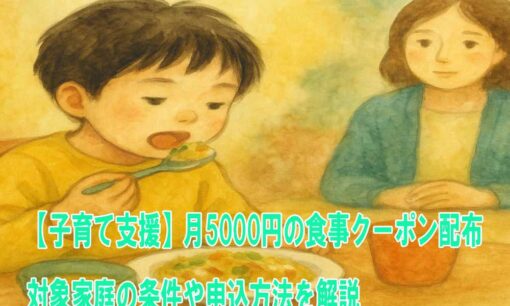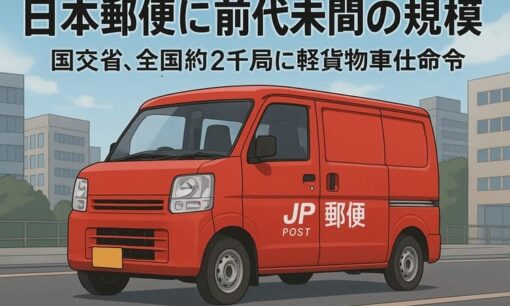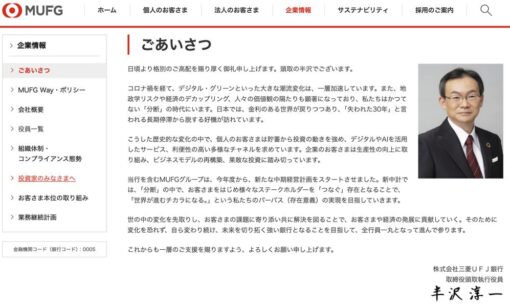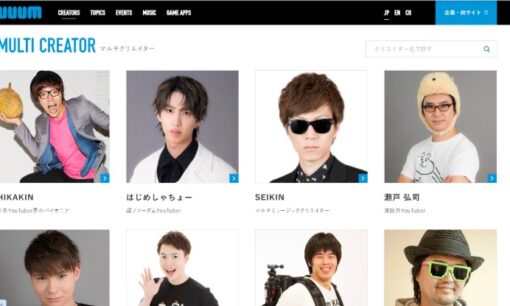東京都渋谷区代々木4丁目の区有地に建つ複合施設「おやこ基地シブヤ」をめぐり、認定NPO法人フローレンスが区に「抵当権」設定として申請しながら、実際には「根抵当権」を設定していたことが明らかになった。
補助金を使って建てた建物に根抵当権を設定することは、補助金適正化法上、原則として制限される行為とされている。2025年11月8日、渋谷区議のすだケン氏が所管に確認した結果として、申請内容と実際の登記に齟齬があったことを公表し、「明確にNG」とSNSで投稿したことで、問題は広く注目を集めつつある。
「抵当権」で承認、「根抵当権」で登記
「本日所管に確認しました。明らかにアウトと思われる部分は、渋谷区に対しては『抵当権』設定を申請していながら、実際に設定したのは『根抵当権』だったという事です」
すだケン区議はXでこう投稿し、続けて「補助金を使った建物について『根抵当権』は明確にNG」と指摘した。
関係者の説明によると、渋谷区は2017年10月に「抵当権設定」を条件として承諾を出したが、同年12月、登記上は「根抵当権」が設定されたという。区議によれば、これは承認内容と異なる類型であり、補助金対象資産の「処分」とみなされる可能性があるとされている。
社会的評価の高いNPO法人で浮上した問題
フローレンスは、2004年の設立以来、病児保育や小規模保育事業などで社会的評価を得てきた認定NPO法人だ。創業者であり現会長の駒崎弘樹氏は、政府の少子化対策や働き方改革に関する有識者会議にたびたび参加し、社会起業家としても知られてきた存在である。
そのフローレンスをめぐる今回の指摘は、NPOと行政との契約手続きにおける管理のあり方を改めて問うものとなっている。
公的資金約1.3億円が投じられた「おやこ基地シブヤ」
「おやこ基地シブヤ」は2017年7月に竣工し、同年10月に開設された。延床面積は約143坪で、建設費には渋谷区の補助金約9700万円、日本財団の助成金約3400万円が充当された。合計約1億3100万円の公的支援が投入された施設であり、区有地は30年間の定期借地契約で、路線価を基準にした低廉な賃料が設定されている。
建物の登記簿によると、所有権はフローレンスが89%、関連法人が11%を保有している。2017年12月には、地元金融機関が同建物に根抵当権を設定。登記には極度額や債権範囲が記され、将来の借入を含めた不特定債権を担保する仕組みとなっている。
補助金会計に詳しいコンサルタントの諸勝文氏は、SNS上で次のように解説している。
「補助金で整備した建物を担保に入れる行為は原則禁止。例外として『抵当権』のみ承認されるが、『根抵当権』は不特定債権を対象にするため、法的に問題がある」。
「抵当権」と「根抵当権」の違いと法的リスク
抵当権は特定の融資など、限定された債務を担保する権利であり、完済すれば効力を失う。一方、根抵当権は上限金額の範囲内で将来発生する複数の債務を包括的に担保できるため、行政の承認を得た補助資産への設定としては異例の扱いとなる。
補助金適正化法第22条では、補助金で取得した資産の譲渡や担保設定などの「目的外使用」を原則として禁止しており、行政が事前に承認する場合は対象となる債権を明確にした抵当権に限られるのが一般的だ。
不特定債権を含む根抵当権は、法の趣旨からも慎重な運用が求められるハズであった。
渋谷区、金融機関、法人の“三重の確認不備”
問題はフローレンス側の登記内容だけでなく、渋谷区および金融機関の確認体制にも及ぶ。
通常、区有地に建つ建物を担保に入れる場合、地権者である渋谷区の承諾書が必要となる。承諾書には権利移転や競売時の取扱いが明記されるのが一般的だが、今回のケースでは「抵当権」と記された承諾書をもとに、実際には「根抵当権」が登記された可能性が指摘されている。
登記完了後、区が内容を確認していなかったことも区議の調査で明らかになった。すだケン区議は「区は承諾後の登記内容を確認しておらず、行政監督として課題がある」とし、今後の議会質疑で追及する意向を示している。
SNSでの反応と拡散 「令和の大スキャンダル」
SNS上では、この件を令和の大スキャンダルに発展するのではと見る投稿が目立っている。10月より、フローレンスグループ会長駒崎弘樹氏とSNS上で舌戦を繰り広げ、今回のフローレンス問題の火付け役ともいえる、ニューマン社長の大郷大介氏は「補助金で建てた建物を担保に入れるのは、子どもの奨学金をパチンコに使うようなもの」と強く批判した。
ただし、問題は単なるスキャンダル報道にとどまらない。区議らのヒアリングで、フローレンスは2017年度末時点で約6億2800万円の現預金を保有していたことが明らかになっており、資金難を理由とした担保設定ではなかったことがわかっている。
これに対し、「なぜ十分な資金がある中で補助資産を担保に入れる必要があったのか」という根本的な疑問も浮かび上がっている。
フローレンスは沈黙、区議会での追及へ
現時点でフローレンス側はこの件に関するコメントを出していない。すだケン区議は「重大な契約上の問題について根抵当権抹消で幕引きを図るのではないか」と懸念を示し、「本会議で詳細を確認していく」と表明した。
渋谷区は補助金契約書、承諾書、登記記録などの照合を進めており、議会での説明が待たれている。
制度的背景 「公と民」の境界が曖昧に
今回の問題は、行政とNPOの協働体制における制度的な曖昧さを浮き彫りにした。補助金や助成金で整備された資産は、形式上は民間の所有でありながら、実質的には公的資産としての制約を受ける。そのため、行政・金融機関・法人の三者による確認が不可欠となるが、いずれかの段階で監視が形骸化すれば、今回のような事例が生じかねない。
渋谷区では2017年の認可保育所公募で、定員60人未満の施設が特例的に採択された経緯もあり、区の裁量的判断が制度的な不整合を生んだとの見方も出ている。
補助金・借地・登記・金融契約が複雑に絡む構造は、他の自治体にも共通するリスクといえる。
「透明性こそ、信頼の礎」
すだケン区議の調査により、「抵当権」申請と「根抵当権」登記の齟齬は明らかになった。補助金額や助成金情報、登記簿の内容が整理されつつある一方で、渋谷区・銀行・フローレンスのいずれも現時点で公式な説明を行っていない。
行政・金融・NPOの三者がそれぞれの責任を果たさなければ、公的資産への信頼は揺らぐ。
社会課題の解決を掲げるNPOほど、説明責任と透明性が問われる。今回の根抵当権問題は、登記上の瑕疵を超えて、公金を扱う制度全体の信頼を試す事案となっている。
渋谷区議会での追及とフローレンス側の説明が、制度の透明性を取り戻す契機となるか注目される。