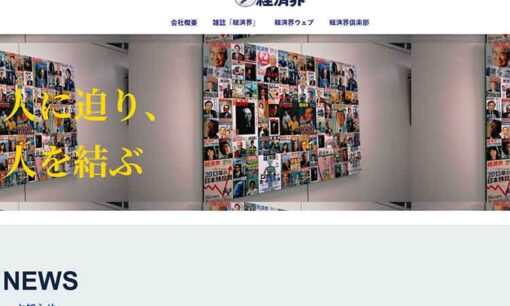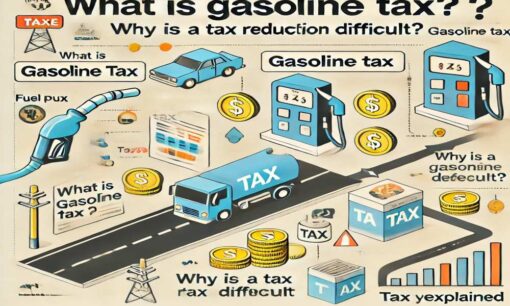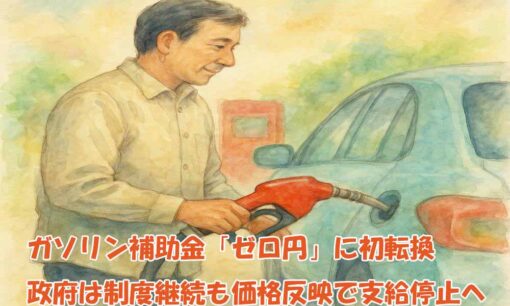あぶらとり紙のイメージからの脱却へ
 國枝昴代表(提供:よーじやグループ、以下同)
國枝昴代表(提供:よーじやグループ、以下同)
あぶらとり紙のパッケージといえば、手鏡に映る女性を描いたあのデザインを思い浮かべる方も多いだろう。「よーじや」は、京都土産の代名詞として、長く観光客に親しまれてきた。
だが今、その「観光ブランド」としての顔を再定義しようとする動きが始まっている。
今回は、創業から120年を超える「よーじやグループ」の代表取締役・國枝昂さんに、地元・京都と向き合う企業としての姿勢、そしてリブランディングに込めた想いについて伺った。
観光偏重から地元へ 原点回帰の決意
 よーじやのあぶらとり紙
よーじやのあぶらとり紙
2025年3月にリブランディングを発表されました。なぜ今、変革に踏み切ったのでしょうか。

國枝
私が代表取締役に就任したのは2019年。その半年後にコロナ禍が始まりました。京都は観光地として栄えてきましたが、観光に依存しきった構造は非常に脆弱だったことを、あの時思い知らされたんです。
弊社も例外ではなく、売上が最大で97%減という厳しい状況に直面しました。京都の街に人がいなくなったときに、地元のお客様との接点がいかに希薄だったかに気づかされました。
私は子どものころから“よーじやの息子”として育ちました。ですが、正直に言えば、幼い頃から違和感があったんです。地元の友人たちが、よーじやの商品を日常的に買ってくれることはほとんどなかった。
皆“あそこは観光客向けの店だから”と距離を置いていた。私はそんな光景を見ながら、“自分たちの会社なのに、なぜ京都の人に使われていないんだろう”と感じていました。
だからこそ、今回のリブランディングでは“京都の人に応援される企業”という原点に立ち返りたいと強く思っています。
 本店の外観
本店の外観
テレビブームが変えた「町の化粧品店」
そもそも「よーじや」は、地元密着型の企業だったと伺いました。

國枝
はい。創業は1904年。舞台化粧品や輸入化粧品を扱う、今でいう町の化粧品店のような存在でした。
戦後、一般消費者にも広がる中で、オリジナル製品も生まれましたが、今のような観光業寄りの姿になったのは1990年代以降です。
あぶらとり紙がテレビで取り上げられてブームになり、全国から観光客が殺到しました。大きな転機でしたが、それと同時に地元との距離は広がっていったとも言えます。
テレビと観光が変えた会社のかたち。そこに葛藤もあったのですね。

國枝
1990年代、テレビドラマであぶらとり紙が取り上げられたことがブームのきっかけでした。
商品が一気に全国に知られるようになり、当時はお客様が列をなして店の前に並ぶほど。ですが、それによって“地元の人がふらっと立ち寄れる化粧品店”という性格は大きく変わっていきました。
観光客対応で忙しくなる中、京都の人たちは次第に足を遠ざけていったんです。そうやって、“よーじやは観光の会社だ”というイメージが定着してしまいました。
「よじこ」とロゴ再編が示す企業の姿勢
 コーポレートキャラクター「よじこ」
コーポレートキャラクター「よじこ」
新たに導入されたコーポレートキャラクター「よじこ」も話題ですね。

國枝
手鏡に映る女性を描いたロゴは、あぶらとり紙ブームと同時によーじやの象徴となりました。
長く“ブランドそのもの”として使ってきましたが、それゆえに“よーじや=あぶらとり紙”というイメージが強く固まってしまった。
今回はそのロゴをあぶらとり紙の顔として明確に位置づけ、新たにブランドのロゴと、企業全体を表すキャラクター「よじこ」をつくりました。
デザインは『Suicaのペンギン』などを手掛けるイラストレーターとして知られる坂崎千春さんにお願いし、より親しみやすく、親近感を持てる存在になりました。
企業としての「あり方」を問い直したリブランディングだったのですね。

國枝
おっしゃる通りです。
“伝統を壊すのか”という声もありましたが、私はむしろ伝統を守るために変えるべきだと考えました。本来の『よーじや』は、京都の暮らしに寄り添うブランドであったはず。その原点に戻るための一歩です。
ロゴやキャラクターだけではありません。今回のリブランディングでは、新たに『ブランドロゴ』『コーポレートロゴ』を作成し、手鏡に映る女性を描いたロゴの役割を社内外に明確にしました。
これまで一つのロゴにすべてを背負わせていた状態から脱却し、それぞれのロゴが担う意味を整理したんです。これは内部の意識変革にもつながりました。
「地元に応援される企業」をもう一度

國枝
約130点にのぼるスキンケアや雑貨商品を展開し、毎月新商品を開発しています。
京都の観光地だけでなく、ロフトや百貨店での取り扱い、ポップアップストアの展開、ECでの販路拡大など、“京都に行かなくても買える”仕組みづくりを進めています。
同時に、地元の方に“また来たくなる”“応援したくなる”店づくりを意識し続けています。
企業スローガンに「みんなが喜ぶ京都にする」と掲げられています。地域に具体的に言及するのは非常に珍しいかと。

國枝
はい。私たちは、京都という土地に支えられてきた企業です。ただ“京都ブランドだから”という理由で買っていただくのではなく、“京都の人が誇れる存在”でありたい。その想いを込めました。
将来的には、地域活動への参加など、企業として“まちづくり”にも積極的に関わっていきたいと考えています。
最後に、京都で育ち、よーじやを継いだご自身にとっての「地元」とは?

國枝
私にとって京都は、“好きだから”というより、“責任を持ちたい場所”です。あまりにもブランドイメージだけが先行してしまったこの街で、商いをする意味をもう一度問い直す必要がある。
よーじやという名前に頼らず、いかに地元の人の信頼を取り戻すか。今ようやく、そこに真正面から向き合える覚悟ができたと思っています。
ちなみに、私が代表取締役に就任したのは父の心筋梗塞がきっかけでした。
事業承継のタイミングとしては想定外でしたが、ある意味で“腹を括る”にはちょうどよい機会だったのかもしれません。実は、それまで私は“ブランド”というものがあまり好きではなかった。
人気やロゴでモノが売れることに違和感を持っていました。でも、だからこそ、今のように“ブランドを使って何を伝えるか”を考え抜く立場になれたのだと思います。