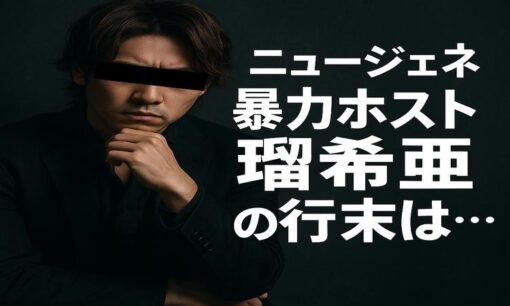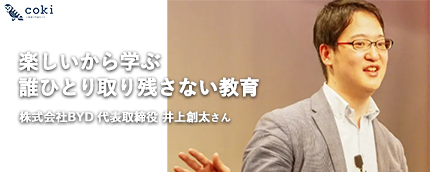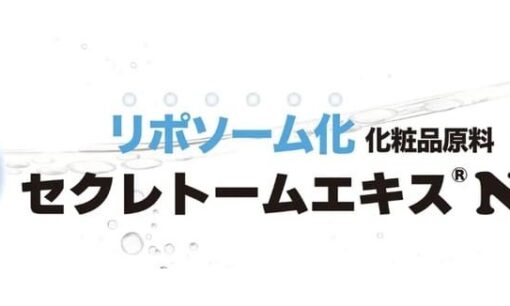吉沢亮主演の映画『国宝』(李相日監督、東宝配給)が公開から3か月で興行収入110.1億円を突破し、実写邦画として歴代2位に躍り出た。興収100億円超えは2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』以来、22年ぶりの快挙である。原作は吉田修一氏が2017~18年に朝日新聞で連載した小説『国宝』。任侠の家に生まれながら歌舞伎の名門に引き取られた主人公が、芸の道に生涯を賭ける半世紀を描いた長大な物語だ。公開当初から口コミで評判が広がり、異例のロングランを続けている。
原作の再評価と出版界の熱気
映画の成功は出版界にも波及した。朝日新聞出版が刊行した『国宝』(上下巻、青春篇・花道篇)は累計130万部を突破。映画公開を契機に売れ行きが再加速し、新聞社発の文学作品が再び脚光を浴びる格好となった。社内の一部では「久々に明るい話題」と沸き立ち、出版事業の存在感を示す結果となった。
SNSが生んだ「口コミの奔流」
ヒットの原動力となったのはSNSの拡散だ。X(旧Twitter)やInstagramでは「吉沢亮の芝居に心を持っていかれた」「歌舞伎を知らなかったけど涙が止まらなかった」といった声があふれる。
特に若い観客層から「伝統芸能をテーマにした作品で初めて泣いた」との感想が相次ぎ、映画館に足を運ぶ動機となった。リピーター鑑賞を勧める投稿も多く、観客が宣伝塔となって作品を後押しする現象が広がった。
劇中のクライマックスで描かれる『曽根崎心中』は「映画史に残る名場面」と評され、上映中に劇場全体が静まり返る瞬間を体験した観客の証言がSNS上で共有され、さらなる観客を呼び込んでいる。
『悪人』の成功体験と今回の不在
今回の成功を前に、朝日新聞社内でしばしば引き合いに出されるのが2010年公開の『悪人』だ。2006~07年に同紙で連載された吉田修一氏の小説を、李相日監督が映画化。
深津絵里、妻夫木聡らの熱演によって映画賞を総なめにし、興収19億円の大ヒットとなった。当時、朝日新聞と朝日新聞出版は製作委員会に名を連ね、原作・出版・映画の三位一体の成果を享受した。
それだけに、『国宝』で両社が製作委員会から外れている事実は社内外に驚きをもって受け止められた。
なぜ今回は関与しなかったのか。複数の関係者によれば、理由は「経営の厳しさ」と「題材の過小評価」にあったという。新聞発行部数の減少や広告収入の低下が続くなか、経営会議では映画事業への投資に慎重な意見が多数を占めた。
ある社員は当時の会議をこう証言する。
「映画事業部門の担当者は『吉田作品と李監督の再タッグは絶好の機会』と強調しました。
しかし経営側からは“歌舞伎は敷居が高く一般層には響かない”“100億円突破など夢物語だ”との声が相次ぎました。結果的に、社会派大作『宝島』(真藤順丈原作)の映画化に投資が回されることになったのです」
経営判断としては理解できるものの、結果的に110億円超えという空前の成功を見逃すことになった。
社内に残る悔恨と“読み違え”
映画が連日満席を記録するなか、社内には「なぜ出資しなかったのか」という悔恨が広がっている。「『悪人』の成功体験を自ら放棄した」「世相を読む力が鈍った」との声が上がり、
文化を発信する新聞社としての存在意義に疑問符を投げかける社員もいる。SNS上でも「原作の版元が映画に関わらないのは不自然」「朝日新聞は文化事業のセンスを失ったのか」といった批判が散見され、広報的にも痛手となった。
『国宝』の劇中で描かれる『曽根崎心中』では、主人公が“死ぬる覚悟”を演じきる。その姿に観客は心を揺さぶられ、劇場は沈黙に包まれる。
だが、製作委員会に参加しなかった朝日新聞の姿勢は、まるでその「覚悟」を欠いていたかのように映る。広報部は「製作委員会に入っていないのは事実だが、個別の経営判断の詳細は答えられない」とコメントするにとどまった。
国際舞台へ、置き去りにされた版元
『国宝』はすでに2026年の米アカデミー賞国際長編映画賞部門の日本代表に選ばれている。国内での歴史的ヒットに加え、世界的評価を勝ち取れば、朝日新聞の“読み違え”はさらに際立つことになるだろう。
ある映画関係者はこう指摘する。
「文化的資産を活かすべき新聞社が、自社連載小説の映画化で成果を取り逃した。これは業界全体の縮図だ。伝統メディアが文化の担い手であるためには、経営的リスクを取る“覚悟”が求められる」
『国宝』の大ヒットは単なる映画興行の成果ではなく、新聞社や出版界が文化事業をどのように位置づけ、社会的価値としてどう活かすかを映し出す鏡となった。