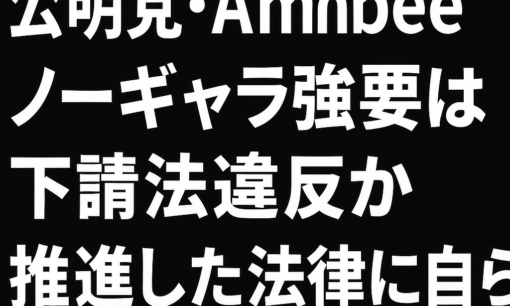DALL-Eで作成
発達障害の診断を受ける人が目に見えて増えた――。だが、それは“有病率の急増”なのか、“見つかる人の増加”なのか。文部科学省の「通級による指導」統計では、公立小学校のADHD対象児童が2019年度2万0616人から2023年度3万5007人へと4年で1万4391人増えた。背景には、診断基準の更新、社会的認知の広がり、受診・支援ルートの整備といった要因が重なる。東洋経済オンラインが取材した本田秀夫・信州大学教授の見立ても「診断される人の増加」が主因という点で一致する。
数字でみる推移――「通級」におけるADHDの増加
公立小学校で通級による指導を受ける注意欠如多動症(ADHD)の児童は、2019年度(令和元年度)2万0616人、2023年度(令和5年度)3万5007人。この4年間で1万4391人増となった。いずれも文部科学省「通級による指導 実施状況調査」に基づく。なお、令和5年度値は3月31日時点の通年値であり、令和元年度値は5月1日時点という基準日の違いに留意が必要だ。
注:ここでの「増えた」は学校現場の通級利用状況(行政統計)の把握であり、医学的な有病率推定とは異なる。文科省は別途「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」を実施しているが、これは医師の診断に基づく有病率を示す調査ではない。
「増えた」のは何か――3つの要因
- 診断枠組みの拡張
DSM-5(2013)で自閉症は自閉スペクトラム症(ASD)として統合され、症状領域の整理や感覚過敏の明記が進んだ。ICD-11でもASDの定義が整理され、実務上の識別が広がった。枠組みの変化は診断の間口を広げ、見つかる人を増やした。 - 社会的認知の浸透とスクリーニングの普及
乳幼児健診や園・学校の気づき、保護者の相談行動が活発化。米CDCの監視データでも、スクリーニングと認定の広がりに伴う診断率の上昇が長期的に示されている。 - 医療アクセス・支援制度の整備
わが国では合理的配慮の提供が2024年4月から事業者に義務化され、教育・就労の場で環境調整が標準化。受診・相談ルートの整備は「把握される人」の増加にもつながる。
成人での診断増――「子どもの問題」から「ライフスパンの特性」へ
ADHDの症状は成人期まで持続する人が多く、年齢とともに多動・衝動は弱まりやすい一方、不注意は残りやすい。仕事や生活の要求水準が上がる成人期に支障として顕在化し、受診の契機になる。
支援の原則――「治す」ではなく環境調整と合理的配慮
発達障害は病気のように「完治」を目指す対象ではなく、特性に応じた環境調整・学習/就労上の配慮で生きづらさを減らすという発想が基本である。英国NHSもASDについて「疾患ではなく脳のはたらきの違いで、治療や“治癒”の対象ではない」と明確に説明する。日本では2024年4月から合理的配慮が義務化され、教育・就労現場での環境整備が制度面で後押しされた。
ことばの選び方――Person-first/Identity-first
当事者の選好を尊重し、**「自閉スペクトラム症のある人(person-first)」と「自閉スペクトラムの人(identity-first)」**を文脈に応じて使い分けるのが推奨される。APAの言語ガイドラインは、双方の用法を認め、当事者・コミュニティの希望に沿うことを求めている。
代表的な発達障害と特性・原因(要約表)
| 名称 | 主な症状 | 特徴 | 原因(現在の科学的理解) |
|---|---|---|---|
| 自閉スペクトラム症(ASD) | 社会的コミュニケーションの困難、こだわり・感覚過敏など | 能力プロファイルの凹凸が大きい。言語・知的能力の幅が広い | 神経発達の違いが基盤。遺伝要因が大きく、環境要因も限定的に関与。診断枠組みはDSM-5/DSM-5-TRで統合。 |
| 注意欠如多動症(ADHD) | 不注意、多動・衝動(成人では落ち着きのなさとして現れやすい) | 学習・就労・生活管理で困りやすいが、関心領域では強い集中も | 神経発達の違い。成人まで持続することが多い。 |
| 学習障害(LD/限局性学習症) | 読み・書き・計算など特定領域の困難 | 知的能力は保たれることが多く、代替手段で学習可能 | 神経発達の違い。DSM-5で診断概念が再整理。 |
| 発達性協調運動症(DCD) | 不器用さ、運動計画の困難 | 体育・日常動作でつまずきやすい | 神経発達の違い(運動制御ネットワーク)。 |
| 発達性言語症(DLD) | 表出・理解の言語発達の遅れ | 学習・対人に波及しうる | 神経発達の違い。個別の言語支援が有効。 |
注:**ワクチン等がASDの原因という科学的根拠はない。**CDCはMMRやチメロサールとASDの関連を否定する複数研究を整理している。
まとめ――「増えた」のではなく「見える化」が進んだ
行政統計が示すのは、学校現場で支援ニーズとして把握される子どもが着実に増えているという事実だ。背景には、診断基準の更新、社会の理解の深まり、受診・相談ルートの整備がある。社会はすでに「平均」に合わせる教育・就労から、個別の特性に合わせる合理的配慮へ軸足を移しつつあり、これは当事者のQOL向上だけでなく、学級や組織の学習・生産性にも資する変化である。