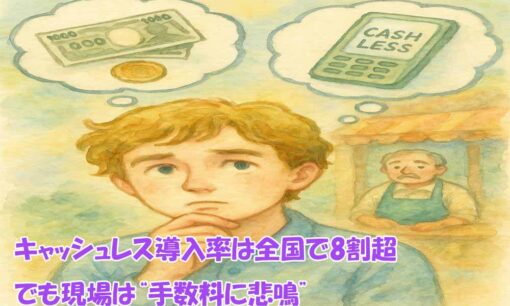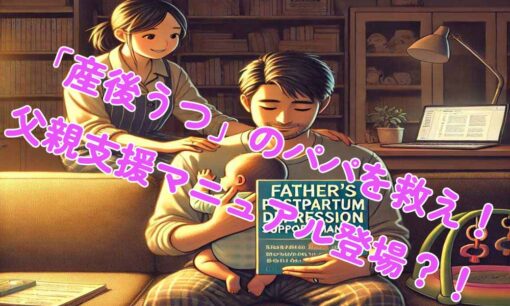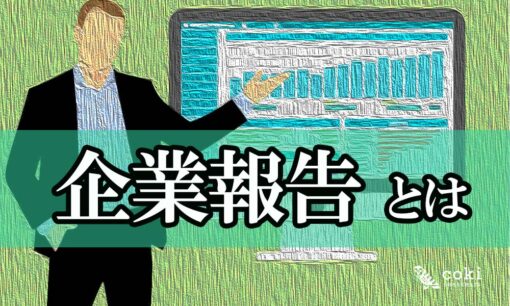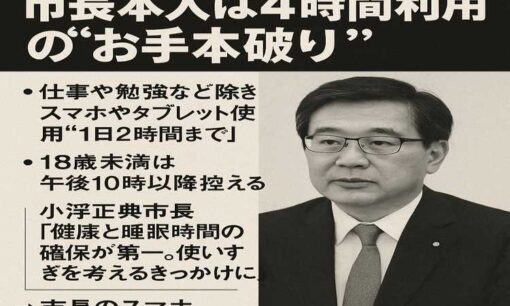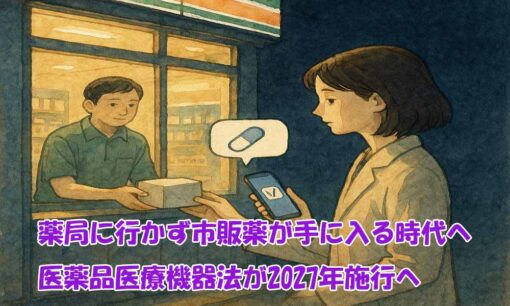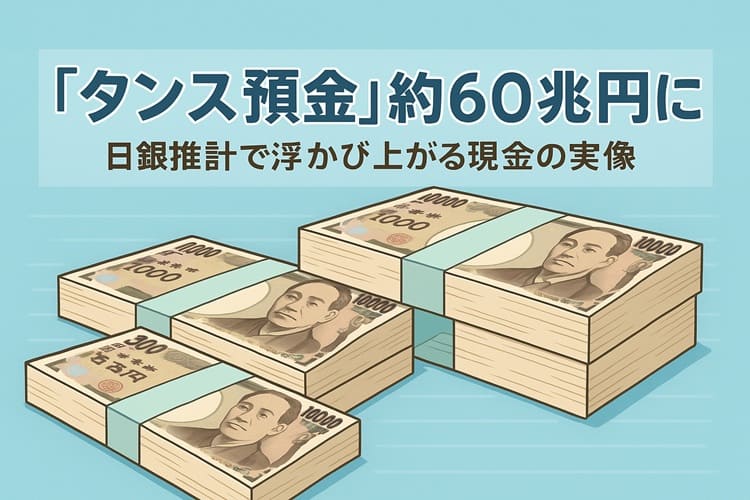
家のタンスや金庫にしまわれ、銀行や証券口座に預けられていない現金。いわゆる「タンス預金」が、日本全国でおよそ60兆円規模にのぼる可能性があると、日本銀行(日銀)の分析で分かった。これは日本の経済規模を示すGDPの約2割に相当する大きな金額で、まさに「眠っているお金」といえる。
なぜそんなに多いのか
日銀は新紙幣発行のタイミングに合わせ、流通するお札の動きを分析した。特に注目したのは「1000円札」と「1万円札」の発行枚数の違い。
日常の買い物でよく使う1000円札に比べて、貯め込む目的で保有されやすい1万円札の増加率が、1990年代後半以降大きく伸びていることが分かった。つまり、お金が流通せず、家庭にしまわれている可能性が高いということだ。
さらに、GDPに対するお札全体の発行残高の比率を調べると、90年代半ばから上昇傾向にあり、通常より多くの現金が「取引に使われていない」と推定された。
専門家はこう見る
経済学者は「低金利が続き、銀行に預けてもほとんど利息がつかないため、現金を手元で持つ人が増えた」と指摘する。また「金融危機や銀行破綻を経験した世代は、銀行への不信感が根強く、現金を安心のよりどころにしている」との声もある。
別の専門家は「個人にとっては安全でも、経済全体から見るとお金が動かず、消費や投資につながらない。成長を妨げかねない」と懸念する。
庶民の声
実際に生活者からはさまざまな声が聞かれる。
「利息がつかないなら、やっぱり手元に置いておきたい」(70代女性)
「防犯を考えると現金を家に置くのは不安。老後資金は投資に回している」(40代男性)
世代や生活環境によって、現金への向き合い方は大きく異なっている。
世界と比べると?
日本は現金への依存度が特に高い国だ。アメリカではGDP比で約8%、ヨーロッパでも同程度だが、日本は20%近くに達している。これは「現金を資産保全の手段と考える文化」と「過去の金融不安による経験」が背景にある。
過去の出来事が後押し
タンス預金は時代の出来事とも結びついている。
- 新札切替時には「古いお札が使えなくなるのでは」と不安が広がった。
- 東日本大震災では停電の影響で現金の重要性を再確認する人が多かった。
- 金融危機では「銀行が危ないのでは」と思い、現金を引き出す動きが目立った。
こうした経験が「やっぱり現金が一番安心」という意識を強めている。
政府と日銀の取り組み
政府や日銀も手をこまねいてはいない。
- キャッシュレス決済の普及:QRコードやマイナポイントで便利さを広める。
- 金融教育の強化:学校や地域で資産形成を学ぶ機会を増やす。
- 高齢者への支援:誰でも使いやすいキャッシュレスの仕組みづくり。
日銀関係者は「タンス預金自体が悪いわけではないが、経済の血流を滞らせてしまう。どうやってお金を動かすかが課題だ」と話している。
今後の行方
日本人にとって現金は「安心の象徴」であり続けている。しかし60兆円ものお金が動かずに眠っている現状は、経済にとって大きな課題だ。今後、キャッシュレス社会の進展や金融教育の広がりが、この「タンス預金」をどう変えていくのか注目される。