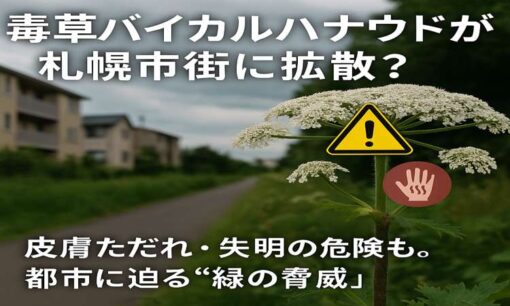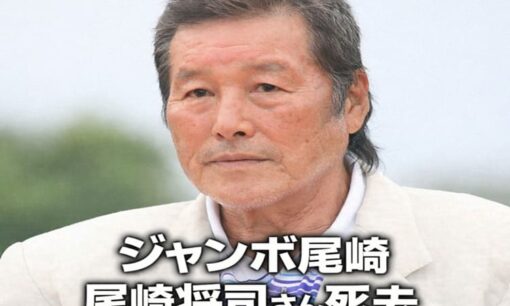2025年9月1日、全国で「緊急銃猟制度」が施行される。市街地に出没したクマを銃で駆除できる画期的な仕組みだ。だが、制度開始を目前にして猟友会は会員に「発砲を断ってもよい」と通達した。人々の命を守る最後の砦が、なぜ銃口を向けることを拒むのか。その背後には、6年間に及ぶ裁判劇「砂川事件」が刻んだ深い爪痕と、行政と警察の責任の押し付け合い、そして世界との制度格差がある。
制度は画期的、だが現場は「撃てない」
環境省の新ガイドラインは、住宅地など生活圏に侵入したヒグマやツキノワグマを市町村の判断で銃猟可能とするものだ。危険鳥獣が出没し、緊急性が高く、銃以外に捕獲手段がなく、住民に流れ弾の恐れがない場合に限られる。
背景には深刻な被害がある。2023年度、クマによる人身被害は219人に達し、死者は6人。2016年度と比べて約3倍に増加した。かつて「秋の一時的な出没」とされたパターンは崩れ、いまや通年の脅威になりつつある。
だが最前線の猟友会員は「もう撃てない」と口をそろえる。札幌近郊で活動する60代の会員は記者にこう漏らした。
「撃てば町を守れる。でも、もし後で警察に『危険な発砲だ』と責められたら、生活も名誉も失う。自分や家族を守るために引き金を引けないんですよ」
砂川事件が生んだ“発砲恐怖症”
猟友会を萎縮させたのは「砂川事件」だ。2018年8月、北海道砂川市で子グマが出没。市職員と現場警察官の要請を受け、当時70歳の支部長・池上治男氏は安全を確認のうえ1発で仕留めた。狩猟歴30年のベテランによる的確な対応だった。
だが2か月後、警察は「弾の先に建物があった」として鳥獣保護法違反・銃刀法違反で書類送検。現場には8メートルの土手があり建物は視認できなかったが、警察は地図上の平面的な位置関係のみで危険と断じた。
検察は不起訴、北海道も免許を剥奪せず、市も駆除員に任命を続けた。だが公安委員会は銃所持許可を取り消し、池上氏は裁判に訴えた。2021年に札幌地裁で「著しく妥当性を欠き違法」と勝訴するも、2024年の高裁で逆転敗訴。結局6年間、銃を奪われ裁かれ続けることになった。
「正義感で町を守った人間が、法廷で人生を削られる。これじゃ、誰も撃ちたくない」——北海道内の現役ハンターは事件をそう振り返る。
行政と警察の「責任の押し付け合い」
砂川事件の核心は、銃を撃つ判断の責任が「誰にあるのか」が曖昧な点にある。市は「地域住民の不安」を理由に発砲を要請し、現場の警察官も同意。しかし、後になって警察本部が「危険な発砲だった」と方針を翻した。
つまり、駆除の現場では行政も警察も判断をハンターに委ね、後から「自己責任」と突き放す構図が生まれている。専門家は指摘する。
「自治体は政治的リスクを避け、警察は法的責任を回避する。結局すべての矢面に立たされるのは猟友会員です」
この責任の空白地帯こそ、猟友会が“発砲拒否”を選ぶ最大の理由なのだ。
報酬とリスクのアンバランス
猟友会員に支払われる駆除報酬は決して高くない。地方都市では1頭あたり数万円にとどまる例もある。それに対して背負うリスクは計り知れない。万一流れ弾で事故が起これば刑事責任はハンター個人。さらに砂川事件のように裁判に持ち込まれれば、長期間にわたり法廷闘争を強いられる。
「命を懸けて駆除に行っても、報酬はガソリン代程度。割に合わない」
現場の声は切実だ。その結果、狩猟免許を持つ人の7割が実働していない「ペーパーハンター」化し、猟友会加入率も低下。地域社会の“最後の防波堤”が崩壊の危機にある。
世界はどう対応しているか
日本だけが迷走しているわけではない。イタリアではローマ市内にイノシシが群れで出没し、2023年に都市部での狩猟を認める法律が成立した。そこでは狩猟が「公的任務」と位置づけられ、責任は自治体が負担する仕組みになっている。
北米では「ベアパトロール」と呼ばれる専門チームが存在し、報酬は公務員並みに保障される。日本のように「民間ボランティア頼み」の制度は先進国の中でも異質だ。
「国際比較をすれば、日本のハンターは自己責任を押し付けられたまま命を懸けている。制度の持続性を考えれば、抜本的な改革が必要です」——野生動物管理を研究する大学教授は警鐘を鳴らす。
制度を生かすのは「責任の明確化」
緊急銃猟制度は、表面上は画期的に見える。だが、その実効性は「撃てば処罰される」という恐怖に覆われている。砂川事件は、行政と警察の責任の押し付け合いがハンターを孤立させた象徴だ。
クマ問題は今後も拡大するだろう。だが、現場の人間が安心して引き金を引ける環境を整えない限り、この制度は絵に描いた餅に終わる。責任の明確化と報酬体系の抜本改革、それこそが制度を「実効あるもの」に変える唯一の道である。