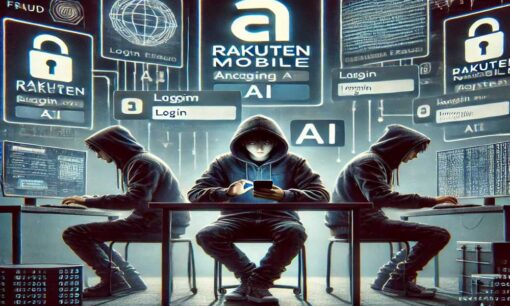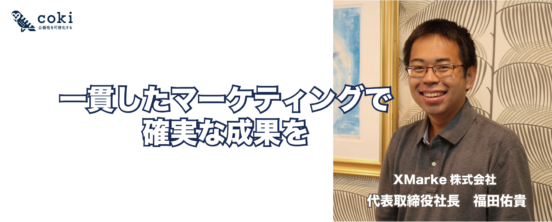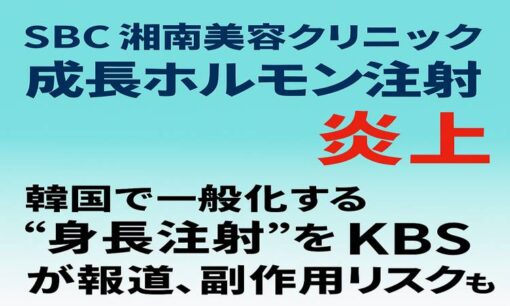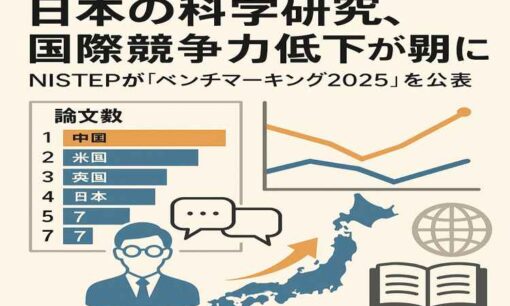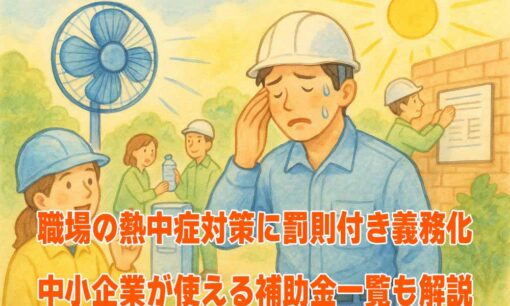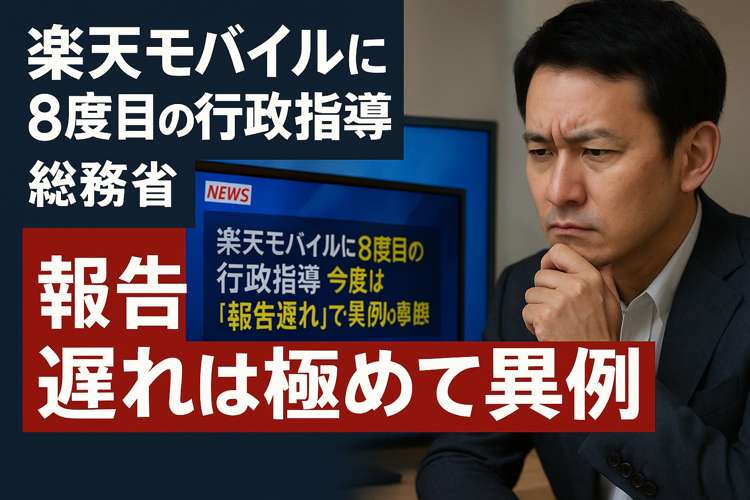
通信業界に再び激震が走った。楽天モバイルが総務省から8度目となる行政指導を受けた。今回の理由は、7000回線超に及ぶ大規模情報漏洩を認知しながら、法で義務付けられた期限を大幅に超えて報告を行ったためである。総務省は「報告遅れを理由とした行政指導は極めて異例」と強調した。
7000回線超の情報漏洩と3か月遅れの報告
総務省によると、楽天モバイルは2025年2月27日までに不正アクセス事案を認識していた。しかし、報告は6月17日まで行われず、3か月以上の遅延となった。電気通信事業法は「通信の秘密」が漏洩した場合、30日以内の報告を義務付けており、これを逸脱したことが今回の指導につながった。
事案の発端は、生成AIを悪用したプログラムで不正アクセスを繰り返した中高生3人の逮捕だった。総務省の発表では、被害は7002回線(4609人分)に及び、通話やSMSの履歴が閲覧可能な状態となった。さらに不正契約は370件に上った。
被害者が直面する理不尽な請求
一部のユーザーには、さらに理不尽な事態が降りかかっている。ある被害者は楽天モバイルアプリで身に覚えのない番号を発見し、契約は取り消されたが、楽天カードには既に請求が発生していた。確認を依頼したものの「正当な請求」と扱われ、結局は不正契約分の料金を支払わされる結果となった。このユーザーは「被害者であるにもかかわらず料金を負担させられるのは納得できない」と憤る。
SNS上でも「楽天モバイルはもう2度と契約しない」「楽天のサービスはセキュリティ面で不安が大きい」といった批判が相次いでいる。
総務省による厳格な監視体制
今回の行政指導を受け、総務省は楽天モバイルに対し、2025年10月末までにコンプライアンス改善策を報告し、2026年1月末までに再発防止策の実施状況を提出するよう命じた。さらに、その後1年間は3か月ごとの定期報告を義務付ける異例の監視体制を敷く。総務省は「同様の事案を繰り返してきた経緯を踏まえ、徹底的な改善を求める」としている。
矢沢俊介社長は「ご指摘を厳粛に受け止め、早急に体制を見直す」とコメントした。しかし専門家の間では「単発的な対応ではなく、企業体質そのものの改善が不可欠」との声が強い。
8度目の行政指導が突きつけるもの
楽天モバイルはこれまでにも、基地局整備の遅れ、通信障害、端末割引違反、情報漏洩などで行政指導を受けてきた。今回で8度目となり、事業者としての信頼性が改めて問われている。
通信の秘密を守ることは電気通信事業者の根幹的な責務である。報告遅れという「極めて異例」の指導は、単なる手続き不備ではなく、危機管理意識の欠如を示すものにほかならない。ユーザーにとっても、契約先の通信事業者を見極める上での大きな警鐘となった。