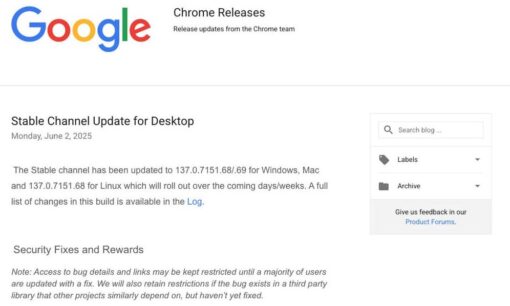2025年8月、日本国内で初めて「日本円と1対1で連動するステーブルコイン」の発行が認められた。フィンテック企業JPYCが金融庁に資金移動業者として登録されたことで、日本円建てのステーブルコイン「JPYC」が誕生する。暗号資産に不安を感じていた人にとっても、安定性を重視したステーブルコインは関心を集める存在だ。本記事では、ステーブルコインの基本から日本円建てコインの意義、今後の展望までをわかりやすく解説する。
日本初の円建てステーブルコイン発行へ
2025年8月18日、JPYC株式会社(本社・東京、代表取締役社長・岡部典孝)が金融庁から資金移動業者として正式に登録された(登録番号 関東財務局長 第00099号)。これにより、国内で初めて日本円と1対1で連動する「円建てステーブルコイン」の発行が可能となった。
金融庁は2023年6月に施行された改正資金決済法に基づき、銀行、信託会社、そして登録を受けた資金移動業者に限り、法定通貨に裏付けられた電子決済手段(ステーブルコイン)の発行を認めている。JPYCはその第一号となり、円建てステーブルコイン「JPYC」を今秋にも発行するとしている。
同社によると、裏付け資産は日本円の預貯金や国債とし、利用者は「1JPYC=1円」で円に償還できる。発行はイーサリアム、Avalanche、Polygonの3つのブロックチェーンで開始予定だ。
ステーブルコインとは何か
ステーブルコインとは、価格変動が大きいビットコインやイーサリアムなどとは異なり、法定通貨や資産と連動させることで「価値を安定させた暗号資産」の総称である。
米ドルに連動する「テザー(USDT)」や「USDコイン(USDC)」が代表例であり、仮想通貨市場の中でも取引量・時価総額ともに上位に位置している。米調査サイト「CoinMarketCap」によると、2025年8月現在、仮想通貨時価総額ランキングのトップ10に2種類のステーブルコインが含まれている。
価格が安定していることから、日常の決済や国際送金、ブロックチェーン上のサービス利用に適しており、「実用的な仮想通貨」として注目を集めている。
ステーブルコインの種類と仕組み
ステーブルコインはその裏付けとなる仕組みに応じて大きく3つに分類される。
- 法定通貨担保型
米ドルや円などの法定通貨を準備金として保有し、その分だけコインを発行する仕組み。USDTやUSDC、そして今回の「JPYC」が該当する。信頼性が高く、流動性が大きい。 - 暗号資産担保型
ビットコインやイーサリアムといった暗号資産を担保として発行される。代表例は「DAI」。価格変動リスクが大きいため、担保を過剰に用意する仕組みで安定性を担保する。 - アルゴリズム型(無担保型)
市場の需給に応じて自動的に供給量を調整し、価格を安定させる仕組み。Terraform Labsが発行していた「テラUSD(UST)」が知られるが、2022年に米ドルとの連動が外れ、暴落して市場に大きな混乱をもたらした。
これらの仕組みの中でも、日本で法的に認められているのは「法定通貨担保型」のみであり、安全性と透明性が重視されている。
なぜ円建てステーブルコインが重要なのか
これまで日本国内では、米ドルに連動したUSDCなどの利用は可能だったが、円建てのステーブルコインは存在しなかった。
そのため、ブロックチェーン上での取引や国際送金を行う際に、一度ドル建てコインを経由する必要があり、為替リスクや手数料が課題となっていた。
円建てステーブルコインが登場すれば、個人による海外送金や法人の国際決済が円ベースで可能になり、コスト削減や利便性向上が期待される。また、分散型金融(DeFi)サービスでの活用も見込まれ、日本人ユーザーにとって使いやすい環境が整うことになる。
海外のステーブルコイン規制と市場拡大
ステーブルコインは世界的にも急速に市場を拡大している。米国では2025年7月、連邦議会で「GENIUS法案」が可決され、ドル建てステーブルコインの規制枠組みが整備された。発行元に対し、裏付け資産の義務化や年次監査を求め、安全性と透明性を強化している。
また、EUでは2022年に「MiCA(暗号資産市場規制)」が可決され、ステーブルコイン発行者に対して保有者がいつでも資産と交換可能な体制を義務付けている。
米国の市場規模は2025年時点で2,500億ドル(約37兆円)を超えており(CoinMarketCap調べ)、金融インフラの一部として機能し始めている。
ステーブルコインのメリット
- 価格安定性
仮想通貨特有の価格変動が少なく、決済手段として利用しやすい。 - 国際送金の効率化
銀行を介さずに24時間365日、低コストで即時送金が可能。 - ブロックチェーン経済との親和性
NFT取引やWeb3サービス、DeFiなど、ブロックチェーンを基盤にしたサービスで使いやすい。
ステーブルコインのリスクと課題
一方で、課題もある。
- 日本国内では外国発行コインの取引に制限があり、1回100万円までの送金上限が設けられている
- 発行体の信頼性や担保資産の透明性が不十分であれば、信用不安に直結する。
- テラUSDの事例に見られるように、アルゴリズム型ではシステム崩壊のリスクがある。
日本での今後の展望
円建てステーブルコインの登場は、日本のデジタル経済にとって重要な転機となる。
JPYCの岡部社長は「国内外における日本円建てステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金を実現する」とコメントしている。今後は銀行や決済事業者との連携が進み、国際送金、法人間取引、個人決済など利用の幅が広がる見通しだ。
さらに、2025年には三菱UFJ信託銀行も円建てステーブルコインの発行を計画しており、競争と普及が加速するとみられている。
まとめ
ステーブルコインは「安定した価値を持つ仮想通貨」として、従来のビットコインなどと異なり日常的な利用に適した存在だ。
今回の日本円建てステーブルコイン「JPYC」の発行は、国内金融における大きな一歩であり、国際送金や電子決済のあり方を変える可能性がある。世界ではすでにドル建てコインが普及しており、日本でも円建てコインが加わることで、デジタル通貨時代の幕開けが現実味を帯びてきた。
今後の法整備や発行体の信頼性確保を前提に、ステーブルコインは私たちの生活に欠かせない存在へと成長していくだろう。