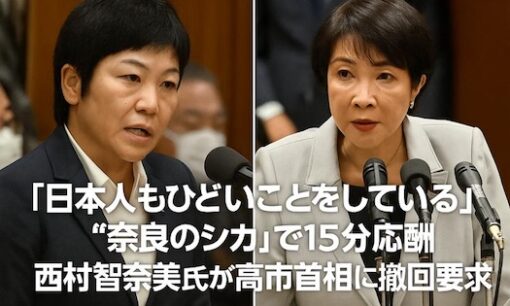北海道・知床半島の羅臼岳で2025年8月14日午前、登山中の20代男性がヒグマに襲われ安否不明となった。警察は安全確保のため14日の地上捜索を中断し、翌15日早朝に再開。現場付近では男性のものとみられる財布とスプレー缶が発見された。
本件は、一般的なクマ被害とはいくつかの重要な点で異なる。報道発表・専門家コメントをもとに整理する。
ヒグマ高密度生息域での発生
羅臼岳を含む知床半島は、日本でも有数のヒグマ高密度生息地であり、世界自然遺産に登録された豊かな生態系が広がっている。河川や渓流、海岸線、山岳地帯といった多様な環境が連続しており、ヒグマが餌場を求めて広範囲に行動することが可能だ。
本州や九州で発生するツキノワグマによる被害では、人里や登山道に出現するクマは通常、人の存在を察知すると回避行動を取ることが多い。これに対し知床のヒグマは、人間の活動域と重なる場所に日常的に出没し、「クマの生活圏内に人が入る」構造が前提となっている。この地理的背景が、偶発的な遭遇ではなく、恒常的な接触リスクを生む要因となっている。
「人を恐れない」個体の存在
知床財団や地元関係者の記録によれば、2025年7月以降、羅臼岳周辺では人を避けないヒグマが複数回目撃されていた。12日朝には、登山者が長時間付きまとわれる事案も報告されている。
通常の野生ヒグマは警戒心が強く、人の気配や音を察知すると距離を取る。しかし今回問題となっている個体は、熊よけスプレーを使用されてもなお追跡行動を取るケースがあったとされる。北海道ヒグマ対策室も「複数回の接近行動は通常の野生個体とは異なる」と警告している。人慣れや条件づけによって警戒心が薄れた個体は、危険度が格段に高まる。
予兆が複数回確認されていた
今回の事故現場は、直近で複数回の危険行動が目撃された場所である。一般的なクマ被害の多くは、農作業中や単独登山中などに突発的な遭遇で発生することが多いが、今回は明確な予兆情報が存在していた点が異なる。
過去にも北海道では、特定の個体が同一地域で繰り返し接近・接触行動を行った結果、人身被害につながった事例がある。知床のヒグマは餌条件や観光客の行動によって行動パターンが変化しやすく、予兆があった段階で入山規制や駆除検討などの初動対応が課題となる。
捕食行動に近い襲撃形態
警察の説明によると、被害男性は太もも付近から大量出血し、登山道脇の茂みに引きずり込まれている。これは威嚇や防衛的攻撃にとどまらず、獲物として捕らえた可能性を示唆する行動だ。
知床でヒグマ対策に17年間取り組む「野生動物被害対策クリニック北海道」代表・石名坂豪氏は、「人そのものを襲うヒグマであれば大変な事態」とし、従来の遭遇回避策に加えて、遭遇後の自己防衛手段の重要性を強調している。
過去の事例でも、捕食行動に移ったヒグマは再び人間を襲う傾向があり、特定個体の早急な特定と排除が不可欠とされる。
登山道という観光利用エリアでの発生
多くのクマ被害は農地や集落周辺で発生するが、今回は観光客や登山者が利用する登山道で起きた。羅臼岳は「日本百名山」に数えられ、知床五湖やカムイワッカ湯の滝と並ぶ人気スポットだ。
今回の襲撃を受け、周辺の主要観光地は閉鎖され、観光客や地元住民に影響が広がっている。道は「正確な出没情報を事前に確認し、出没が相次ぐ場所は避けること」を呼びかけ、ヒグマ注意報を発出している。
このように、観光利用を前提としたエリアでの人身被害は、地域経済や観光安全政策にも直結する。
専門家・行政の注意喚起(北海道ヒグマ対策室)
- 複数人で会話しながら行動する
- 鈴や笛などで存在を知らせる
- ヒグマよけスプレーを常時携帯
- 出没が相次ぐエリアは入山を避ける
- 登山前に最新の出没情報を確認する