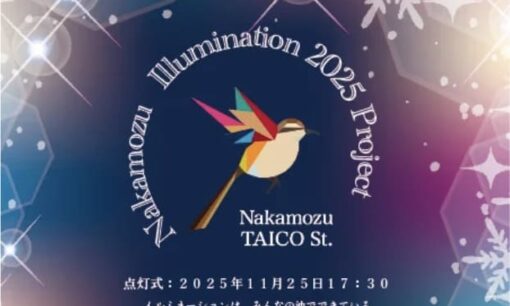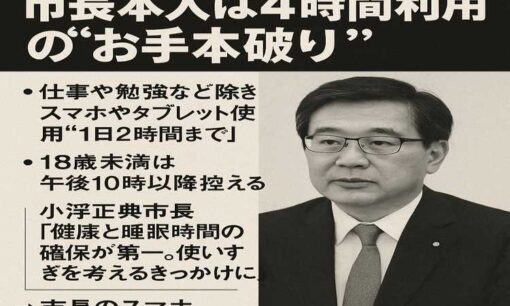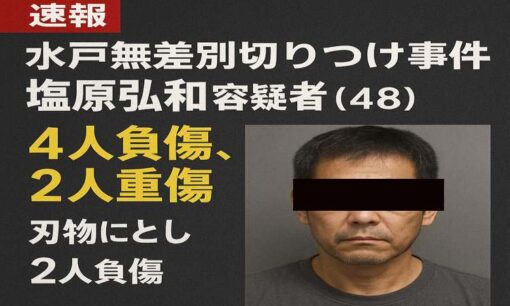2024年度のふるさと納税による寄付総額は、初めて1.2兆円を超えた。制度開始以来、利用者も寄付額も右肩上がりを続けているが、その内訳を見つめ直すと、単なる「お得な買い物」としての側面が強まっている現実も浮かび上がる。
利用者・寄付総額ともに過去最高
総務省の発表によると、2024年度のふるさと納税による寄付総額は1兆2727億円となり、5年連続で過去最高を更新した。利用者数も1079万人と過去最多を記録し、もはや「特別な制度」ではなく、広く浸透した税制度のひとつとして定着したことがうかがえる。
政府も制度の拡大を歓迎する姿勢を示しており、林官房長官は「お世話になった自治体に感謝や応援の気持ちを伝えることができる制度」としてその意義を強調した。
見えにくい「経費」の中身
だが、寄付額の急増と比例するように、制度の「透明性」や「効果」に対する懸念の声も高まっている。今回、初めて自治体がふるさと納税にかけた募集費用が調査され、その総額は5901億円に上ることが明らかになった。
特に注目されるのは、うち28%にあたる1656億円がポータルサイト運営事業者への手数料だった点だ。つまり、寄付額の約8分の1が民間プラットフォーマーに支払われている構図となる。
加えて、返礼品の調達、発送、PRなどに伴う事務費も各自治体にのしかかっている。こうした費用が地域の持続的な財政支援につながっているのか。その効果は依然として見えにくい。
「返礼品なし」の寄付が示す制度本来の姿
今回、最も多くの寄付を集めた自治体は兵庫県宝塚市だった。その大半を占めたのは、地元在住の夫婦が老朽化した病院の建て替えのために行った254億円の寄付であり、返礼品も仲介業者も介さない、本来のふるさと納税の形だった。
この事例は、制度本来の目的、地域を自発的に支援し、住民税の控除を受けながら自治体の未来をともに考えるという精神を体現している。こうした寄付がもっと評価されるべきではないか。
地域に本当に「残る」お金は?
上位の自治体には北海道白糠町や大阪・泉佐野市など、海産物や肉類などの高付加価値な返礼品で知られる地域が並ぶ。寄付を集める手段として返礼品の競争が激化する一方で、純粋な税収として自治体に残る資金がどれほどあるのかは不透明なままだ。
一方、返礼品を提供する企業や農家にとっては新たな販路となり、地域経済の活性化につながるという見方もある。しかし、それは納税制度としての副次効果であって、主目的が「買い物の延長線」であっては本末転倒ではないだろうか。
制度の持続性と信頼性を保つために
年々認知度を高め、活用者を増やしているふるさと納税。だからこそ今、あらためて制度の「意味」と「持続可能性」が問われている。寄付者が何に共感し、どこに納税したいかを判断するためには、事務費・仲介費・地域経済への還元率など、費用の内訳と効果の「見える化」が不可欠だ。
政府や自治体は、制度の透明性を高める取り組みを急ぐとともに、「感謝」と「応援」の気持ちがしっかり地域に届く設計を再構築する必要がある。