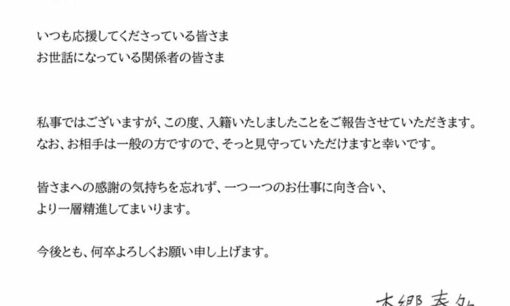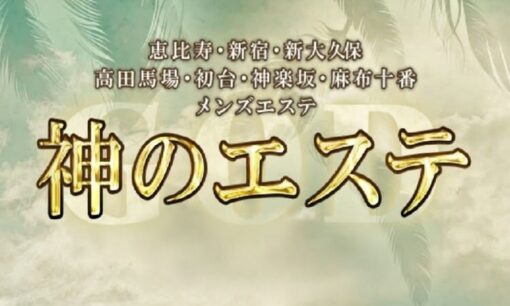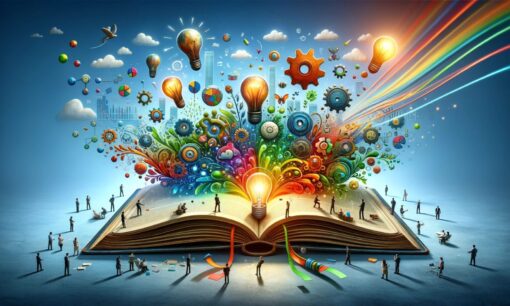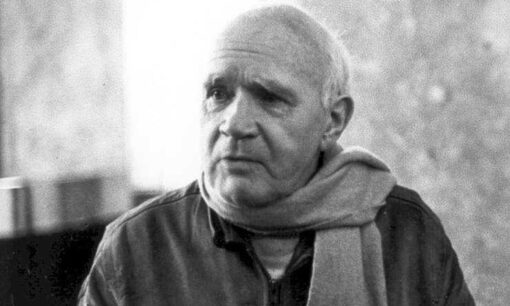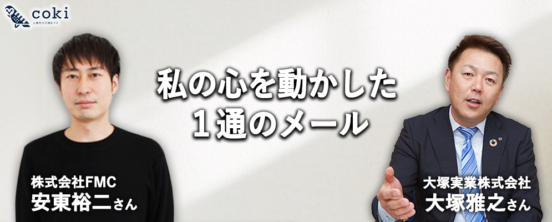2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻から、2年半が過ぎた。
戦火を逃れた人々は800万人を超え、今も多くが国外での避難生活を続けている。日本でも、これまでに約2,600人の避難民が暮らし始めた。
避難民という言葉に、私たちは“どこか遠い存在”のような印象を抱きがちだ。だが実際には、私たちのすぐ近くで、新しい暮らしを始めようとしている人がいる。
戦争から逃れてきた人たちにとって、本当の試練は、「避難」のその先にある。
支援は“6か月間”、でも避難生活は年単位
日本政府は、ウクライナからの避難民に特定活動の在留資格を認め、医療・教育・就労の機会を提供してきた。生活費や住居の支援も行われているが、これらの制度は原則6か月間で打ち切られる。
その後は、自力での生活、つまり就労による「自立」が求められる。しかし、日本語が話せなければ、仕事を見つけるのも難しく、そもそも文化や制度の違いが大きな壁になる。
小さな子どもを抱える母親、高齢の避難民、単身者など、状況によっては就労そのものが現実的でないケースも多い。
では、6か月を超えた今、彼らはどうしているのか。
答えは、多くの場合、地域や民間の支援に頼りながら、なんとか生活をつないでいるというのが実情だ。
NPOが運営する食料支援や、日本財団などによる生活再建支援、地域ボランティアによる通訳や学習支援──その恩恵がなければ、暮らしが成り立たない避難民も少なくない。
「帰る」も「残る」も、まだ選べない
戦争が長期化するなかで、避難民たちは「このまま日本に住み続けるか、それとも帰国するか」という選択に直面している。
だが現実には、容易に選べるわけではない。ウクライナの情勢は不安定なままで、故郷には簡単に戻れない。一方、日本で定住するには在留資格、語学、雇用、教育……いくつもの条件を乗り越える必要がある。
未来の見通しが立たないなかで、「まず目の前の暮らしをどうにかするしかない」というのが、多くの避難民の率直な声なのだ。
私たちにできること──「遠くの誰か」ではないと知ることから
私たちにできることの第一歩は、「彼らはもう、どこか遠くの人ではない」と知ることかもしれない。
避難民という言葉に、私たちはつい“遠くの国の話”を重ねてしまいがちだ。だが現実には、同じ電車に乗り、同じスーパーで買い物をし、同じ街の保育園や学校に子どもを通わせている人たちがいる。
自分たちの暮らす場所に、すでに彼らが「ともに生きている」という事実を知ること。
それは支援というより、関心と尊重のまなざしを持つことだ。
「気づかないまま通り過ぎる社会」から、「ともに暮らす社会」へと、空気を少しずつ変えていきたい。
それこそが、いま私たちにできる、もっとも現実的で、確かな支援なのだろう。
その声に、目を向け続けられるか
支援の期限が切れたとき、本当の暮らしが始まる。
帰る場所をまだ持てないまま、不確かな未来と向き合っている人がいる。私たちの暮らしと地続きの場所で、静かに日常を取り戻そうとしているその声に、目を向け続けられるか。
支援とは、大きなことではなく、その関心を持ち続けるという選択なのだ。