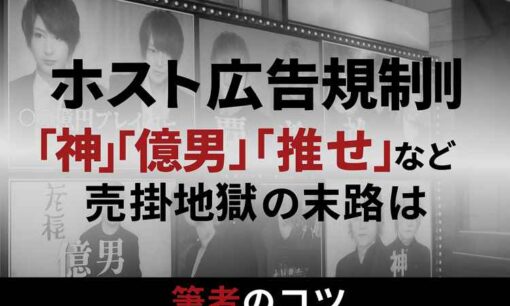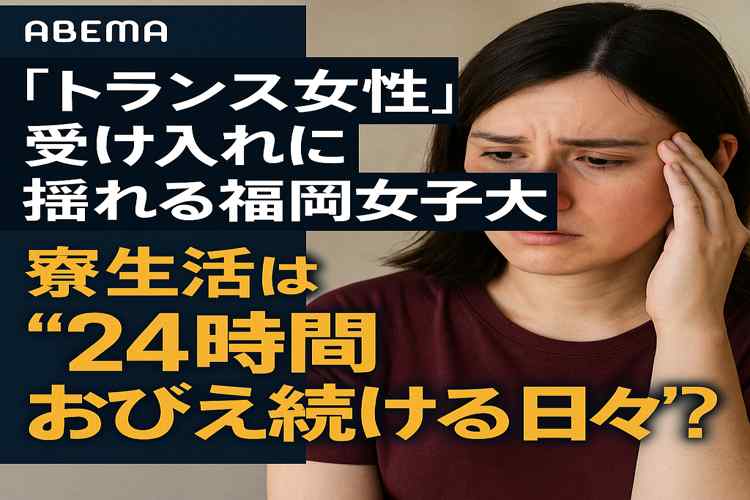
福岡女子大学が2029年度入学から、性自認が女性であるトランスジェンダーの学生を受け入れる方針を公表し、全国的な議論を呼んでいる。特に全寮制という同大学の特徴が、当事者の不安や社会的反発を浮き彫りにしている。
「志あるすべての女性に学びの扉を」…だが現実とのギャップ
福岡女子大学は2022年5月から検討を開始し、学生や保護者の意見を聞きながら受け入れの方針をまとめた。2026年秋には、出願資格や審査手続きの詳細を示す予定としている。同大学は「志あるすべての女性に本学固有の学びへの扉を等しく開いていくことは使命」として、今回の決断に至った。
しかしネット上では、「性自認の確認は不可能」「事実上の共学化では」「行き過ぎた多様性だ」といった批判の声も噴出。背景には、同大学が1年次全寮制を採用していることがある。トイレや更衣室、入浴施設の共用という極めてプライベートな空間で、肉体的性別の違いが無視できない現実が存在する。
当事者の声「24時間おびえて暮らす可能性」
番組『ABEMA Prime』に出演したトランスジェンダー女性のかえでさん(仮名)は、共学の大学に通いながらも「スッピンで男性に見える」「ヒゲが生える」など、見た目とのギャップに日々悩まされていることを番組で語っている。
「大学にいる時間が数時間ならまだしも、全寮制になると24時間ずっと自分を隠して過ごすことになり、精神的に非常にしんどい。自分が“バレてはいけない存在”であるというプレッシャーの中では、到底安心して生活できない」と吐露した。
また、「受け入れる女子大、受け入れない女子大があってこその“多様性”ではないか」と語り、トランスジェンダーの全受容が“正義”とされる風潮に一石を投じた。
アレン様の苦言「多様性を盾に理想を押しつけるな」
タレントのアレン氏も番組に出演し、「多様性を盾に、現実的配慮を無視して突っ走るのは危険」と語る。「体格差がある“元男性”が女子寮に入ることへの不安は、差別ではなく自然な感情」として、トランス女性の入寮には慎重な姿勢を示した。
一方で、「LGBTQのパレードなどで“裸のような格好”をして主張することが、むしろ特別視を助長してしまっている」と指摘。「もっと静かに、自分らしく生きる方法を模索すべきだ」とも述べた。
かえでさんも、「ロリータ服を着て外に出たいけど、見られるのが怖い。いじめられた過去もあって、人の目が気になってしまう」と本音を吐露した。
海外の女子大も悩む「トランス受け入れ」の線引き
福岡女子大の方針をめぐる議論は、日本に限った問題ではない。たとえば米国のバーナード大学やマウント・ホリヨーク大学など、多くのリベラルアーツ系女子大学が近年「トランス女性の受け入れ」を進めている。
だがその多くは、「戸籍上も女性」「ホルモン治療を一定期間以上受けている」など、客観的な要件を設けているのが実情だ。なかには「トランス男性(出生時女性、性自認男性)は受け入れ対象外」としており、性自認の多様化が女子大という制度そのものの前提を揺さぶり始めている。
日本では戸籍変更には厳格な要件があるが、米国では「自己申告」のみで性別が変えられる州も存在し、各大学が対応に苦慮している。福岡女子大も、同様の混乱を避けるには、国際的な事例を踏まえたガイドラインの整備が不可欠だ。
揺れるフェミニズム “女性の権利”は誰のものか
さらに深刻なのは、「女性の権利」が誰のためのものかという根源的な問いだ。フェミニズム運動の内部では、「トランス女性も女性だ」とする包括派と、「女性空間の安全性が脅かされる」と主張する批判派(いわゆるTERF=Trans-Exclusionary Radical Feminists)の対立が顕在化している。
この対立は英作家J・K・ローリングの発言を契機に世界的議論となった。「女性の権利を守るために、肉体的性別に基づいた空間は必要だ」という意見と、「性自認こそがアイデンティティの核だ」という主張は、互いに正義を掲げてぶつかり合う。
女子大とは、そもそも「女性のための、女性による教育空間」であり、その安全性・快適性が前提としてあった。そこに肉体的特徴が男性のままのトランス女性が入ることで、かえって従来の女性が“声を上げづらくなる”状況が生まれる危険も指摘されている。
“多様性”の暴走が、逆に「普通の女性」を排除する構図
こうした議論が浮き彫りにしているのは、多様性の名のもとに「発言しづらい空気」が生まれているという現実だ。「不安を表明すれば差別主義者扱いされる」との声は、SNSでも後を絶たない。
ある保護者は「娘が寮で身体的に男性の学生と一緒に過ごすとなると、不安を感じるのは自然なこと。それを口にすることさえ許されないのは、ある意味で“思想的暴力”ではないか」と語った。
実際、トランス受け入れの女子大を避ける受験生が増えるなど、制度が一方的に変更されることで「普通の女子学生」が離れていくリスクもある。結果的に、“多様性を尊重する場”が、特定の声の大きい層だけの場となってしまうという皮肉な構造が生まれかねない。
大学という学びの場において、多様性と安心の両立がいかに困難か。今回の福岡女子大学の事例は、その現実と限界を社会に突きつけている。
SNSの声に見る社会の揺れ
SNSでは今回の方針について、賛否を超えた多様な視点が飛び交っている。多くは、理念の是非よりも、実務上の課題や安全面への懸念に集中しているのが特徴だ。
「トイレ・風呂・更衣室の問題は必ず出てくる。いくら“自認”が女でも、体が男なら、その空間に入ること自体が違う」
「そのうち“自称女”の男性が悪用して入り込む事件が起きる。本当にトランスの人を守りたいなら、そのリスクに備えるべき」
「女子寮に入れるなら、せめて別階にして、出入りの動線は共有スペースを必ず通るよう設計するなど、工夫が必要」
一方で、受け入れに理解を示す意見もある。
「多様性を語るなら“排除しない”という選択は支持したい。制度設計さえ丁寧にすれば問題は解決できる」
「生まれや親を選べないのと同じで、性別も選べない。でも今は“変えよう”と努力する人がいる。それを否定する社会ではなく、支える社会であってほしい」
また、現代の身体改変技術に驚く声も見られた。
「昔は性別も遺伝も“諦めるもの”だったけど、今は性別変更や身長伸ばし、顔改造などで他人になれる時代。ここまで来たら、社会制度の側も変わらざるを得ないのでは」
だが最も多かったのは、「性自認と身体の性は別問題であり、少なくとも共有空間では“身体性”を基準に考えてほしい」という意見だった。
「性自認が女性でも、病院や風呂など身体的配慮が必要な空間は“体の性”基準でいいと思う。それは差別ではない」