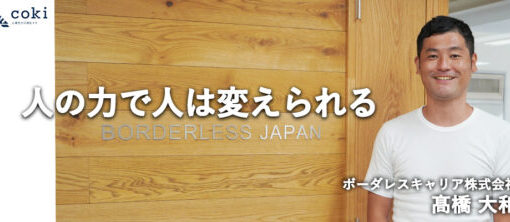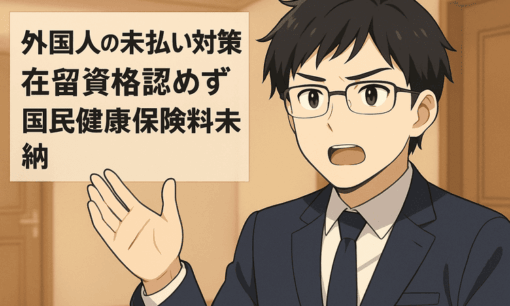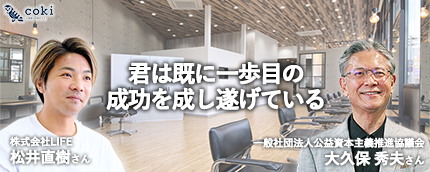福岡・博多といえば、全国的にまず思い浮かぶのは豚骨ラーメンだろう。ストレート細麺に白濁したスープ。ゴマと紅しょうが、からし高菜を添えて…。しかし、そんな“博多=ラーメン”という印象に反して、博多の地元民が日常的に食している麺類は、「うどん」なのである。しかも、そのうどんは讃岐のようなコシの強さとは真逆。驚くほどやわらかく、ふわりと喉を通り、忙しい日常に寄り添うような優しさをもつ。
そしてもうひとつ、あまり知られていない歴史的事実がある。博多こそが、日本におけるうどん文化発祥の地だというのだ。このコラムでは、ラーメンの影に隠れてきた「博多うどん」の真の姿とその背景にある歴史、文化、そして人々の暮らしとの結びつきを紐解いていく。
うどん文化の原点、承天寺と聖一国師
博多駅からほど近くにある臨済宗の古刹・承天寺。その境内には「饂飩蕎麦発祥之地」と刻まれた石碑が立つ。鎌倉時代中期、宋(現在の中国)から帰国した高僧・聖一国師(しょういちこくし/円爾)が、同寺の開祖としてこの地に根を下ろし、粉を水で挽く技術──いわゆる「水磨(すいま)」を博多にもたらした。この製粉技術により、うどん・そば、そして饅頭といった小麦粉を使った食品が広まり、博多は“粉もの文化”の源流となった。
この史実は、単なる伝説ではなく、文献や記録にも残されており、地元の小学生たちが社会科見学で訪れる定番スポットにもなっている。つまり博多は、単なるラーメンの街ではなく、「日本の麺文化の起点」なのだ。
なぜ、博多のうどんは“やわらかい”のか?
博多うどんの最大の特徴は、麺のやわらかさにある。コシを重視する讃岐うどんや稲庭うどんとは対照的に、博多のうどんは茹で置きされたものを再度温めて提供するスタイルが主流で、歯応えよりも「喉越しの優しさ」が重視されている。しかもそのおかげで麺にだしの旨さがしっかりと染み込んでいる。
この背景には、商人の街・博多の文化が関係している。多忙な商人たちにとって、食事は手早く済ませたいもの。注文から提供までのスピードを重視した結果、茹で置きという合理的な手法が広まり、結果として麺がやわらかくなった。だがそれは単なる妥協ではない。温かく、やさしい味わいは、忙しい博多っ子たちの胃と心を癒してきたのである。
ラーメンより、「うどん」が日常食
観光客の目には、博多ラーメンがこの街の象徴のように映るかもしれない。実際、駅周辺には有名ラーメン店が軒を連ね、深夜でも行列が絶えない。しかし地元民にとって、ラーメンは“ハレの食”に近い位置づけであり、日常的に親しまれているのは、断然うどんだ。
特に支持を集めているのが「丸天うどん」や「ごぼう天うどん」。魚のすり身を揚げた丸い天ぷらや、香ばしく揚がったごぼうの天ぷらを載せた一杯は、素朴でいてどこか懐かしい。朝食に一杯、昼にさっと、酒の締めにも。博多のうどんは、暮らしのリズムにすっと馴染んでいる。
さらに、うどんチェーン「ウエスト」や老舗「因幡うどん」など、地域に根ざした店舗が数多く存在し、各店が独自のだし、麺、トッピングでその土地のうどん文化を支えている。
黄金色のだしと、トッピングの妙
博多うどんのもうひとつの魅力は、スープ=だしにある。昆布や鰹、いりこ、トビウオ(アゴ)など、複数の魚介系素材を組み合わせて煮出した出汁は、黄金色に輝き、透き通っている。醤油は控えめで、口に含むとやさしい旨みが広がる。この上品なだしが、やわらかいうどんにしみこみ、絶妙なバランスを生む。
トッピングは自由自在。天かす、ネギ、わかめ、肉、そして先述の丸天やごぼう天など、選ぶ楽しみもまた大きな魅力である。なかには「うどんには必ずいなり寿司を添える」という人も少なくない。
再評価される“やわらか文化”
近年、全国のうどん愛好家や食文化研究者の間で、博多うどんの評価が高まりつつある。かつて「コシがない」として敬遠されがちだったやわらかな食感が、むしろ唯一無二の個性として注目されている。ラーメンで有名になった博多の食文化だが、その奥には、やわらかく包み込むようなうどんの存在があった。
テレビ番組やSNSでも「福岡に行ったらラーメンよりうどんを食べて」と勧める声が増えている。「ウエストの朝うどん」や、「因幡うどんのだしの香り」に魅せられて福岡を再訪するリピーターも多いという。
ラーメンだけでは語れない、博多の食文化
博多の食といえば、まずラーメンが想起される時代は、そろそろ見直されるべきなのかもしれない。発祥地・承天寺に刻まれた「うどん・そば発祥の地」の碑が語るように、博多は日本の粉食文化の原点である。そして、忙しない日常に寄り添ううどんこそ、地元の人々が本当に愛してきた味なのだ。
博多を訪れたなら、名店のラーメンを味わうのも一興だが、ぜひ一度は、ふわりとした麺に黄金のだしが染み込む一杯のうどんをすすってほしい。そこには、博多の暮らしと人情と、長い歴史が溶け込んでいる。