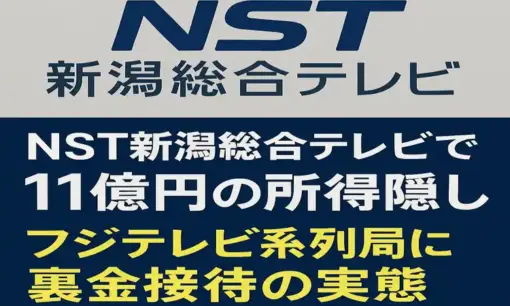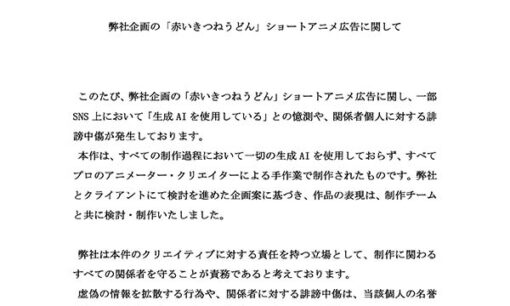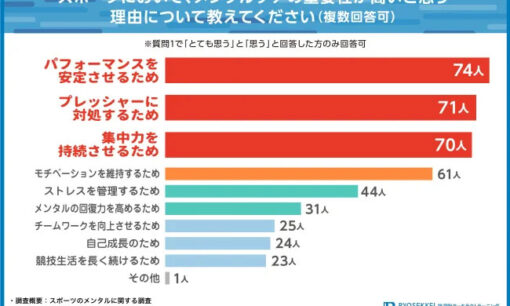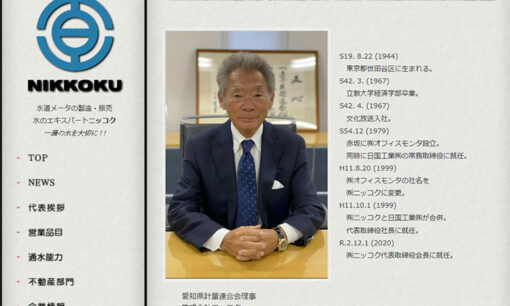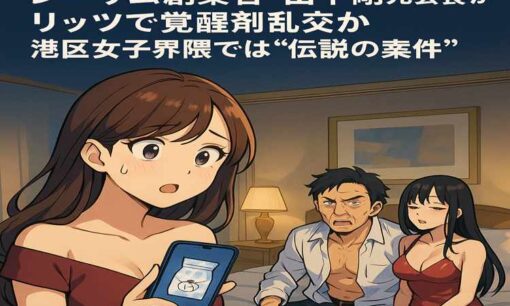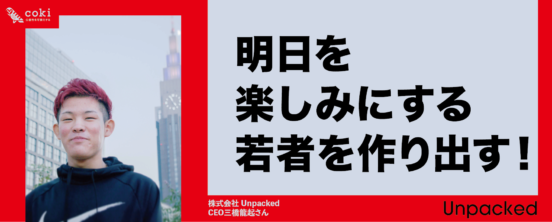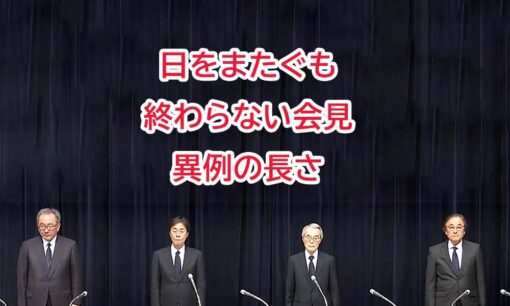2021年に開催された東京五輪・パラリンピックの運営業務をめぐる談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われたイベント企画会社「セレスポ」(東証スタンダード上場、東京都豊島区)とその元専務に対し、東京高裁は6月3日、控訴を棄却する判決を言い渡した。
1審・東京地裁による有罪判断を支持し、同社には罰金2億8000万円、元専務・鎌田義次被告(62)には懲役1年10月・執行猶予4年の判決が維持された。
高裁も「受注調整」の共謀認定
事件では、2018年2月から7月にかけて、大会組織委員会が発注した東京五輪の本大会運営業務やテストイベント計画立案業務をめぐって、セレスポと鎌田被告が元組織委次長(有罪確定)らと共謀し、あらかじめ受注業者を調整していたとされる。
1審の東京地裁判決では、こうした調整行為が公正な競争を阻害するものとして独禁法に違反すると認定。控訴審でも同様の事実認定が下されたかたちだ。
セレスポ側は判決に「遺憾」のコメント
同社は6月3日、適時開示で「原審の事実認定と判断の不当性を訴え、引き続き無罪を主張してきたが、控訴審で当社側の主張が認められなかったことは誠に遺憾」とするコメントを公表し、判決内容について弁護人とともに精査のうえ、今後の対応を検討するとしている。一方、鎌田被告は上告の方針を示している。
博報堂に続く2社目の高裁有罪、業界全体の責任問う声も
東京五輪談合事件では、公正取引委員会が2023年2月28日、セレスポのほか、広告最大手の電通グループ、博報堂、東急エージェンシー(未上場)、フジクリエイティブコーポレーション(未上場)、セイムトゥー(未上場)の6社を告発。東京地検特捜部が法人と関係者計6人、さらに組織委元次長を起訴していた。
このうち、控訴審での判決が言い渡されたのは、2024年の博報堂に続いてセレスポが2社目。両社ともに高裁でも有罪判決となった。他4社も1審で有罪判決を受けており、東京五輪の舞台裏で公正な競争が損なわれていた構図が改めて浮き彫りとなっている。
「官民一体の構造的問題」との指摘も
有罪が確定した元組織委次長をはじめ、業界と官側との癒着が構造的に指摘されるなかで、談合体質そのものを断ち切れるかが今後の焦点となる。入札制度のあり方や再発防止策に対する社会の視線も厳しさを増しており、公的イベントにおける透明性の確保は喫緊の課題といえる。
五輪という「特別仕様」が談合を招いた構造的背景
東京五輪をめぐる入札談合事件の根底には、巨額予算が動く一方で、準備期間の制約や政治的プレッシャーにより、“公正な競争”よりも“円滑な遂行”が優先される構造があったと指摘されている。
広告代理店業界に長年身を置いている関係者は、今回の事件について次のように語る。
「テストイベントや本大会の運営業務は、発注仕様が曖昧なまま進行していた。時間がない中で“あの社に任せるべき”という空気が自然に生まれ、裏で発注側との意思疎通が行われていた。明文化されずとも“調整”は暗黙の了解だった。ただ、大阪万博のごたごたを見てもらえばわかるように、広告代理店が入らなければ回せない規模の案件もあるのだ。」
これは特定企業への利益誘導という単純な構図ではない。むしろ、「プロジェクトを止めてはならない」という使命感にも似た心理が、結果として競争排除につながったという。
あるイベント業界関係者は「本来は公共調達として、透明で公正であるべき案件だが、五輪という“国策プロジェクト”では、平時のルールが通用しなかった」と証言する。セレスポや博報堂といった経験豊富な大手企業に“任せるべきだ”という空気が、入札前から形成されていたとされる。
このように、大会の成功が最優先された結果、官と業界の“協働”が談合という不正に結びついた構図は、五輪という特殊な状況下でこそ生まれた可能性がある。
「談合の再発を防ぐには“受発注の透明化”が不可欠」
関係者の間では、「責任は個人や企業のみにあるのではなく、制度そのものが談合を温存してきたのではないか」との懸念が広がる。先ほどの関係者は「どこまでが準備協議で、どこからが違法行為なのか、その線引きすら曖昧だった。今の制度設計のままでは、再発を防ぐのは難しい」と指摘する。
現在、政府はスポーツイベントや大型国策プロジェクトの発注プロセスについて、より透明性を求める方向で制度見直しを検討している。しかし、業界内では「現場のスピード感と法令遵守がいまだに乖離している」との声も根強い。
五輪のような一大事業でこそ、信頼の土台となる入札制度の厳格な運用が必要とされる。今回のセレスポに対する高裁判決は、単なる一企業の処罰にとどまらず、業界全体に対する“構造変革”の必要性を突きつけたといえる。