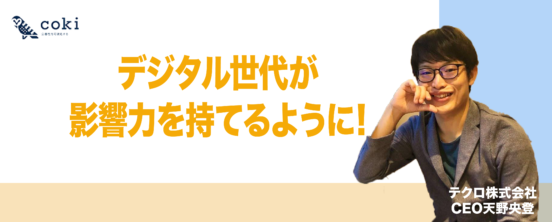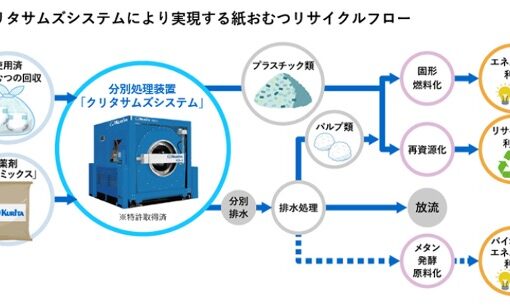日本企業の採用慣行に大きな転機が訪れた。富士通株式会社が、長年にわたり続けてきた「新卒一括採用」の制度を2026年卒から廃止すると発表した。かねてより議論されてきたこの日本独自の採用スタイルに、ついに大手企業が終止符を打ったかたちだ。
富士通の決断は、単なる採用手法の変更にとどまらない。年功序列や終身雇用と並んで「日本的雇用」の象徴とされてきた新卒一括採用の終焉は、若者のキャリア観を変え、大学教育にも影響を及ぼす可能性がある。
「ジョブ型」への完全移行
今回の改革により、富士通は通年採用体制へと移行する。職務ごとに明確な要件を示し、それに合致した人材を柔軟に採用する「ジョブ型人事」が全面適用されることになる。内定者の給与も、これまでの一律処遇から脱し、職務内容や求められるスキルに応じて差を設ける方針だ。
富士通の平松浩樹CHRO(最高人事責任者)は、「潜在能力に期待して長期的に育成する『ポテンシャル採用』には限界がある」と日経新聞で語り、即戦力に近い人材の獲得と定着を急務とした。一方で、長期インターンシップの強化を通じて、採用の精度を高めるという。2026年卒の学生向けには、前年度比で十数倍にあたる数百人規模の有償インターン枠を設ける予定である。
若者に広がる「旅と探究の時間」
新卒一括採用の廃止は、学生たちのライフデザインにも自由度を与える。これまでの就職活動は、3年生後半から始まる「就活戦線」が人生の一大イベントとなっていたが、それに縛られる必要がなくなる。
例えば、卒業後に1年ほど旅に出たり、自らの関心分野を深掘りする「ギャップイヤー」を設けたりする学生が増える可能性もある。キャリアの選択がより主体的になり、社会に出るタイミングも多様化することが期待される。
一方で、「全員が安心して一社に就職する」ことによって新卒の失業率が低く抑えられてきたという、日本型システムのメリットが薄れる懸念もある。セーフティネットとして機能していた側面が失われることで、職を得られない若者が一定数生まれるリスクも無視できない。
海外と比較する就職システムの違い
日本における新卒一括採用は独特な制度であり、諸外国とは大きく異なる。今回の富士通の改革を機に、日本と海外の就職制度を比較することで、より多角的な理解が可能となる。
アメリカ:インターン重視・即戦力重視の市場主義
アメリカでは新卒一括採用という概念自体が存在しない。学生は学年を問わず、インターンシップやアルバイトなどを通じて企業と関係を築き、職種ごとの求人に応募していく。卒業後にすぐ就職する義務もなく、大学卒業後に起業やボランティア、大学院進学、就職浪人を経るケースも一般的だ。
また、採用はポジションベースで行われ、給与も職務内容と交渉力によって決まるため、「配属ガチャ」のような概念は存在しない。企業は即戦力を求める傾向が強く、スキルを可視化するポートフォリオや実績の提示が必須となる。
韓国:公務員志向と競争過熱の両立
韓国でも一括採用の慣行はあるが、日本よりも競争が熾烈だ。特に大企業や公企業は人気が高く、学歴フィルターや筆記試験を経て採用が行われるケースが一般的である。また、韓国では「就職浪人」(再挑戦)も社会的に容認されており、卒業後に1〜2年かけて準備を続ける若者も多い。
近年では職務中心の採用や中途採用も拡大しており、日本同様に「スキルベース」への移行が模索されている。ただし、韓国でも長時間労働と成果主義によるプレッシャーが社会問題化しており、柔軟なキャリア設計はまだ浸透しきっていない。
ヨーロッパ:多様な進路と職業訓練の文化
ヨーロッパ、とりわけドイツやオランダ、北欧諸国では、早期からのキャリア選択と職業訓練制度(デュアルシステム)が整っている。大学に進学する者だけでなく、高校卒業後すぐに職業訓練を経て企業に就職するルートも一般的で、実務スキルと理論教育が並行して進められる。
新卒・中途の区別がほとんどなく、求人は通年で行われる。また、転職もキャリア形成の一部として肯定的に捉えられており、「流動性の高い労働市場」が成熟している。企業と学生の間に中間支援機関が存在する国も多く、雇用のマッチングに公共が関与している点が特徴だ。
教育と企業、双方に突きつけられる課題
こうした比較を通じて明らかになるのは、日本型雇用がこれまで担ってきた「安定性」と「効率性」の一方で、個々人のキャリア設計に自由が乏しかったという現実である。今後、企業は人材要件を明確に提示し、学生は主体的に選び取る必要がある。大学教育にも、より実践的かつ柔軟なカリキュラム設計が求められるだろう。
日本企業の人事改革に波及か
富士通は、1993年に成果主義人事を導入した先進例を持ち、今回もその姿勢を貫いた。「90年の歴史があるこの規模の会社でも変われることを示したい」と平松氏は語る。
富士通の決断は、他の大手企業にとっても無視できない前例となるだろう。就職活動の構造が根本から変わることになれば、日本社会における「仕事と人生」の在り方そのものが、次のフェーズへと移行する端緒となる。