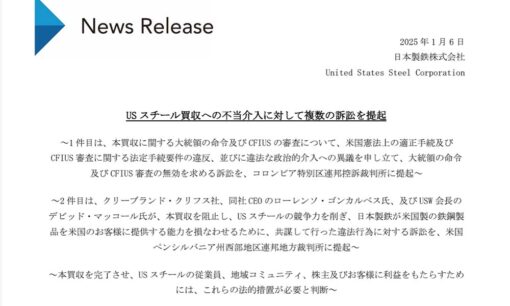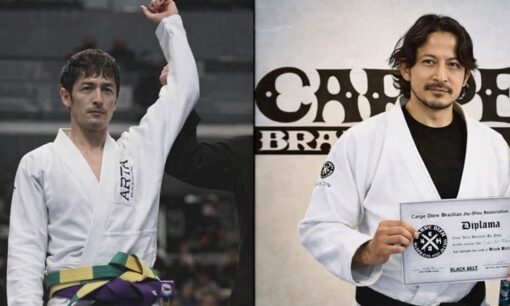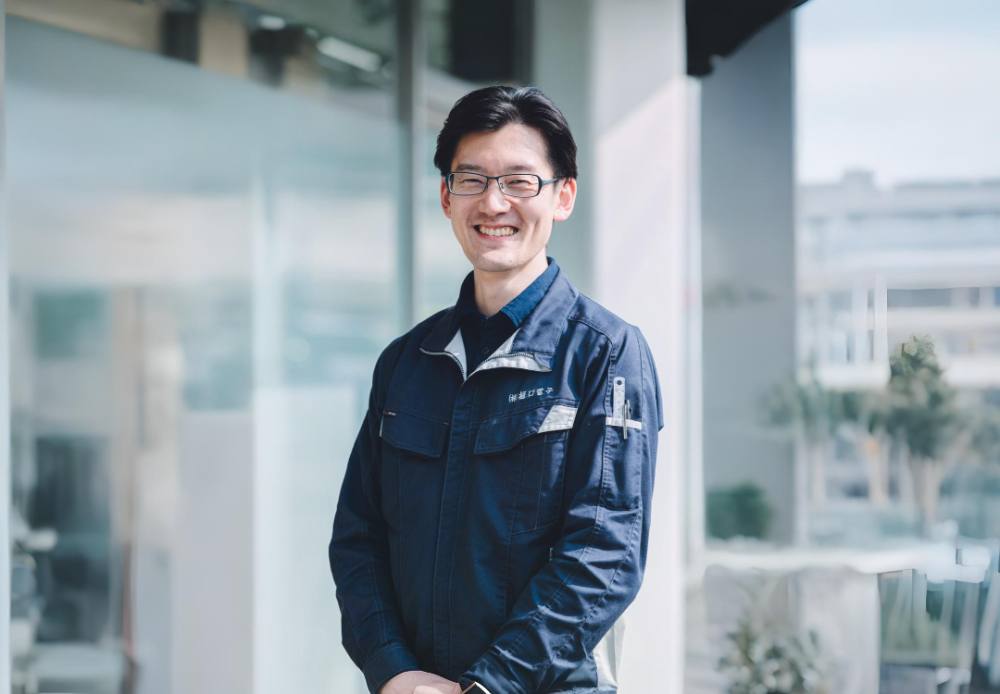
自分たちを「コンビニエンス加工屋」と名乗る、株式会社樋口電子(以下、樋口電子)。製造業である同社と、「コンビニ」は一見すると相容れない存在に見える。しかし、高齢化、人手不足、人口減少、後継者不足…さまざまな課題に直面する日本の産業において、この「コンビニ」が、大きな一手になるかもしれないのだ。
樋口電子は日本の製造業の基盤を守るため、新たな挑戦を始めている。「コンビニエンス加工屋」とは何なのか、なぜそれが必要なのか。樋口電子の次期社長として、現在は専務取締役を務める樋口真士氏に聞いた。
失われゆくモノづくりの基盤を守る。地域の身近なパートナー
大阪府を拠点とする樋口電子は、電子部品の加工・組立などの手作業のアウトソーシングサービスを提供する会社だ。1996年の創業以来、各種電子基板・ハーネスの調達から設計、実装、検品まであらゆる業務を請け負ってきた。
短納期、小ロットから多様な依頼に応えてきた中で技術が磨かれ、今では対応できる手加工は20種類ほどに。手加工で少量多品種に対応できる企業は少なく、お客様のニーズにきめ細かく対応できることを大きな強みとして、地元のモノづくりを支えてきた。
近年、自動化やAIがますます発達しているが、日本の電子機器の製造現場において手加工を必要とする場面はまだまだ多いという。人間の判断能力が求められるために、人の手による加工、修正でしか対応できないケースがあるのだ。そのため、航空宇宙や軍事製品、産業機器の製造をはじめとするさまざまな場面で手加工が行われている。

しかし、製造業は後継者不足、高齢化などの大きな課題を抱えている。2024年時点で、製造業の企業の約43.8%が後継者が決まっていない状態にあるという(※1)。廃業する会社も少なくなく、2022年は5,479社が休廃業・解散している(※2)。樋口氏はその状況を目の当たりにし、大きな危機感を感じてきた。
「取引先も同業もどんどん廃業し、町工場が消えていっています。また、経営者や従業員も高齢化が進む中、それに対処しきれていない会社も目の当たりにしてきました。例えば、70代の従業員が20年以上作り続けている製品があり、外注するとその人の仕事がなくなるし、外注しないとその製品は作り続けられない…と。2040年には働き手が1,100万人足りなくなり、近畿地方相当の労働人口がいなくなるともいわれています。誰かが何かしなければ、仕入れ先も売り先もなくなってしまうと感じました。
また、海外で生産することも増えており、このままでは国内産業は縮小して日本が貧乏になってしまいます。それだけでなく、技術や設計も海外に出ていってしまうでしょう。このままでは、日本のモノづくりの土台が失われてしまうのではないかと感じました。日本にはコアな製品や「すごい製品」がまだまだ残っています。そうした製品や、それが作れる環境を支えたいと強く思うようになりました」(樋口氏)
そこで樋口電子が編み出したのが「TESHIGOTOでんき+」というサービスだ。小ロット多品種で、手加工が必要な部分だけをアウトソーシングで対応する。“コンビニ”のような身近さでお客様のパートナーとなる、モノづくりの土台に便利な加工屋だ。
また、専門業者だからこそスピードや品質、コストのどの点においても強みがあるため、アウトソーシングの方が早く、品質向上にもつながり、単価も安くなることは少なくないという。それにより、各企業が自社の事業や使命に集中してクリエイティブな営みに時間やコストを割くことができるようになり、新しい商品が生まれやすくする狙いがある。
「日本の『すごい製品』を守り、新しい製品が生まれていく環境を守るためには、産業基盤がなかったらどうしようもありません。モノづくりを支える土台として、当たり前に手加工をアウトソースしてもらうことで、各企業の使命に集中してほしいと考えています」(樋口氏)
この構想から3年、コンビニ加工屋として事業を始めてから売上は160%に。問い合わせも増えており、高い需要があることを感じているという。
※1:帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2024 年)」
※2:経済産業省「2023年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」第5節より
今だからこそ、やらなければ。コンビニ加工屋のビジョン
コンビニ加工屋は、多拠点で展開していくビジョンを持っている。近隣地域の加工屋同士でビジョンを共有し、得意分野を共有することで生産委託関係を作り上げるのだ。それにより、早い・便利・楽というまさに「コンビニ」のようなあり方を製造業で実現する。そして、ビジョン共有・地域最適化・新商品誕生・仕事が生まれる、というサイクルが回っていくことにより、地域の加工屋全体で売上がアップし、継続的に売上を上げていくことが可能になる。
また、後継者が決まっていない加工屋であれば、樋口電子が持つ幅広い技術と経験を活かして事業継承することで、地域としても支えていく考えだ。
「自動化している部分と、していない部分の間にあるちょっとした手加工の部分を担う会社が減っていったら、みんながちょっとずつ人を奪い合うわけですよね。この人口減少の中では奪い合うのではなく、各企業にノウハウや製品が効率よく行き渡るように分配することが必要だと思います。そういう関係性こそみんながwin-winになれるし、今後の日本のためにもなるのではないかと思うんです」(樋口氏)

樋口電子のコンセプトは「時代の力になる」こと。そのためには、先端技術・古典的技術にかかわらずその時に必要な手段を選べるようにならなければならない。廃業が進み、日本が衰退していくこの時代に必要な手段こそ「コンビニ加工屋」であり、今やらなければならないのだ。コンビニ加工屋を通じて、「サプライチェーンの一角のような存在になりたい」と樋口氏は語る。
「今の時代に必要なのは、いかに効率を上げて、なくなろうとしている日本の産業基盤を守るかということです。製造業において一番効率が悪いのが手加工の部分なので、そこにアプローチすることこそ日本全体の生産性向上への近道だと思います。それにより、人口は減っていくのに、生産量はずっと変わらず、むしろ増えている、そんな産業を実現したいです」(樋口氏)
「自分は社長にはなれない」諦めていた夢を叶えるチャンス
ー小学生の頃から「樋口電子の社長になりたい」と思われていたそうですが、なぜそう思うようになったのでしょうか。
樋口電子の社長として働く父の背中を見ていたからだと思います。「サッカー選手になりたい」と同じような感覚で、憧れを持っていたんでしょうね。何より、仕事を通じていろいろな人と関わっているのが楽しそうだったんです。
ーその後、新卒では別の会社に入社して2020年に樋口電子に入社されましたが、もともとどんなキャリアを描いて歩んできたのですか?
私は次男なので、自分は樋口電子の社長にはなれないと高校生の頃には気付いていました。それからは樋口電子の社長をイメージすることはなくなったものの、大学は電子情報工学科に進みました。その後、「大きいものを動かす方がかっこいいな」と思い、機械メーカーに入社しまして。もともとは機械を制御する部分の開発や設計を志望していたのですが、適性を見て技術営業の配属になったんです。
技術営業とはいえ、お客様の図面をもとに素材から完成、搬送などの構想を自分で考えることができ、自分の思いが現場に反映されるのが非常に面白くて。とても楽しんで仕事をしていました。3年目からはメインのお客様も任せてもらい、海外へも行かせてもらって、子会社とのコラボレーションを初めて成功させました。でも、そのタイミングで辞めて、樋口電子に入社したんです。
ー楽しいうえに、成功を収めたタイミングで辞められたと。かなり大きな決断だったのではないですか。
そうですね。次は私が海外駐在に行かせてもらえるかもしれないという話もあり、樋口電子に入社するとしても、その後考えようと思っていたくらいでした。でも、そんな時にコロナ禍に見舞われて。樋口電子の業績はガクンと落ち、廃業の準備をするほど苦しい状況になっていました。
そこで、兄と父と3人で会社のことをオンラインで話したんです。その中で、当時はコロナ融資もあり、樋口電子でチャレンジするなら最後のチャンスだと。夢だった「樋口電子の社長になる」を実現させる大チャンスでもありましたし、「なんとか立て直したい」という思いもあり、大阪に戻らせてほしいと願い出て樋口電子に入社することになりました。前職はある程度大きい会社でしたし、そこにいた方が苦労せずに安定して働けたでしょうから、父には反対されましたね。

ーそれから何年くらいで業績は持ち直したのですか?
2期かかってようやく黒字まで持ち直すことができました。それまでは身を粉にして働いて、必死に取引先を増やしていました。当時はコロナ禍で半導体が不足しており、こんな小さな会社にまで部品が回ってこなかったんですよ。だから、部品を集められるような会社にひたすら潜り込んで、仕事をもらってきていました。あの時お付き合いいただいた企業さんがいなかったら、今の樋口電子もなかっただろうと思います。
成長するための会社づくりに欠かせないもの
ーここ数年でホームページのリニューアルやロゴ変更、「アトツギ甲子園」出場など、新しい取り組みをいろいろとされていますが、会社として新しいことをしていこうという考えなのですか?
そうですね。表に出ていくことで人目につく機会を増やし、営業を効率化する狙いもあります。ただ、単純計算で私はこの会社であと40年頑張らないといけないんですよね。技術の発達、人口減少と、きっとこれからの40年はものすごい変化があるじゃないですか。「これからどうやって生きていく?」なんて問われる時代の中で、やれることはどんどんやっていこうという思いです。
ーそういった対外的な活動以外にも、社内の環境や制度の改善にも取り組まれていますか?
はい、取り組んでいます。例えば、朝礼は私が入社後に始めた取り組みです。毎朝10分間、従業員みんなでコミュニケーションを取るんです。
これから会社の規模を拡大することを考えると、人数が増えるにつれて今よりもコミュニケーションが取りにくくなると思います。話したことがない人がいたりもするでしょう。でも、従業員みんなが協力し合える関係でなければ、組織としてのメリットは最大化できません。100人の企業になったら、100人がそれぞれの仕事をしているよりも、100人が協力した方が当然大きい仕事ができますから。そういう体制を作るために、コミュニケーションは大切にしたいと考えています。
また、手加工のノウハウは指示書はあるものの、個人が持っている効率化の技術やちょっとしたコツは全部頭の中にあるんですよね。それはコミュニケーションでしか伝わりません。そういうものを教えあえて、柔軟に取り込んでいける環境を作りたいとも考えました。
こうした考えから朝礼を始めて、最初は業務報告や事務連絡をしたり、班に分かれて会社に関するテーマを決めて話し合ったりしていました。でも、最近は雑談に変わってきていまして。というのも、ライフステージに応じた柔軟な勤務制度を整えているのですが、柔軟にすると、個人のバックグラウンドを知っていた方がいい場面があると思うんです。例えば、お子さんがいるとか、親御さんの介護があるとか。そういうことを知っていると、「サポートしよう」という思いが生まれると思います。そういう思いを持ち、会社全体でお互いに助け合っていると意識してほしいですし、周りの人がフォローしてくれるから安心して休めるような環境も作りたいと考えています。
ー働きやすい制度にはどのようなものがありますか?また、そうした社内の環境や制度の改善を進める中でどのような変化がありましたか?
子育てをしながらの従業員も多いので、ライフワークバランスの充実も大切にしています。休みの連絡は業務用のLINEだけでよくして、有給は一時間単位で取れるようにしました。また、パートさんは朝6時から夕方6時の間でいつでも自由に働いていい制度にもなっています。
もともと離職率は低かったのですが、さらに低くなっていますね。これまで未経験の方も含めて14人雇って、離職したのは2人だけです。自由で柔軟に働けることは、メリットに感じていただけているのだと思います。

より良いものを早く、楽しく。樋口電子のあり方
製造業、手加工、地域。日本の社会がこれからも良いものであるために、今何が必要かを常に考えているのが樋口電子なのだ。それを実現するために、これからどんな会社を目指しているか。最後に伺った。
「コミュニケーションをちゃんと取りあえて、ゲームのように楽しく働ける樋口電子でありたいです。手加工はオンラインではできませんし、事業を展開し技術を継承していくためにはコミュニケーションが一番大切ですから。また、今既に取り組んでいるように、手加工の効率化は絶対に欠かせません。生産性向上を愚直に考えられる社員がたくさんいて、ゲームのように作業を早く楽しくさせ、間違いなく品質のいいものができる会社でありたいと思っています」(樋口氏)
◎プロフィール
樋口真士
株式会社樋口電子 専務取締役
◎会社概要
会社名:株式会社樋口電子
住所:〒569-0841 大阪府高槻市西面北1丁目12番1号
事業内容:業種 ソフト・ハード開発、プリント基板の設計・製作・実装、製品の組立、ハーネスの製作・手配、部品調達(電子部品、ハーネス)
URL:https://www.higuchi-ele.com/