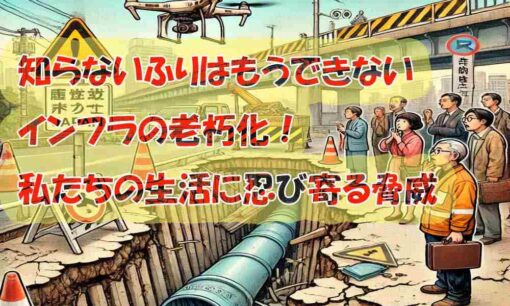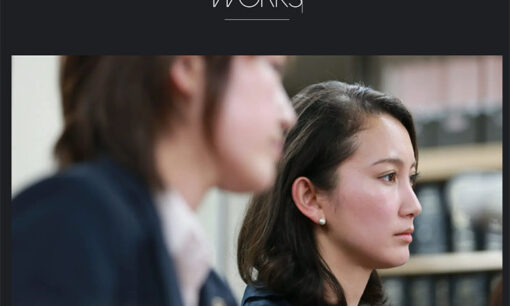親を亡くしたり、保護者に障害がある子どもたちの進学を支援する公益社団法人あしなが育英会の奨学金制度で、申請者の急増により不採用が相次いでいる。2023年度から全額給付型に変更された高校奨学金には希望者が殺到し、2024年度の千葉県内では申請者の半数以上が支援を受けられなかった。物価高騰も重なり、大学生向けの支援枠も逼迫するなか、制度の持続可能性と社会の支えが改めて問われている。
「全額給付型」転換で応募者が殺到 物価高が進学希望に影を落とす
病気や災害、自死などで親を亡くした子どもや、重度の障害を持つ保護者のもとで暮らす子どもを支援する公益社団法人あしなが育英会(東京都千代田区)の奨学金制度が、近年、支援希望者の急増により大きな岐路を迎えている。特に高校奨学金については、制度の「全額給付型」への移行と物価高騰の影響が重なり、2024年度には千葉県内で申請者112人のうち採用は47人にとどまった。
これは**東京新聞(2025年4月19日付、河津真行記者)**による報道に基づくもので、同会は制度変更による人気の高まりと生活コストの上昇が主因だと分析している。
高校奨学金は給付型へ 急増する応募と採用の乖離
あしなが育英会の高校生向け奨学金は、2022年度まで貸与・給付一体型で提供されていたが、返済の心理的・経済的負担を軽減するため、2023年度より返済不要の全額給付型へと転換された。この変更を受けて申請数は右肩上がりに増加し、支援の枠組みが追いつかない状況が続いている。
■ 高校奨学金制度概要(2025年時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 保護者が死亡または重度障害を持つ家庭の高校生 |
| 奨学金の種類 | 全額給付型(返済不要) |
| 支給額 | 年額48万円(月額4万円) |
| 応募時期 | 年1回(春期) |
| 採用状況(千葉県) | 2024年度:申請112人中47人採用(不採用65人) |
大学生向け奨学金も拡充 無利子貸与と給付型支援の両輪で支える
高校卒業後も、進学先で経済的な支援が必要となるケースは少なくない。あしなが育英会では、大学生・大学院生を対象とした無利子貸与型奨学金のほか、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)と連携した給付型奨学基金を運用している。
■ 大学生向け奨学金制度(2025年時点)
◇ 大学奨学金(無利子貸与型)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 保護者が死亡、または1~5級の障がいを持つ家庭の大学・短大生 |
| 月額貸与額 | 一般:月額4万円/特別:月額5万円 |
| 返還条件 | 卒業後6か月以降から20年以内に無利子で返還 |
| 応募時期 | 毎年5月20日消印有効 |
| 選考方法 | 書類審査・作文・オンライン面接(6月実施) |
◇ あしながMUFG奨学基金(給付型)
| 支援種別 | 対象者 | 月額給付額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 理系大学生支援金 | 理系学科に在学する大学奨学生 | 月額4万円 | |
| 文系大学生支援金 | 文系学科に在学する大学奨学生 | 月額2万円 | 2025年度から倍額に増額 |
| 理系大学院生支援金 | 理系の大学院に在学する奨学生 | 月額4万円 | |
| 大学進学支援金 | 高校奨学生で大学進学予定の者 | 一時金30万円 | 進学前に給付 |
| 進学仕度一時金 | 高校奨学生で短大・専門進学予定者 | 一時金30万円 | 進学前に給付 |
申請者の声 「奨学金がなければ進学は無理だった」
支援を受けながら学ぶ学生の証言は、制度の意義を如実に物語る。東京情報大学(千葉市若葉区)に通う3年生の男子学生(20)は、5歳で母親を乳がんで亡くし、小学1年時に新潟市へ転居。父親は東京の職を辞し、祖父母のもとで子育てを続けながら働いた。
家庭の経済状況は常に厳しく、当初は高校卒業後に就職する意向だったが、工業高校で学ぶ中で情報分野への関心が高まり、大学進学を志すようになった。首都圏への進学は学費に加え生活費の負担も大きく、あしなが育英会の給付型奨学金が決定打となったという。
「奨学金がなかったら、本当に生活は苦しくなっていた」と彼は語る。その言葉には、給付制度の存在が単なる経済的支援にとどまらず、人生の選択肢を広げる後押しとなっている現実が込められている。
街頭募金に学生らが立つ 4月中に千葉県内各地で実施
奨学金制度は市民の寄付によって支えられている。あしなが育英会では制度維持のため、春と秋に街頭募金活動を実施している。2025年春の募金は、4月19日・20日・26日・27日の4日間、JR千葉駅東口やJR船橋駅南口など県内の主要駅前で行われる。時間は正午から午後6時まで。
同会の担当者は「経済的な理由で進学をあきらめる子どもを一人でも減らしたい」と話し、広く支援を呼びかけている。
将来を担う子どもたちの夢を守る制度が、今まさに試練に直面している。社会全体で制度の意義を見つめ直し、支援の持続可能性を高める仕組みの再構築が求められている。