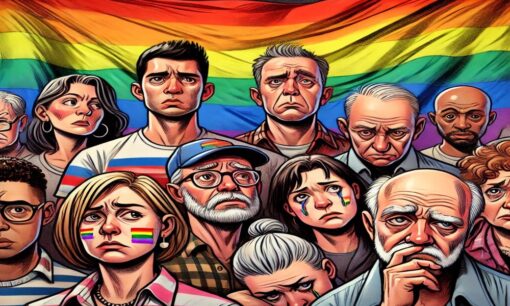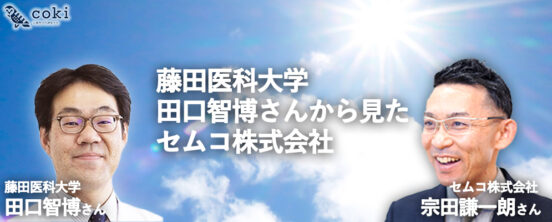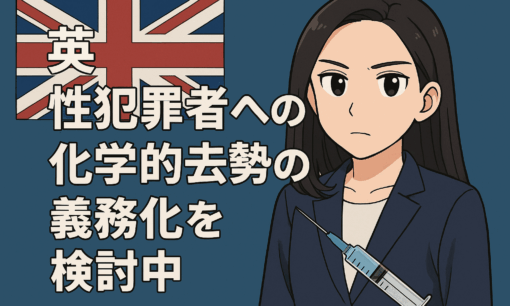なぜいま田畑の近代化なのか

まず注目すべきは、ロボットトラクターとドローンが同時に稼働する光景だ。GPSとセンシング技術が融合した無人機は、葉色指数を読み取りながら施肥量を自動補正し、圃場を短時間で縫う。農林水産省が3月にまとめた実証プロジェクトの報告によると、こうしたスマート農業技術はすでに全国217地区で試験導入され、確かな成果を挙げているようだ。
ロボットとAIが圃場を「可視化」する
次に、上記の機械群を束ねるクラウド型営農管理システムに目を向けたい。ドローンや衛星から得た生育データはAIで解析され、最適な防除時期や追肥ポイントがスマートフォンに届く。「見る・測る・動かす」を一気通貫で実現するこの仕組みが、ムダな重複作業を排除しつつ生産計画の精度を高めている。
さらに数字が示す省力化――最大80%の時短
こうした仕組みは、統計的にも効果が裏づけられている。たとえばドローン防除は従来手法に比べ作業時間を平均61%短縮し、遠隔操作の自動水管理システムは圃場巡回を8割減らした。
直進アシスト田植機でも18%の削減が確認され、熟練者と同等の精度を維持した。
だからこそ人材も変わる――女性と若者が主役に
ここで労働力の質的変化に触れておきたい。岐阜県の集落営農法人では、経理担当だった女性がロボットトラクターのオペレーターとなり、経営面積を164ヘクタールから196ヘクタールへ拡大。輸出用米の生産量は2.8倍に跳ね上がった。
同様に宮崎の法人では、ラジコン草刈機を投入した結果、学生アルバイトが夏場の草刈をゲーム感覚でこなし、作付面積を1.4倍に広げた。
もっと後押しする制度と資金
もっと導入を進めるため、昨年施行されたスマート農業技術活用促進法が追い風となる。同法は技術導入と生産方式の刷新をセットで認定する「生産方式革新実施計画」を創設し、長期低利融資や特別償却、ドローン飛行許可のワンストップ化を提供する。
開発側も研究設備の供用や登録免許税の軽減が受けられ、開発と普及を同時にドライブする設計だ。
そしてデータが業界をつなぐ――WAGRIの登場
制度面の整備と並行して、データ連携基盤「WAGRI」が118社を束ね始めた。気象・土壌・衛星画像といった公的データをAPI経由で提供し、営農支援アプリや可変施肥マップなど多様なサービスが次々と生まれている。農家は作目や経営規模に合わせてツールを選び、サービス事業者は相互運用性を確保しつつビジネスを拡大する――そんな好循環が芽生えている。
未来を担う学びの場へ、高校生がドローンを操縦
データ時代を担うのは次世代の人材だ。農業高校・大学校ではドローン操縦や環境制御を学ぶカリキュラムが整い、実習農場には無線LAN網が行き渡った。オンライン教材と出前授業を組み合わせた研修には教員と学生あわせて数百人が参加し、現場で即戦力となるICTスキルを習得しつつある。
それでも残る壁と広がる可能性
もっとも、初期投資の高さと技術者不足は依然として大きい。それでも補助制度やシェアリングサービスの拡大で導入コストは下がり始めた。人口減少が続くなか、省力化とデータ駆動型経営が浸透すれば、地域農業は「小さくても高収益」なモデルへと転換できる。環境負荷低減、多様な人材参入、そして食料安全保障――スマート農業はそのすべてを同時に叶える切り札になりつつある。