定型業務はAIへ、創造と共感は人間へ。変革期のマネジャー像に迫る
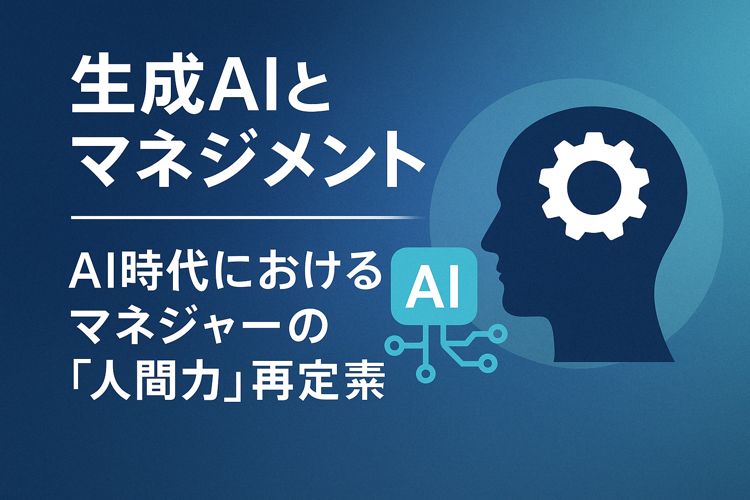
生成AIが社会に登場してからわずか2年半。その間に、対話型AIをはじめとするツールがビジネス現場に浸透し、議事録の作成やレポートの下書き、さらには会議ファシリテーションまで、かつて人が担っていた業務を代替する場面が急速に広がってきた。リクルートワークス研究所が発表した最新の報告書『生成AIが変えるマネジャーの役割と業務』は、こうした時代のうねりの中で、マネジャーの職務と存在意義が根本から再構築されつつある現状に警鐘を鳴らす。
同研究所は2024年12月から2025年2月にかけて、アクセンチュアやイオン、サイバーエージェントなどの企業実務者を招いた研究会を開催。企業におけるマネジャーの役割を「人材マネジメント」と「仕事マネジメント」の視点から11項目に分類し、生成AIの進展がそれらに与える影響を分析した。そこから見えてきたのは、生成AIがマネジメントにおいて「何を代替し、何を強化するのか」という問いに対する実践的な答えである。
マネジャーの「手離れ」業務と「残される」業務
まず明らかになったのは、業務進捗のモニタリングや定型的な例外処理、法対応の一部など、情報の収集・記録・整理といったルーチンワークは、生成AIの導入によって大幅に省力化されるという点である。こうした業務は今後、マネジャーの役割から段階的に外れていくことが予想されている。
たとえば、かつてはマネジャーが目視や口頭確認で行っていたタスク進捗の管理も、AIによってリアルタイムに記録・可視化されるようになり、「進んでいるかを確認するだけの役割」ではもはや価値を提供できなくなるという。
一方で、マネジャーが果たすべき核心的な役割は、むしろ鮮明に浮かび上がってきている。それは、メンバーの動機づけやパフォーマンスマネジメント、さらには学び続ける風土を組織内に醸成し、変化に対応できる人材とチームを育てていくという「人間にしかできない支援」である。評価や計画立案といった業務自体はAIが代替可能でも、個々の背景や志向に合わせた目標設定や適切なフィードバックには、人間ならではの観察力や共感力が不可欠となる。
組織の境界が曖昧になるなかで問われる「個」としての魅力
報告書では、プロジェクトベースの働き方が主流化する中で、マネジャーが果たすべきもう一つの重要な役割として「対社外との関係構築力」を挙げている。生成AIがスキルや専門性を可視化し、人材の探索やマッチングを支援することが常態化すれば、これまで出会わなかったような人材と協働する機会も飛躍的に増える。
だからこそ、マネジャー自身が組織や業務の魅力をイキイキと語れるか、人として信頼されるかといった「人間的な魅力」が要となる。
AIがあらゆる判断材料を提示し、計画を半自動で策定してくれる時代においても、最終的にどの道を選ぶか、誰と一緒に働くかの決断は人間の領域に残される。その意味で、マネジャーは単なる管理職から、未来像を描き、意思をもって判断する「個の力」を問われる存在へと進化を迫られている。
企業が生き残る鍵は「生成AIを使い倒す組織文化」
報告書では、生成AI時代におけるマネジャーの変革を支えるために、企業として果たすべき役割も明示された。経営層が自ら生成AIを使い倒し、背中でその有用性を示すこと。生成AI活用事例を社内で積極的に広報し、話題の中心に据えること。そして、組織として「強みを活かしあう文化」を育て、生成AIを全社員が扱う「共通語」にすること。こうした一連の施策が、マネジャーの役割変革を組織全体で支える基盤になるという。
変化に対する適応力をマネジャーに求めるだけではなく、組織全体が変化を促す土壌を整備することが、これからの企業の生存戦略として問われている。
人間だからこそ担える「変化の担い手」へ
生成AIはもはや敵ではなく、マネジャーが自らの役割を洗練させるための「相棒」となった。業務の一部が自動化されるからこそ、マネジャーは「何をするべきか」に集中できるようになる。報告書の締めくくりには、こうしたAIとの協働の先にあるマネジメントの新しい地平が描かれている。
伝統的な管理能力に頼らず、未来を描き、変化を促し、人を惹きつける——そんな「人間力」が、これからのマネジャーには求められていく。
















