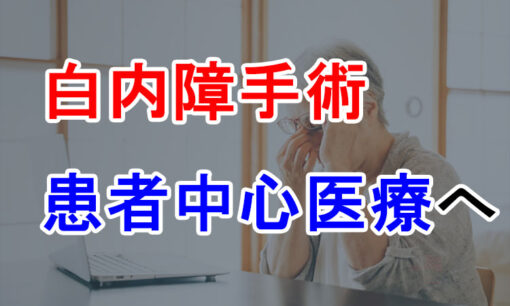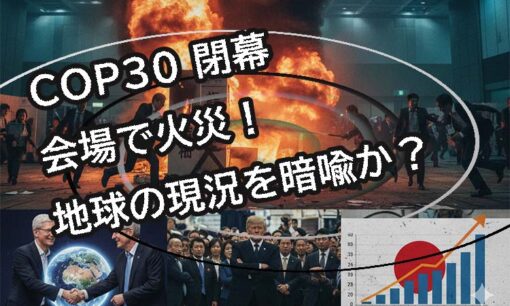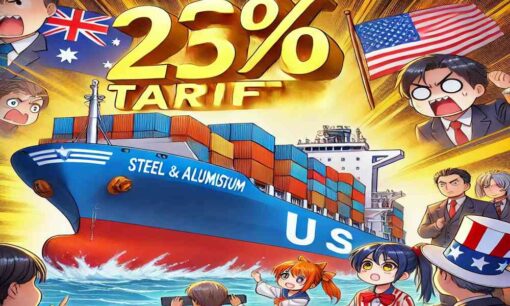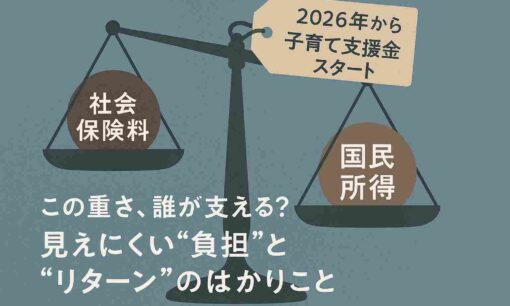2025年度から新型コロナウイルスワクチンの定期接種に対する国の財政支援が打ち切られる方向で調整が進んでいることが、関係者への取材で明らかになった。
対象は65歳以上の高齢者と、基礎疾患を持つ60~64歳の人々。これまで国は1回あたり8300円を自治体に助成し、接種費用の大部分を肩代わりしてきたが、2025年度からはこの助成が終了する。実質的に、自己負担額が大きく跳ね上がる可能性がある。
「特例臨時接種」から「定期接種」へ 支援の役割を終えたとの判断
新型コロナワクチンの公費助成は、感染が拡大していた2021年以降、「特例臨時接種」として全額公費で提供されてきた。2024年度からは、インフルエンザと同様の扱いとなる「定期接種」に移行。その際、急激な負担増を避けるために国が暫定的に助成を続けていた。
この移行措置としての助成が2024年度限りで打ち切られる背景には、「制度としての安定期に入った」とする政府の認識がある。厚生労働省関係者によると、コロナワクチン接種が社会的に恒常化しつつある中で、財政支援をいつまでも続けることは難しいとする判断があったという。
また、助成財源に用いられていた「ワクチン生産体制等緊急整備基金」については、過去に運用損失があったことが2024年2月の衆院予算委員会で指摘されており、政府内では基金の持続的活用に対する懸念も強まっていた。
自己負担は最大7千円に 地方自治体の対応も分かれる見通し
現在、定期接種における費用は1万5千円程度で、このうち最大7千円を自己負担とする形で調整されている。残りは国の助成や基金によって補填されてきた。助成がなくなれば、この7千円の上限が撤廃される可能性もある。
一部の自治体では独自の補助制度を設ける動きが出ており、住民の負担軽減を続ける方針を示している。例えば東京都や大阪市など人口の多い自治体では、高齢者支援の一環として接種費用を継続的に補助する検討がなされている。一方で、財源が限られる中小自治体では対応が難しいとの声もある。
助成終了がもたらす“接種控え”の連鎖 感染リスクの再拡大も懸念
国の助成打ち切りにより、今後コロナワクチンの接種をためらう人が増える可能性が指摘されている。特に影響を受けやすいのが、もともと医療費の負担が重い低所得の高齢者や、複数の基礎疾患を抱える人々だ。
厚生労働省は、定期接種の対象として65歳以上の高齢者と特定の基礎疾患を持つ60~64歳を指定しているが、仮に自己負担が増加すれば、これらの層においても“接種控え”が進む恐れがある。
日本感染症学会など専門団体も、こうした状況に警鐘を鳴らす。ワクチン接種による重症化予防効果は統計的にも確認されており、特に高齢者においては、接種によるリスク低減が大きい。国立感染症研究所によると、2023年のデータでは、コロナウイルスによる入院率や死亡率はワクチン未接種の高齢者で明らかに高かったという。
医療現場からは、「助成がなくなれば、感染予防よりも生活費を優先せざるを得ないという声が確実に出てくる。結果的に重症者が増え、地域医療を再び圧迫しかねない」との指摘もある。
高齢者・基礎疾患層への代替支援策はあるか
国の助成打ち切りに対して、高齢者や基礎疾患を持つ人々を守るための代替的な支援策は以下のように整理できる。
| 支援策の種類 | 内容・備考 |
|---|---|
| 低所得者への無料接種措置 | 住民税非課税世帯などを対象に、接種費用を引き続き全額補助。詳細は今後調整。 |
| 自治体独自の補助制度 | 東京都や大阪市などで継続検討中。実施内容は地域により大きく異なる可能性あり。 |
| 感染症対策外来・相談体制の維持 | 各都道府県が発熱外来や電話相談体制を継続。重症化リスク層への対応を中心に体制整備。 |
| 医療費助成・高額療養費制度の活用 | 感染後の治療費に対して既存の公的医療補助制度が適用可能。事後対応型で予防的ではない。 |
また、支援の継続性と公平性を担保する上での課題も多い。
主な懸念点
- 地域間格差:自治体独自補助は財政余力に依存し、全国的な一律支援が困難
- 所得制限:低所得層は保護される一方、中間層以上は実質的に全額自己負担となる可能性
- 予防策の空白:助成終了が「予防を控える選択」につながると、結果的に医療費増大へとつながる恐れ
専門家からは、「助成の打ち切りは単なる財政措置にとどまらず、公衆衛生全体への影響を慎重に見極めるべき局面だ」との指摘も上がっている。
おわりに――「支える社会」への転換点として
新型コロナウイルスとの共存を前提とした日常が定着しつつある中で、今回の国の助成終了は、制度的にも社会的にもひとつの転換点を迎えたことを示している。確かに、公費による支援が縮小することで、特に高齢者や基礎疾患を持つ人々の不安は拭いきれない。
だが一方で、この変化は自治体や地域社会、さらには個人の備えのあり方を問い直す契機でもある。限られた財源のなかで、いかに脆弱な層に手を差し伸べ、予防医療の格差を防ぐか。そこに知恵と工夫を重ねることで、新しい時代の公衆衛生のかたちが築かれていくだろう。
国や自治体による柔軟な支援の再設計と、地域に根差した相互扶助の仕組みづくりが進めば、「助成がなくなったから終わり」ではなく、「支え合う社会への一歩」として、この変化は次の希望につながっていくはずだ。





![株式会社エッジコネクションが求めるゲーム感覚で仕事を楽しめる人材とは[対談]代表取締役社長大村康雄氏×取締役趙美紀氏](https://coki.jp/wp-content/uploads/2022/03/0c1689de3a0ec4303243c05e52d76699-1-510x306.jpg)