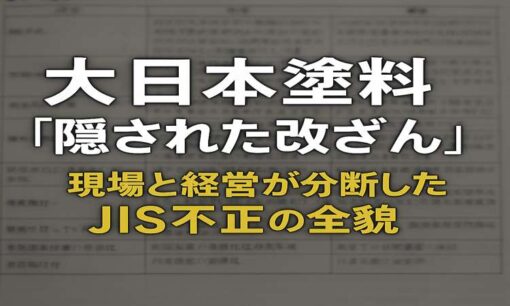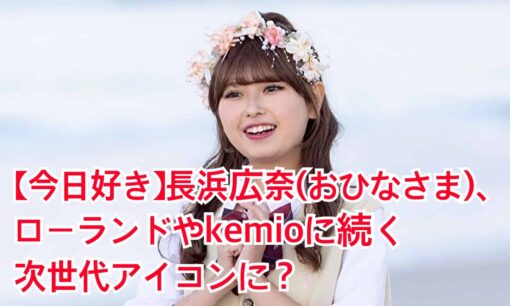ENECHANGE(エネチェンジ)株式会社(東京都中央区)は、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに掲げ、脱炭素社会をデジタル技術で推進する脱炭素テック企業だ。2020年に東証マザーズ(現 東証グロース市場、証券コード4169)へ上場し、エネルギーの自由化・デジタル化・脱炭素化・分散化を見据えたSaaS事業を中心に急成長している。
同社のルーツは、自由化先進国のイギリス・ケンブリッジ大学で行われていた電力データ研究にあり、グローバルなネットワークとエネルギーデータ解析技術を強みとしている。
そんなENECHANGE株式会社が3月25日、東京証券取引所へ「改善状況報告書」を提出した。同社の新規事業であるEV充電事業をめぐる会計処理を巡り、過年度決算の訂正や監査法人との見解相違が表面化。その背景には、SPC(特別目的会社)を介した資金調達やプットオプションの取扱いなど、複雑なスキームが存在していた。
本稿では、ENECHANGEが直面した会計処理問題と再発防止策、さらには同社が発表した最新リリース内容を交えながら、“ルポ”形式で全体像を描いていく。
EV充電事業の現場と企業の躍動
ある秋の日、筆者は首都圏の商業施設に設置されたEV充電スタンドを見学する機会を得た。ENECHANGE株式会社が手がけるその充電設備は、電気自動車の普及を進めるうえで要となるインフラだ。現場担当スタッフは「今後EVがどんどん増えるはず。会社としても攻めの姿勢で設備を整えている」と語る。だが、その“攻め”が同社の内部統制を揺るがす火種を抱えていたことは、当時だれも予想できなかったという。
膨大な数の充電設備を設置するにあたり、ENECHANGEはSPCを活用した独自の資金調達スキームを採用していた。匿名組合出資や社債の発行などによってリスクを切り分けた形にしていたが、実際にはENECHANGE本体がSPCを“支配”していると認定される余地もある――こうした点が問題視され、東京証券取引所への改善報告が余儀なくなったのである。
SPC非連結をめぐる対立――浮かび上がった会計処理問題
事態が公になるきっかけは2024年初頭に、ENECHANGEの当時の監査法人(有限責任あずさ監査法人)から「SPCの連結要否に関する疑義」が示されたことだった。本来であれば、SPCを連結範囲に含めるかどうかは、誰が実質的にリスクとリターンを享受しているか、誰が意思決定を行っているかといった点が判定基準になる。ところがENECHANGE側の説明資料には、代表取締役CEOによるSPC最大出資者への貸付(いわゆる金銭消費貸借契約)の存在が十分に共有されておらず、さらにプットオプション行使条件の扱いにも疑念が浮上。
外部調査委員会が着手した調査の過程で、Slackやメールなどのデジタル・フォレンジック調査を実施すると、「代表取締役CEOへの権限集中」「取締役会・監査役会への情報共有の不備」「コンプライアンス意識の欠如」が次々と明らかになっていった。ただし、監査法人と外部調査委員会では、経営トップらが“意図的に不正を図った”か否かについて評価が分かれた。ENECHANGE側は「隠蔽する意図はなかった」と説明しつつも、監査法人は「重要な事実を隠蔽した可能性がある」と断じ、対立は深まった。
高まるプレッシャー――売上目標と株価のはざまで
急成長を期していたENECHANGEでは、EV充電事業による売上確保が株価上昇の大きな原動力になると期待されていた。執行役員の報酬にはストックオプションが多用され、結果的に「なんとしても事業目標を達成したい」という雰囲気が社内に充満したとされる。
しかし、管理部門からすれば、複雑な会計スキームを扱うには慎重なリスク検証や監査法人とのコミュニケーションが不可欠だ。にもかかわらず、短期的な業績目標を優先するあまり検討が後手に回ったと外部調査委員会では指摘される。取締役会や監査役会も十分な情報を得られないまま会計処理が決定され、最終的に2024年秋から冬にかけて大幅な過年度決算の訂正が余儀なくされた。
現場の声――内部統制の問題は何をもたらしたか
「不正があったか否かはともかく、内部統制の整備不足は否めない」――これはENECHANGE内部の関係者が口をそろえて認めるところだ。EV充電スタンドの現場スタッフは、「事業自体は進めたいし、急ぐのは当然と思っていた。でも、監査法人とのやり取りや会社全体の管理体制がどうなっているかまでは、正直よくわからなかった」という。
結局、会社として必要なチェックが働きにくい構造やトップダウン過多の企業風土が、結果として社内外の信頼を脅かす事態につながったことになる。
ENECHANGEが明らかにした再発防止策――東京証券取引所への「改善状況報告書」
こうした問題を受けて、ENECHANGEは改善状況報告書に多角的な再発防止策を示している。代表取締役CEOに経営判断が集中しないよう組織改革を行い、社外取締役との情報連携を強化し、法務や経理、監査の専門部署を拡充してガバナンスの綻びを正していく姿勢を表明した。
さらに、監査法人と速やかに情報を共有し、連結範囲の判定などで意思疎通の齟齬が生じないようにコミュニケーションを改善する方針であることも明言されている。
新たなリリース:海外特化型の脱炭素テックファンドによるEquilibrium Energy社への投資
渦中の同社だが、3月7日に海外特化型の脱炭素テックファンド「ジャパン・エナジー・ファンド」がジャパン・エナジー・キャピタルを通じ、米国サンフランシスコに本社を置くEquilibrium Energy社への投資を実施したと公表した。Equilibrium Energy社は次世代の電力会社向けオペレーティングシステムを構築するテック企業であり、再生可能エネルギー拡大に伴う送電網の不安定化をAIを活用したオプティマイザーによって改善するビジネスモデルが注目されている。
今回の投資額は2800万ドル規模で、GS Energy社が主導し、DCVCやValo Venturesといった既存投資家も参加した。日本を含む世界各地で大容量蓄電施設が増加するなか、電力取引を最適化して収益を最大化する技術開発に拍車がかかっている。
Equilibrium Energy社のプラットフォームはバッテリーなどの資産を管理し、所有者のリスクを抑えつつ取引収益を高められる点が評価されており、ENECHANGEの代表取締役CEOである丸岡智也氏は「こうしたオプティマイザー企業のソリューションは海外だけでなく日本の電力市場にも大きなインパクトがある」とコメントしている。
再発防止の先にあるもの
ENECHANGEに降りかかった会計処理問題は、単なる経営上のトラブルにとどまらず、急拡大するEVインフラ分野で「企業がスピードとリスク管理をどう両立させるか」という普遍的な課題を突きつけている。デザイン思考の観点で見れば、まず“共感”として、社内外のステークホルダーとのコミュニケーションが鍵を握っていたはずだ。投資家や自治体、消費者との対話を緻密に行い、ビジネスリスクを透明化する努力があれば、問題は早期に顕在化していたかもしれない。
そして、“問題定義”の段階でSPCスキームのリスクや会計上のグレーゾーンを洗い出し、外部の専門家とともに“アイデア創出”へつなげられれば、ENECHANGEは市場からの強い信頼を獲得したまま、拡大路線を進められた可能性がある。社内で試作(プロトタイプ)段階を踏み、監査法人とも認識をすり合わせるプロセスづくりが、いわば“テスト”として機能すれば、今回のような大掛かりな決算訂正は回避できただろう。
ガバナンス改革と事業成長の両立に向けて
最初に訪れたEV充電スタンドでは、スタッフがENECHANGEの明るい未来を語っていた。しかし、その裏側では、SPCをめぐる会計処理の不備や情報共有不足が発生し、経営者と監査法人の認識相違が企業の信頼に影を落としていた。今回、東京証券取引所に提出された「改善状況報告書」には、再発防止策として組織体制の見直しやコンプライアンスの強化など、多くの方策が記されている。
この一連の問題によって得た教訓は、「拡大路線を突き進むならこそ、内部統制や法令順守を土台に据えなければならない」という点に尽きるのではないだろうか。ENECHANGEは今後、EV充電事業と同時に海外特化型の脱炭素テックファンドなどを通じて投資活動も行い、より大きなエネルギー市場へと打って出ようとしている。成長とガバナンス改革の両立は、現代社会に求められる企業モデルの象徴でもある。
今回の「改善状況報告書」やEquilibrium Energy社への投資リリースを一連の動きとして捉えると、ENECHANGEが内外に示した“自浄能力”の真価が、これから本格的に問われることになるだろう。