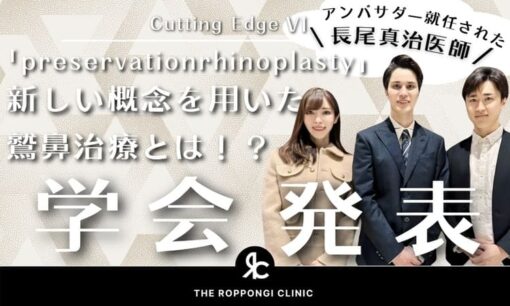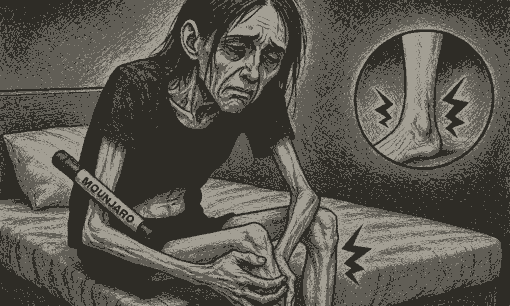奈良県の山あいに位置する御杖(みつえ)村で、建設費約1億円の公衆トイレが物議を醸している。MBSNEWSの報道によると、村民の間では「あの規模でこの値段はおかしい」と批判の声が上がる一方で、村長は「村の良さをアピールするため」との立場を示している。
高額な費用の背景と、御杖村の特性について検証する。
住民の疑問「1億円の価値はあるのか?」
問題のトイレは、御杖村の西の入口に位置する国道沿いに昨年2月に完成した。男女1台ずつの個室トイレに加え、バリアフリー対応やオムツ交換台も設置されているが、外観は一般的な公衆トイレと変わらない。建設費は駐車場やベンチの整備費も含め約9500万円にのぼる。
村の財源として10年返済の「過疎債」が活用され、その7割を国の地方交付税が、残り3割を村が負担する。これに対し、一部の住民は「1億円近くもかけるべきではない」と疑問を呈している。
「これが1億円?」「もっと観光施設の整備に使うべきでは」との声もあり、村議会の議事録によると、設計額7630万円、落札額7590万円で一般競争入札が行われた。通常、競争入札では価格が大きく下がることが期待されるが、落札率は極めて高かった。さらに、半年後に契約額が約25%増加する契約変更が行われた。この変更について、議会ではほとんど議論が交わされず、「質疑なし」という形で承認された。その後、議案は「むらづくり委員会」に付託され、正式な変更契約額も公表されることなく手続きが進められた。
この迅速な決定に対し、住民からは「なぜ議会で十分な審議が行われなかったのか」との疑問の声も上がっている。
村長の言い分「適正価格だった」
トイレの設置目的について、伊藤収宜(いとう・としのり)村長は「村の良さをアピールする狙いがある」と説明する。トイレは、奈良県と三重県を結ぶ伊勢本街道の入り口にあたり、休憩所として観光客を呼び込む狙いもあるという。
また、村長は「奈良県産のヒノキなど地元木材を使用した」とも説明。物価高や人件費の影響も加わり、「価格は適切」との見解を示している。
一方で、近隣の曽爾(そに)村にある公衆トイレは約20年前に建設され、費用は1170万円。御杖村の東側にあるトイレも駐車場付きで2000万円ほどだった。これらと比較しても、今回のトイレの費用は突出しており、「地元産木材の使用だけでは説明がつかない」との指摘もある。
御杖村の魅力と観光資源
御杖村は、奈良県の東端に位置し、三重県との県境にある山村で、面積は約80平方キロメートル。人口は2025年1月時点で1269人と減少傾向にある。
村の歴史は古く、伊勢本街道が通り、江戸時代にはお伊勢参りの宿場町として栄えた。現在も、三峰山(みうねやま)の霧氷や温泉施設「姫石の湯」などの観光資源を有し、自然豊かな環境が魅力とされる。
産業は農業・林業が主体で、ほうれん草や米の生産が行われる一方、人口減少と高齢化が進み、過疎化対策が課題となっている。こうした状況のなかで、観光振興を目的とした公衆トイレの整備は、村の未来を見据えた施策ともいえる。
SNSの声「無駄遣いか、未来への投資か?」
御杖村の公衆トイレを巡る議論は、公共事業の透明性や適正価格についても考えさせられる。SNS上では「公共工事は相場より高くなる傾向がある」「全国各地で同様の無駄遣いが行われているのでは」といった声も見られる。
SNS上では、公共工事の透明性や適正価格について多くの意見が飛び交っている。「親が建設会社経営だが、公共工事は特定企業との癒着で相場よりも高くなりがち」「全国でこのような無駄遣いが行われているはず」「国の交付金を引っ張る仕組みが業者の利益になっている」といった指摘も多い。
一方で、「山間部ではトイレ整備が観光促進に必要」「伊勢本街道を歩く旅行者にはありがたい施設」との意見もあり、地域振興とのバランスをどう取るかが問われている。1億円のトイレが、単なる「高額設備」として終わるのか、それとも観光振興の起点となるのかは、今後の村の取り組みにかかっている。