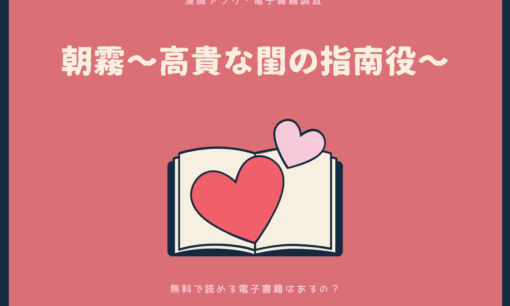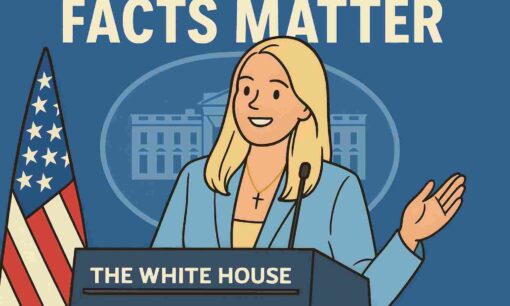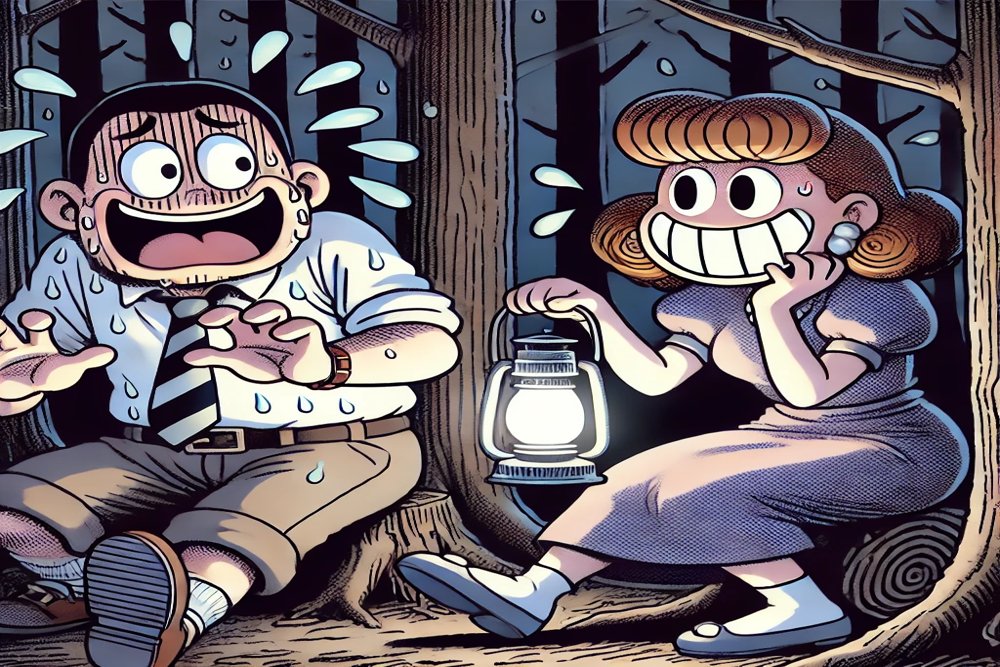
パリ西郊に広がるブーローニュの森で、日中にもかかわらず売春行為が堂々と行われているという――そんな毎日新聞などの報道が2月3日、SNSで話題を呼んでいる。観光都市の華やぎを擁しながら、その森の奥深くには人目を忍ぶ行為がまことしやかに行われ、しかも「より安く、より危険な取引」が増えているとの指摘だ。観光客でにぎわうシャンゼリゼやルーヴルとは対照的な様子に、読者は一様に驚きを禁じ得ない。
フランスでは十数年前から売春規制の強化が進み、買う側に厳罰が科される制度が敷かれている。それでもセックスワーカーに対する処遇や福祉の不十分さが指摘されてきた。むしろ規制強化の裏をかき、より隠微な場所へとこの行為が押しやられ、取引の条件も過酷さを増す――アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの団体が警鐘を鳴らすのも頷ける状況だ。
彼女たちを守るはずの施策が皮肉にもさらなる危険を生んでいる。この森では安易に足を踏み入れられぬ緊張感すら漂うという。
文学が捉えたブーローニュの森
しかし、ブーローニュの森と聞くたび、古典文学が咲かせた優雅なイメージを思い出す読者も少なくないはずだ。たとえば、フローベールの『感情教育』やゾラの『ナナ』、プルーストの『失われた時を求めて』などに散見される“森のシーン”は、社交界の舞台装置としてのパリと、そこにくすぶる欲望の入り混じる暗がりを象徴的に浮かび上がらせる。
クリノリン姿の令嬢たちが馬車で乗りつけ、競馬や散策を楽しむかたわら、森の深奥にはさまざまな身分の人々が錯綜する場所がある。すなわち煌びやかな貴族の余暇を彩りながら、裏面には退廃と官能が絶えず脈打っている空間として描かれてきたのだ。まさに光と影の双方が凝縮された土地、そこにブーローニュの森ならではの魅力が備わっている。
さらに、ジャン・コクトーが脚本を手掛けた映画『ブーローニュの森の貴婦人たち』でも、際立ったコントラストが示される。華麗な公園の風景の裏に隠れた、人間の嫉妬や欲望のさざめき。同作はベル・エポックの名残から第二次大戦後に至るまで、この森が独特の妖艶さを内包してきたことを象徴的に映し出している。
欲望と規制のはざまで
現代の報道が伝える姿は、こうした文学や映画で取り上げられた過去のイメージと奇妙に重なりながらも、さらに複雑さを帯びている。取り締まりが強化されたにもかかわらず売春行為が根強く残るのは、売り手と買い手の両者の需要がまったく消えないからだろう。そうした行為を明確に否定しながら、社会は矛盾を解決できぬまま、闇に潜ってより危険になるのを容認している側面もある。
実際にこの森を歩いてみると、鬱蒼とした木立の陰には、使い捨てられたコンドームがころがっていたり、ホームレスが身を休める姿も見受けられる。パリ市内のあちこちで暮らす人々がいることは周知の事実だが、ここブーローニュの森では、観光パンフレットには決して載らない“現実”が色濃く浮き彫りになるのだ。家族連れが利用するグラウンドや乗馬クラブの賑わいと、薄闇に潜む欲望とが混在するその様相は、人間の多面性を集約したかのようでもある。
社会政策の果たす役割や倫理の是非をめぐる問題は、今後も絶えず議論されるだろう。しかし、かの森で日夜行われる行為が伝えられるたび、往時の作家たちが見た光と影は、現代にこそ色濃く蘇ってくるのかもしれない。
ブーローニュの森という舞台は、パリの華美と人間の欲望、そして法のはざまで揺れ動く“永遠のパラドックス”を映し出す鏡として、まだしばらくは多くの人々の想像力を掻き立て続けるだろう。