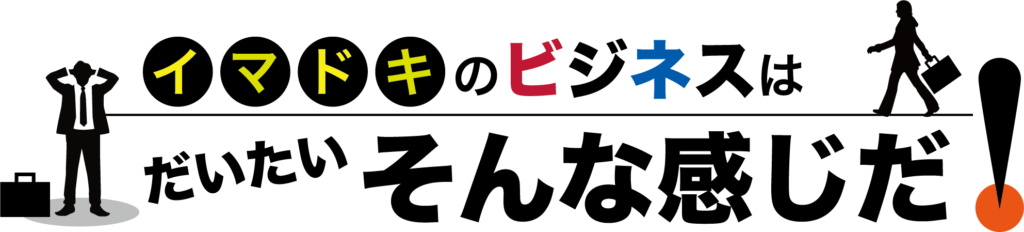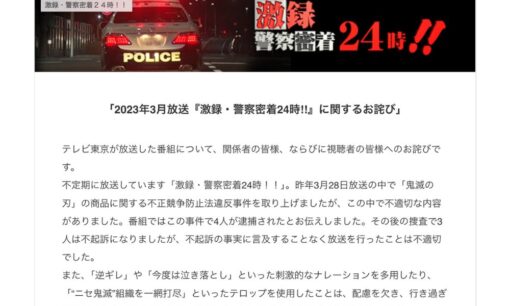最近の経済現象をゆる~やかに切り、「通説」をナナメに読み説く連載の第11回!イマドキのビジネスはだいたいそんなかんじだ‼
問題:次の企業の共通項を探しなさい。
「フォード」「BMW」「フィアット」「ミシュラン」「エルメス」「プジョー」「テトラパック」「イケア」「J・Pモルガン」「カーギル」「ウォルマート」「コーニング」「フィデリティ・インベストメント」「モトローラ」「エステー・ローダー」「L・Lビーン」「ゼニア」「カンパリ」「フェラガモ」「フルラ」
すべて知らなくても、巨大グローバル企業であることは、なんとなく分かると思う。だから正解はグローバル企業……では、問題にはならない。それでは南京豆を落花生と言い換えてるようなものだから。
答えは「同族企業」である。意外?と思われるだろか。
同族企業というと、グローバル企業とは程遠くて、どこかの小さな地方都市でドメスティックな事業をコツコツと続けているイメージが強い。
しかしこの例に挙げたように著名なグローバル企業の結構な数が同族企業である。あのトヨタも同族企業である(ごぞんじですね)。注目すべきは、こうした同族企業はそうでない企業よりも収益性が高いということである。
収益性で非同族企業を圧倒する同族企業
いささか古いが、2007年に甲南大学の倉科敏材教授と帝国データバンクが行った分析では、東証1部2部の企業の07年までの5期の平均利益率は、非同族企業が4.5%なのに対して同族企業が5.7%と、1ポイント以上上回っていた。
総資本に対する利益率=ROAについても、非同族企業が1.0%に対し1.6%、株主資本に対する利益率=ROEは非同族企業の0.2%に対して1.9%と、いずれも圧倒している。
こうした傾向は欧米でも同じらしい。
カナダのアルバータ大学の研究所ダニー・ミラー、イザベル・ル・ブレトン=ミラー氏らの研究では、1990年代初頭のアメリカの公開企業の上位800社のうち、同族企業は利益率で33%、成長率で15%、業界平均より上回るというデータが載っている。
もちろん何をもって同族企業というのか、という問題はある。長年同族企業について研究してきた日本経済大学の後藤俊夫教授によれば「定義はいろいろだが、創業者一族(三親等以内)の影響下にある企業」という。
では影響とは何か。「発行株式における一族の比率とか役員比率など」(後藤教授)らしい。
問題はなぜ同族企業は強いのかということだ。
最大の強みは、社員が「誰の派閥についたら出世が早いか」といった権力闘争コストが小さく、長期視点に立った経営に専念できるからだ。
一見するとトップまで競争原理を働かせる非同族企業のほうが、民主的で効率的だと思われる。しかしながら過剰なまでの出世競争は、企業に無駄なエネルギーやコストを発生させ、意思決定も遅れがちだ。
「民主的」で「合理的」な判断をする非同族のDX化が進まないのはなぜか
資本力のある非同族の大企業がDX化を進めて、業務の効率化を図ったとしても、肝心のお客様へのサービスが悪化したりして、客が離れることも多い。たとえば銀行である。そもそもコンピュータ化をいちはやく実現して、全国にATMを普及させた都市銀行でトラブルが続出したりするのはなぜか――。
効率化を進めて合併したが、銀行同士の基幹システムが違っているため、刷新ができず、旧来のシステムを活かしながら業務を進めてきたからだ。
金融機関のセオリーとして、異なる基幹システムを持つ金融機関が統合する場合は、原則的にシステムの遅れているほうに合わせることになる。
その結果、その調整のためにまたコストと時間と人が要るという負のスパイラルを起こすことになる。
より進んでいて利便性の高いシステムを採用すればいいはずなのだが、できない。要はかかわる利害関係者が多いから、その利害関係者の顔を立てるからできないのだ。そういった忖度も大企業では「総合的合理的」判断となる。
ついでに言っておくとそもそも日本のDXは欧米のように簡単には進まない。
なぜか?
言語が日本語だからだ。
欧米に限らず、いま大概の国の言葉はアルファベットの組み合わせでできている。つまり26文字+アルファの組み合わせで、プログラムやプロンプト既述がかける。

だが日本語はひらがな、カタカナ、漢字など一通り使う上、漢字の場合は同じ漢字でも意味や読みが違ってくる。別にプログラムは英語でかけばいいじゃん!という声もあるが、例えば、製品のカテゴリやジャンルを整理する場合、古い企業であれば、甲乙丙、といった文字を使うこともある。
さらに商品群を表す記号に◯をつけたりする。
昨今は別にプログラム言語を知らなくても「ノーコード」でつくれるプログラムが生まれているが、管理対象となる製品や商品、部品、部材の表現やルールが時代とともに変わっていたり、合併・統合によって複数の企業の商品やルールが混在するといかに優れたコンピュータシステムを導入しても、活かしきれない。
神奈川県に本社がある数百億円規模のグローバル部品メーカーでは、DX導入を図ろうとずっと後回しにしてきた基幹システムに手をつけることになった。
後回しにしてきた理由は枝番を含めると100万種になんなんとする製品の整合だった。大手ベンダーのシステムを使うと、1つのカテゴリの登録商品数に限界があり、そのままは使えず、自分たちでカスタマイズする必要があった。
こうした部品や部材提供の場合は、その管理方法は得意先に合わせる場合も多い。顧客の製品が改定された場合、その改定された管理方法も引き継ぐことになる。
一方で同じ仕様の部品を自社ブランド、別の企業の部品として提供する場合もある。その場合、素材や機能を少し変えることもある。また昨今はトレーサビリティの観点から、以前は使用できた原料や素材が突然使えなくなることもある。
基幹システムを変更することは、こうした細かい差異を含めて一元管理のフォーマットで使用できるように商品群のラベルを新たなルールに準じてすべて貼り替えることを意味する。もちろんこうした作業は大企業だろうが、中小企業だろうが発生する。
問題は誰がやってもやっかいなこと、下手すれば、顧客への商品やサービス提供が停止し、業績に悪影響を与える可能性のあるやっかいな作業をいつ誰にやってもらうかである。ワタシがもし、大手企業の雇われ社長だったらぜひ後回しにしたい案件だ。任期中に評価を下げたくないからだ。
無論、同族企業だからできるというつもりもない。ただ派閥抗争や過剰競争にエネルギーを使う民主的で合理的な判断をするとされる大企業や中堅企業よりは、思い切りよく進められる可能性は高い。
一周回ってもとに戻った昨今の「サステナブル経営」
日本はバブル崩壊後の失われた30年の間に「株主・株価重視」「時価総額経営」にシフトし、短期で利益を上げる経営スタンスをとるようになったが、その構造が充分追いついていなかった。
それが昨今のサステナブルブームで、長期視点の経営が叫ばれるようになった。かつて日本の経営では、短期と言えば1年、中期が5年、長期が10年を指した。それが近年は短期が四半期、中期が1年、長期が2~4年が当たり前になり、そして再び、10年、30年スパンが語られるようになった。
一周回ってもとに戻った感じがするのはワタシだけではないだろう。
後藤教授が調査した同族企業からは、「短期10年、中期30年、長期100年という話がよく聞かれた」という。同族企業はBorn to be sustainableなのである。
当然こうした経営の立脚点は日本でも欧米でも同じだ。
あのエルメスでは、こう繰り返すという。
「われわれは過去の遺産を引き継いだからここにいるのではない。未来のものを預かっているのだ」「未来からの預かり物に対して、ここで我々がいい加減なことはできない」と。
後藤教授の定義に従えば日本の企業の95%は同族企業である。つまり日本の企業はその本来の経営の強みを活かせばグローバル市場において、かなり優位に立てるはずなのだ。日本の経営者はもっと自信をもっていい。
イマドキのビジネスはだいたいそんな感じだ。