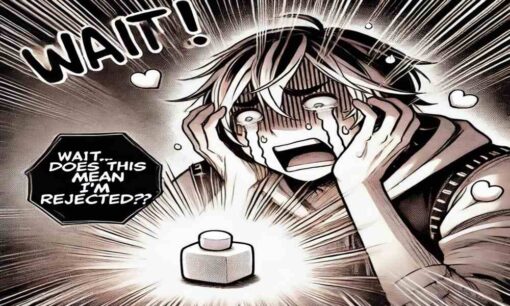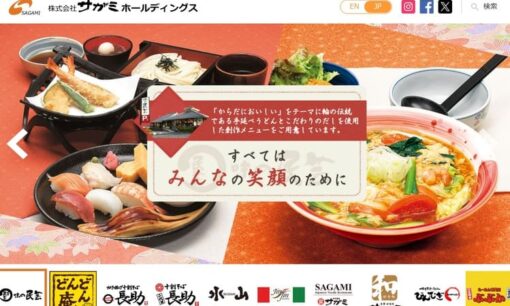OpenAI、非営利の統制を維持 批判と圧力が後押しに
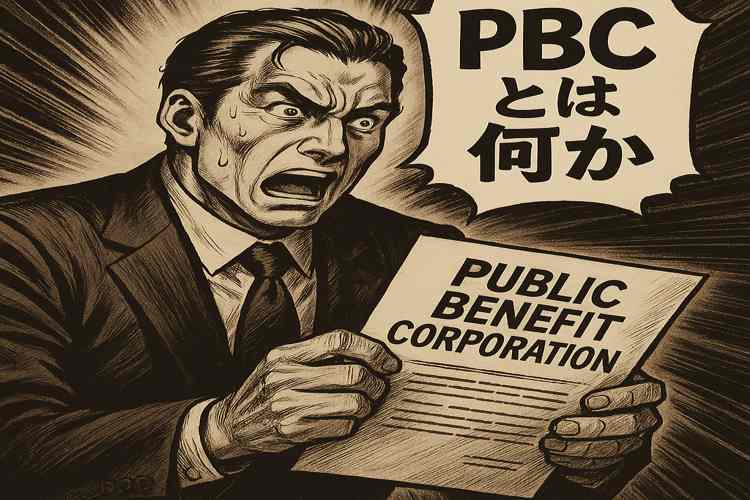
米OpenAIは5月5日、これまで検討されていた営利企業主導の経営再編を撤回し、非営利組織が主導する体制を維持する方針を明らかにした。営利子会社であるOpenAI LLCは、米国デラウェア州の法律に基づく「パブリック・ベネフィット・コーポレーション(PBC)」へと再編されるが、その監督権限は引き続き非営利法人に残る。
この再編の背景には、共同創業者であるイーロン・マスク氏をはじめとする関係者からの激しい批判と、カリフォルニア州やデラウェア州の司法当局への申し立てがある。AIの急速な発展において、「株主の利益が安全性や透明性より優先されるのではないか」という懸念が広がっていた。
アルトマンCEOは従業員宛ての書簡で「OpenAIはこれからも普通の会社にはならない」と述べ、営利一辺倒の姿勢ではなく、ミッション重視の姿勢を改めて打ち出した。
PBCとは何か?歴史と制度の仕組み
PBC(Public Benefit Corporation)は、2010年に米国デラウェア州で初めて導入された法人格で、通常の営利企業とは異なり、定款に記された「公共の利益」を追求することが法的に義務付けられている。これは株主利益だけを重視する株式会社の限界を補い、企業が社会的責任を果たしつつ事業を推進することを可能にする“ハイブリッド型企業”として注目されてきた。
経営陣は、事業の意思決定において株主だけでなく、従業員、顧客、社会全体への影響を考慮する法的責任を負う。そのため、環境、倫理、人権、安全性などの要素が経営判断に組み込まれやすい仕組みといえる。
レモネードの事例が示す「PBC=非上場」の誤解
今回の再編をめぐりSNS上では、「OpenAIは収益化を諦めたのか」「上場の可能性はなくなったのか」といった声も上がった。しかし、PBC形態でも収益の確保や株式上場は可能であり、実際にその成功例も存在する。
米国の保険テック企業「レモネード(Lemonade, Inc.)」は、2020年にNASDAQに上場を果たしたPBC企業である。同社は、「利益よりもミッション」を掲げつつ、収益を一部チャリティに還元する仕組みや、透明性の高い保険料運用などを通じて投資家と社会的意義の両立を図っている。OpenAIも同様に、公益性と持続可能な収益基盤の両立を模索する方向とみられる。
日本にPBCはないのか?政策の動きと可能性
現時点で日本にはPBCに相当する法的法人格は存在しない。ただし、公益社団法人や公益財団法人、あるいは認定NPO法人が類似した立ち位置にあり、一部の株式会社では「B Corp™」と呼ばれる民間認証を取得する企業も出てきている。
政府内でも関心は高まっており、内閣府や経産省は「PBC的な法人格」の創設に関する調査研究を重ねている。実現には会社法改正などの法制度整備が必要だが、OpenAIの事例が法制化への後押しとなる可能性は十分にある。
ユーザーへの恩恵と残された課題
PBC再編により、OpenAIは価格設定や機能開発において急激な営利寄りの方針転換が起きにくくなる。教育機関や行政機関による導入のハードルも下がり、ユーザーにとっては透明性や安全性の強化、無料枠の継続といったメリットが期待される。
一方で、「公益とは何か」という判断軸が米国本社に依存する点、さらには日本リージョンのデータセンター不在といった技術的・制度的な課題は残る。また、米国の輸出規制や政権交代の影響によって、海外への最新モデル提供に遅れが出る可能性も否定できない。
OpenAIが今回選択したPBCという形態は、単なる制度変更ではなく、AI企業のガバナンスと社会的責任のあり方を巡る深い問いかけである。今後、この動きが業界全体に波及するのか、注視が必要だ。
日本でも広がるB CORP取得企業など関連記事はこちら