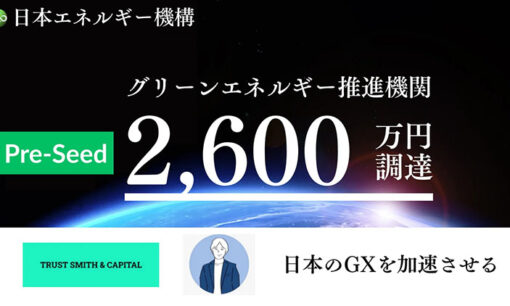東山動植物園のコアラが食べ残したユーカリを紙糸に再生し、Tシャツとして循環させる試みが動き出した。資源循環と動物福祉を両立させる名古屋発のプロジェクトが、地域と企業を巻き込みながら新たな支援の形を提示している。
コアラの未利用ユーカリを紙糸化 東山動植物園×アップサイクルが循環型Tシャツを制作
一般社団法人アップサイクルは、名古屋市が管理運営する東山動植物園のコアラが食べ残したユーカリを原料の一部に用いた「ユーカリTシャツ」を制作した。12月1日に開始する名古屋市のふるさと納税型クラウドファンディングの返礼品として提供され、寄付金はコアラの飼育環境整備やユーカリの森の保護に充てられる。
東山動植物園では9頭のコアラを飼育しているが、新芽を好む特性から栽培したユーカリの多くが食べ残されてきた。未利用資源として処理されてきた枝葉を、「TSUMUGI」の紙糸技術によって循環資源に転換したことで、都市動物園ならではの新たな資源循環モデルが生まれた。
クラウドファンディングの目標額は1,500万円。募集は2025年12月1日から2026年2月28日までの90日間となる。
動物福祉と資源循環を融合 動物園由来バイオマスを繊維へ再生する希少なモデル

ユーカリTシャツの特徴は、動物園で発生する未利用バイオマスを、衣料用途へ再資源化した点にある。紙糸の主原料である使用済み紙や間伐材に加え、今回はコアラの食べ残しユーカリを一部使用することで、動物福祉と地域資源循環の接点をつくった。
“人間の廃材”からの循環は一般化してきた一方、動物園由来の素材を生活者に返す事例は少ない。動物が日々の暮らしの中で生み出す未利用資源を、地域コミュニティの手で循環させる取り組みは、都市型動物園が抱える資源課題を可視化する役割も担う。
Tシャツのデザインは、東山動植物園に暮らす9頭のコアラそれぞれの個性を反映させたグラフィック。日常使いできる落ち着いた風合いで、いわゆる“記念グッズ”に留まらない確かな完成度を持つ。
都市の動物園と森をつなぐ試み “いのちを支える資源”を地域で循環させる思想
今回のプロジェクトの背景には、「動物の暮らしを支える資源の循環を市民と共につくる」という思想がある。
東山動植物園のコアラ飼育は、市内でのユーカリ栽培と不可分だが、コアラは新芽のみを好むため多くの枝葉が未利用のまま残ってきた。自治体がその現実を隠さず捉え、資源循環の視点で新たな価値に転換した点に特徴がある。
アップサイクル団体の紙糸技術と、市民参加型の寄付制度を組み合わせることで、「いのちの循環」を生活者が理解し、手触りとして感じられる仕組みが生まれた。動物園の存在意義を“展示”から“地域との共創”へと拡張する試みでもある。
サステナビリティを生活者へ接続する技術と設計力 市民参加型の循環を可視化
今回の取り組みが示すのは、企業や団体が持つ技術を、社会課題・動物福祉・地域経済と結びつける「循環の設計能力」である。
紙糸「TSUMUGI」は単なる素材開発にとどまらず、回収拠点づくり、啓発、製品化、市民参加を通じ、循環の輪を広げてきた。ユーカリTシャツはその延長線に位置づけられ、Tシャツを手に取る行為そのものがコアラの暮らしを支える構造をつくった。
サステナビリティが専門家の領域に閉じず、生活者の意思選択と地続きであることを示すモデルとして、他自治体や動物園への展開余地も大きい。クラウドファンディングの反響は、都市型動物園と地域社会の新しい関係性を測る試金石となる。