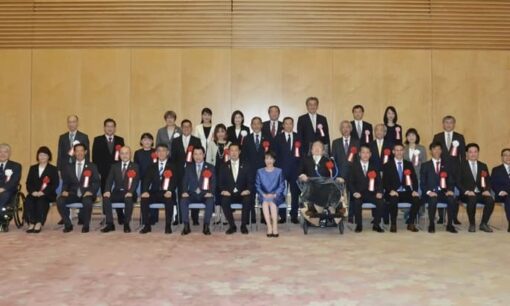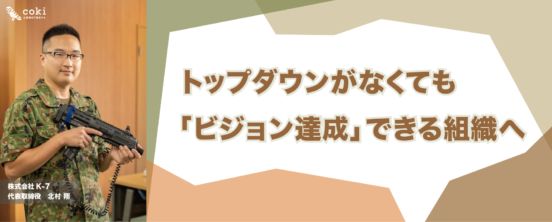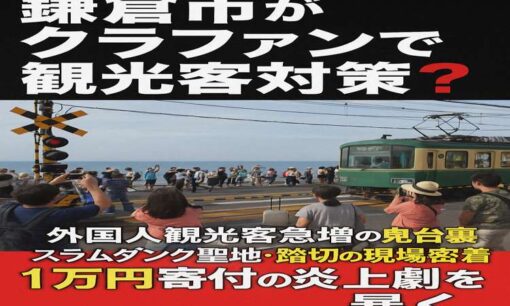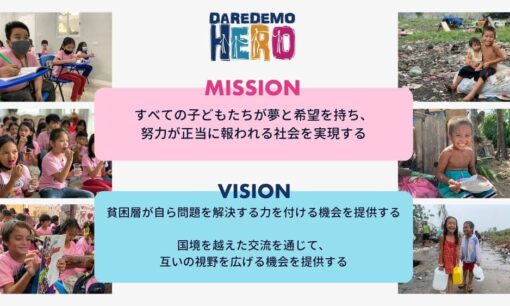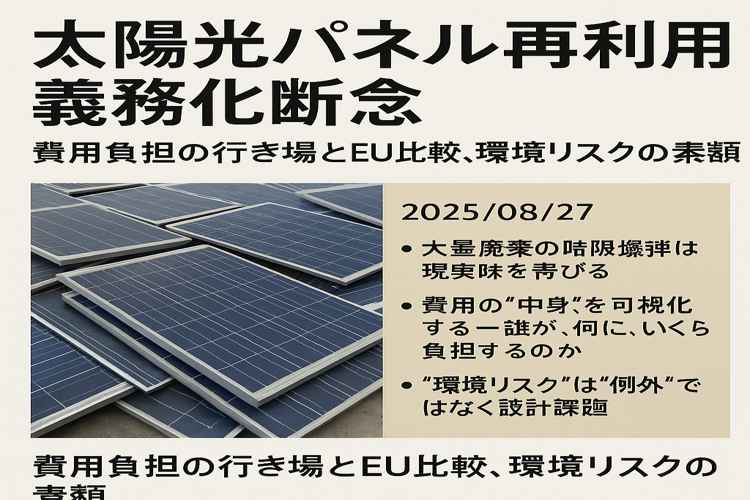
政府は、使用済み太陽光パネルのリサイクル義務化を見送る方針を固めた。2030年代後半以降、大量のパネルが寿命を迎えて廃棄される見通しがあるため法制化を検討してきたが、費用を誰が負担するかで調整がつかず制度設計が難航した。関係者が27日明らかにした。
義務化の断念は、最終処分場の逼迫や不法投棄の増加につながりかねない。政府は代わりに、大規模発電事業者にリサイクル実施状況の報告を義務付ける仕組みを検討し、来年の通常国会で関連法案提出を目指す。だが「報告」だけで実際のリサイクルがどこまで進むかは不透明だ。
廃棄の山、30年代後半から一気に
太陽光パネルの寿命は20〜30年程度とされる。環境省の推計では、廃棄量は30年代後半に急増し、40年代前半には年間で最大50万トンに達すると見込まれる。2010年代に普及した設備が一斉に寿命を迎えるからだ。現場からは「処理施設のキャパシティを超えれば自治体の負担に直結する」と危機感が出ている。
費用の正体 1枚あたり数千円〜数万円
議論の焦点は「処理費用」を誰が払うかだ。経済産業省の調査では、事業用パネルの撤去から運搬、整地、処分までを含めると、1キロワットあたりおよそ1.06〜1.37万円がかかるとされる。このうち、ガラスや金属を分別する処理自体は約0.21万円/kWにとどまるが、解体や撤去などの現場作業がコストの大部分を占める。
実際の民間見積もりでは、設置状況によって1枚あたり1万円前後から数万円に膨らむケースもある。発電事業者が払うのか、メーカーや輸入業者に義務を課すのか、それとも電気料金に上乗せして国民が広く負担するのか——答えが出せなかったことが義務化断念の背景だ。
政府は一部の事業者に「外部積立制度」を導入し、売電収入の一部を将来の廃棄に備えて積み立てさせている。しかし制度の対象外も多く、抜け道が残る。
EUは“前払い方式”、韓国も追随
海外では「メーカーが最後まで責任を持つ」制度が整っている。EUは2012年のWEEE指令で太陽光パネルを対象に加え、製造・輸入業者に回収とリサイクルを義務付けた。ドイツでは、メーカーが登録して回収義務を果たす仕組みを法で整備済みだ。
フランスはさらに進んでいる。政府認可の団体「Soren」が、新しいパネルを売るときに上乗せされる前払い金(エコ拠出金)を集めて資金を確保し、そのお金で廃棄時の回収と処理を行う。所有者に追加の費用はかからない仕組みで、長期的な費用回収リスクを避けている。
韓国も同様に「拡大生産者責任制度」を導入し、メーカーにリサイクルの責任を課している。国際的には「売った責任を最後まで持つ」ルールが当たり前になりつつある中で、日本の立ち遅れが際立つ。
環境リスク、見過ごせない有害物質
太陽光パネルは環境にやさしいエネルギーの象徴とされるが、廃棄時には別のリスクが浮上する。主流の結晶シリコン型でもはんだに含まれる鉛が問題視されるほか、薄膜型ではカドミウムといった有害物質が使われることもある。
適切に処理されなければ、破損や粉砕の過程で有害成分が漏れ出し、地下水や土壌を汚染する恐れがある。環境省は、こうしたパネルを「有害物質が外に漏れないよう管理された特別な処分場」で扱うよう指導しているが、不法投棄が増えれば管理が行き届かない危険性も高まる。
先送りは許されない
政府は「報告義務制度」で一定の透明性を確保しようとしているが、義務化を断念したことで「誰が最終的に責任を負うのか」は依然として曖昧だ。専門家は「海外のように前払いで資金を確保する仕組みを導入しないと、結局は自治体や納税者が尻ぬぐいをすることになる」と警鐘を鳴らす。
2050年カーボンニュートラルを目指す日本にとって、再生可能エネルギーの拡大と廃棄物対策は表裏一体だ。廃棄パネル問題の解決なくして「グリーン成長」の旗は掲げ続けられない。