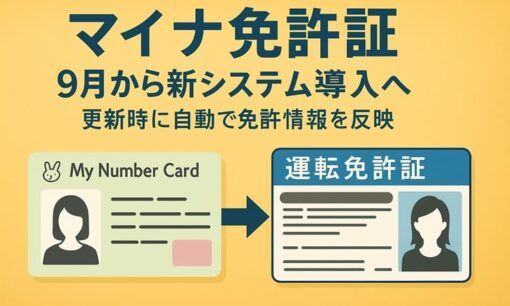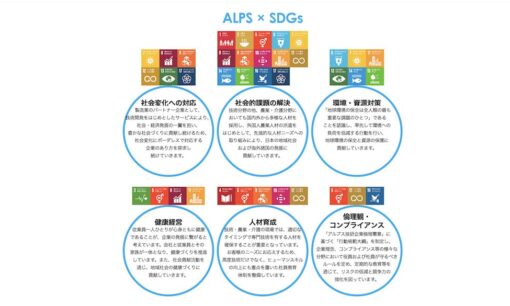地方から都市へ 若年層の移動に潜む構造的問題

内閣府が2025年6月に公表した「令和7年版 男女共同参画白書」では、少子高齢化と人口減少が加速する中で、地域の活力を維持・向上するためには、若者とりわけ女性の定着が極めて重要であることが改めて浮き彫りとなった。
白書によれば、進学や就職、結婚などを機に地方から都市へ移動する若者の流れは依然として強く、特に女性については一度都市に出ると地元に戻らない傾向が顕著だという。
背景には、希望する進学先や就職先が少ないことに加え、地元に対する閉鎖的な人間関係や干渉から距離を取りたいという心理がある。調査では、女性の方が「親や周囲の人の干渉から逃れたかった」と回答する割合が高かった。
愛着と現実のギャップ 「戻りたい」が叶わない構造
また、東京圏に移住した地方出身の若者を対象にした調査では、現住地域よりも出身地域への愛着が高いという結果が出ている。特に女性の場合、その傾向が強く、6割以上が出身地域に「愛着がある」と回答している一方で、実際に戻ることにはためらいもある。
その主な理由としては、「収入や生活費への不安」「希望する仕事に就けるか」といった経済面や就労面の問題に加えて、「買い物や公共交通機関の利便性」など生活インフラへの不安も挙げられている。
家事・育児に偏る負担 数字に見るジェンダー格差
特に地方に根強く残る「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識も問題視されている。
例えば、6歳未満の子どもを持つ家庭では、全国すべての都道府県において妻の家事時間が夫よりも210分以上長く、逆に夫の仕事時間は妻よりも180分以上長いという結果が示されており、ジェンダー役割の分担が依然として明確に残っている 。
女性参画の遅れ 政治と地域の意思決定の場で
また、政治分野への女性の参画状況も依然として低水準にとどまっている。都道府県知事に占める女性はわずか4.3%(47人中2人)、市区町村長では3.7%(1740人中64人)に過ぎない。地方議会における女性議員比率も東京都を除けば多くの自治体で1~2割程度にとどまっており、意思決定の場への女性の進出は依然として途上段階にある 。
白書が提示する地域再設計のヒント
こうした背景を踏まえ、白書は、地域の男女共同参画を進めることが地域全体の活力向上、さらには日本社会のウェルビーイング向上につながると強調する。その上で、性別に関係なく個性と能力を発揮できる環境の整備が急務だとしている。
たとえば、女性の起業を後押しする仕組みづくりや、家庭と仕事を両立しやすい柔軟な働き方の普及、女性管理職や女性議員の増加、さらには地域の大学や教育機関を通じたキャリア教育など、さまざまな手段で地域の魅力を高めることが提言されている。また、地域活動に女性の意見を取り入れること、防災や復興の視点にもジェンダー配慮を織り込むことなどが具体的な施策として掲げられている 。
両立願望が多数派に 変わる若者のライフ観
白書後半では、働き方に関する意識の変化にも触れられている。かつて多かった「専業主婦コース」を理想とする未婚女性は、2021年時点では13.8%まで減少し、「結婚して子どもを持ちながら仕事も続ける(両立コース)」を希望する割合が最も高くなっている。未婚男性の理想とするパートナー像でも同様に「両立コース」が主流であり、男女ともに価値観の変化が進んでいることがうかがえる 。
地方創生は「ジェンダーの解放」から
このように、「令和7年版 男女共同参画白書」は、単なるジェンダー施策の報告にとどまらず、地域の未来と社会の構造的課題を鋭く照らし出す内容となっている。地域の持続可能な成長を目指すならば、女性が住みやすく、働きやすく、戻りたくなるような社会の再設計が不可欠である。