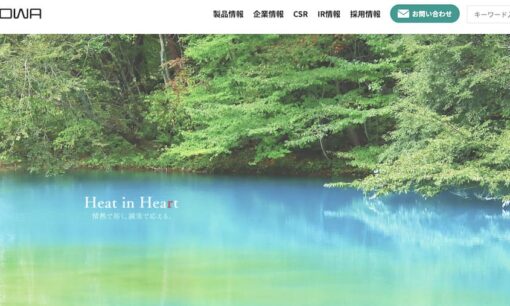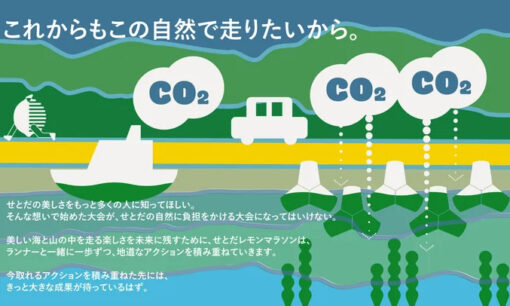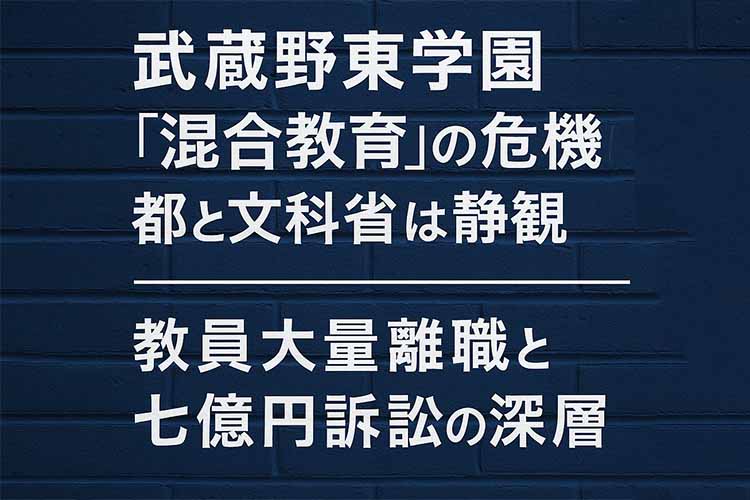
自閉症児と健常児が共に学ぶ「混合教育(インクルーシブ教育)」で国内外から注目を集めてきた武蔵野東学園(東京都)。近年、その“唯一無二”とも呼ばれた教育現場に異変が生じている。週刊文春の連載によれば、今年度末までに全教員の半数近い30名以上が退職したという。
さらに、自閉症児たちの卒業後の生活支援を担ってきた教育センター「友愛寮」についても、2024年10月1日に閉寮という事態が既に現実化しており、長年にわたり学園を支えてきた機能が失われつつあるという。
寺田欣司前理事長の招請でHazuki会長・松村氏が理事に就任、異例の早さで理事長に
こうした急激な変化の背景には、前任の理事長・寺田欣司氏の決断と、その後任として選ばれたHazuki Company(ハズキルーペ)会長として知られる松村謙三氏(プリヴェ企業再生グループ 代表取締役会長)の台頭が密接に関係している。
松村氏は当初、理事の一人として学園に加わったが、就任2年目には異例の早さで副理事長に昇格。その後、他の理事の退任が相次ぎ、学園の意思決定層は大きく入れ替わることとなった。退任が自発的なものだったのか、意図的な刷新だったのかは定かでないが、気がつけば理事会の中枢には松村氏を理事長とし、その家族や関連企業の関係者が多くを占める布陣となっていたと、元学園関係者は語る。
昨年2月、正式に理事長となった松村氏は、以後、急ピッチで改革と人事再編を進めているが、現場からは「説明が不十分で、性急すぎる」との批判も少なくない。防犯カメラの大量設置、学園に異議を唱えた教員の賞与減額、一部教員の不透明な異動などが『週刊文春』で報じられ、保護者の間にも「このままで子どもたちの教育は守られるのか」と不安が広がっている。
児童の親が見た“混合教育”の価値
そもそも、武蔵野東学園は、自閉症児と健常児が一緒の教室で学ぶ「混合教育(インクルーシブ教育)」の先駆けとして知られてきた。幼稚園から小・中学校、高等専修学校まで、一貫して「障がいの有無を超えて育て合う」カリキュラムを積み上げてきたことで、多くの保護者・専門家から高い評価を得ている。
ある学園卒業生は「健常児にとっても、自閉症児とふれ合いながら育つことで、違いを自然に受け止める心や優しさが育つ」と述べる。また、自閉症児を持つ別の親は「個別の特性に合わせ、専門知識を持つ先生が寄り添ってくれるのは本当に助かる。普通の学校では見過ごされる課題も、ここではきちんと対応してもらえた」と語る。
このような相互理解・相互成長が起きやすい環境が整備されていたからこそ、“日本一の混合教育”との呼び声が高かった武蔵野東学園。子どもの将来を案じる親たちは高額な学費を工面し、地方から引っ越してでも通わせる例が少なくなかったという。
友愛寮の閉寮 卒業後の就労支援機能も失われる
ところが、こうした学園の付帯施設であり、卒業後の生活や就労を支援していた「友愛寮」が、2024年10月1日に閉寮となってしまっている。「友愛寮」では、自閉症を含む障がいのある人たちが安心して働ける職場を探したり、社会適応を学べる環境が提供されていたため、保護者からの評価は非常に高かった。卒業した後も学園とつながりを持ち、必要なときに生活指導を受けられる“セーフティネット”として機能していたのだ。
しかし、学園側は「経営上の理由」や「今後の方針」などを理由に施設の閉鎖を決定。「赤字経営から脱却するために仕方ない」という声がある一方、「あれほど重要な機能を、赤字だからといって簡単になくしていいのか。障がいのある子どもの将来を丸ごと見てくれると信頼していたのに」と憤る保護者は少なくない。
ある父親は「“卒業後も面倒を見てくれる学園”という安心感が武蔵野東の大きな魅力だった。友愛寮の閉寮は、子どもが大人になるときの不安要素を増やすばかりだ」と語る。こうした声はすでに現役保護者だけでなく、これから入学を検討していた家庭にも伝わり、学園を取り巻く評判をさらに悪化させているようだ。
大量離職が止まらない 児童の親たちの不安
メディアが報じたところによると、運営側でも問題が起きているのだろう、ここにきて30名以上の教員が辞めるという話がでているようだ。経験豊富な専科教員の離職も相次ぎ、やむを得ず担任が音楽や理科、体育などを兼務するケースが増えることが予想される。
ある母親は「小学校の高学年になれば学習内容は高度になるし、中学校へ向けての準備も必要なのに、教員が突然入れ替わるのではとても不安」と心境を吐露。別の保護者は「『教員を辞めさせたくないので静かにしてほしい』という空気があり、私立のため反論もしづらい。理事長の児童のいる学年のみ優遇されているように見え、学年間でも対立しているようだ」と打ち明ける。
学園が持つ“混合教育”のノウハウは、長年の実績と専門家の研究成果が結びついた貴重な資産だ。しかし、ベテラン教員が退職すれば、そのノウハウが散逸しかねない。さらに、積極的に意見を述べてきた教員に対する処遇が「不透明」「不当」との噂が広まる中、校内には「異論を唱えづらい」萎縮ムードが漂っているという。
前任理事長・寺田氏への疑問 OB保護者の疑問
学園の混乱を受けて、かつて児童を通わせた親の中には「寺田欣司・前理事長は、なぜ安易に松村氏に託してしまったのか」と悔やむ声もある。「経営が苦しいのは分かるが、何より大切にすべきは武蔵野東が積み上げてきた教育理念ではなかったか」「もし理事長を交代するならば、慎重に人選をして適切なガバナンス体制を敷くべきだったのに、結果として急進的な改革ばかりが先行してしまった」といった批判が少なからず聞かれる。
あるOB保護者は「赤字だからといって、なにも卒業後の行き場を支える施設(友愛寮)まで潰してしまう必要があったのか。寺田前理事長も、そうした事態になるとは想定していなかったのではないか。知っていたとしたら酷い」と憤りを露わにした。さらに「創設者の理念を守るどころか、逆方向に向かっているように思える。学園の全権を預けてしまったのは何故なのか」と、寺田氏への失望を口にする者もいる。
現場と経営の“落としどころ” 穏健な着地が急務では?
一方で、学園が抱える赤字を克服するには何らかの改革が必要だと認める保護者も少なくない。経営者としての松村理事長が「持ち前のノウハウを生かし、財政を立て直したい」と考えること自体は当たり前の話だろう。
問題は、その進め方だと多くの声は指摘する。強引な施策によって大量離職が起きれば、混合教育の屋台骨は崩れ、子どもたちが将来にわたって得られるはずだった学びや支援が大きく損なわれる。ある保護者は「改革自体が悪いとは言わないが、子どもたちや現場の意見を丁寧に聞き、きちんと合意形成を図りながら進めてほしい」と訴える。
「友愛寮の閉寮が既定路線なのであれば、代替の支援策を十分に用意すべきだったのではないのか」「ベテラン教員が何を問題視しているのかをもっとくみ取ってくれないのか」
こうした要望は現役・OB問わず多い。特に障がい児の保護者の中には「子どもが変化を嫌う特性を理解しているなら、急激な改革は心理的負担が大きすぎる」と懸念を強める声もある。
創設者・北原キヨ先生がいまを見たらなんと言うのか
武蔵野東学園の創設者である北原キヨ先生は、生徒や保護者の間で「熱意と優しさの人」として語り継がれてきたという。自閉症児の可能性を信じ、社会全体で子どもをはぐくむ場を作りたい。その理念がきっかけとなり、幼稚園から中学・高等専修学校、さらには就労支援施設に至るまでの総合学園が築かれた。
しかし、現状では自閉症児と健常児が共に学ぶ貴重な環境が崩れかけ、卒業後のセーフティネットである「友愛寮」も閉寮が決定済み。多くの専門性ある教員が離職し、保護者は未来への不安を抱え込んでいる。ある母親は「もし北原先生がいまの姿を見たら、『こんなはずじゃなかった』と泣いてしまうのではないか」と声を詰まらせた。
赤字解消を焦るあまり、“唯一無二”とされた混合教育の根幹を壊してしまえば、学園の損失のみならず、日本社会全体が大切なモデルケースを失うことになる。いま必要とされているのは、創設者の理念にもう一度立ち返り、保護者・教員・理事長が対話を重ねながら穏健に改革を進める姿勢だろう。そうした合意形成を欠けば、武蔵野東学園が築いてきたかけがえのない教育文化は遠からず瓦解しかねない。
7億円もの訴訟。特別支援の公共性は?
実際に現場で困窮している児童や家庭は存在しており、5月現在も速やかな支援を求める声が強まっている。大きく関係しているのは、4月に学園側が行った合計7億2572万円もの訴訟のようだ。この損害賠償請求は武蔵野東学園を守る会のメンバーや理事長と対立していた卒業生とその親、週刊文春記者らを対象としたもの。学園のコーポレートサイトには卒業生児童の名前まで開示されている。この高額な訴訟がそこまでするかという驚きをもって、学園内外に動揺が広がっている。
特に保護者の間では、「まさか学園が子どもや保護者にまで訴訟を起こすとは思わなかった」と驚きと困惑の声が相次いでいる。「批判しただけで訴えられるようでは何も言えなくなる」との声も多く、提訴の妥当性そのものを疑問視する声も多い。かつては信頼を寄せていた学園が、強硬な法的対応に踏み切ったことへの不安と落胆は根強く、学園との関係性を見直す保護者も出始めているという。
学園側には学園側としての事情もあるのだろうが、こうした不安が蔓延する状況が長期化すれば、子どもたちの教育機会そのものが脅かされかねないのではないか。もはや問題は一法人の経営判断にとどまらず、教育行政の責任のあり方にも及んでいるだろう。
行政の関与はなぜないのか?
武蔵野東学園が担ってきた「混合教育」は、特別支援と通常教育を融合させた社会的に重要なモデルであり、長年にわたって国や東京都から助成金も支給されてきた。
そうした背景を踏まえるなら、同学園は単なる私立学校ではなく、公共的役割を担う教育機関と見るべきだろう。助成金という公的資金が投じられている以上、文部科学省や都の関係部局には、教育環境の維持と透明性確保に向けた一定の関与と責任が求められていることは間違いない。
実際、同学園が卒業生らに対して7億円を超える損害賠償請求を行った件について、国会では文部科学省の阿部俊子大臣が「教育上適切な対応をお願いしたい」と言及した一方で、「学園に対する直接の指導は東京都の所管」として静観の姿勢を示した。
東京都側も「民事訴訟のみをもって指導するのは難しい」と述べており、国と都が互いに責任の所在を曖昧にしたまま及び腰でいる構図が浮かび上がっている。しかし、こんな情けない行政の姿勢で何が教育だと言いたい。
制度としての私学の自主性を尊重しつつも、特別支援教育という代替のきかない、公共性の高い分野においては、監督体制の強化や法的枠組みの見直しも視野に入れるべき時期なのではないか。いま行政がどう動くかは、社会全体が「誰ひとり取り残さない教育」を本気で守れるかどうかの試金石でもある。


株式会社Sacco 代表取締役。一般社団法人100年経営研究機構参与。一般社団法人SHOEHORN理事。
連載:日経MJ・日本経済新聞電子版『老舗リブランディング』、週刊エコノミスト 『SDGs最前線』、日本経済新聞電子版『長寿企業の研究』