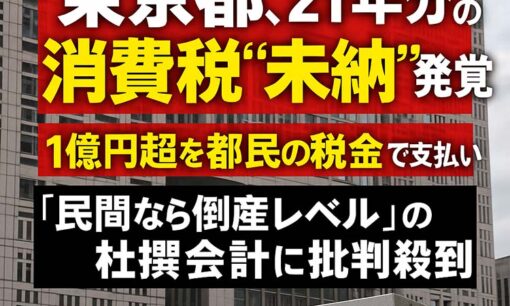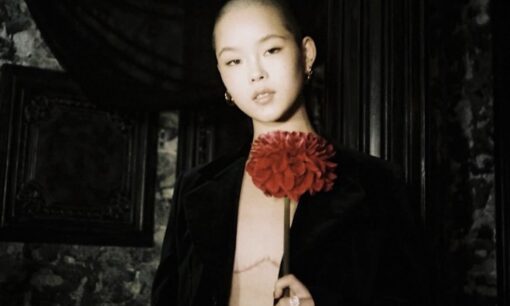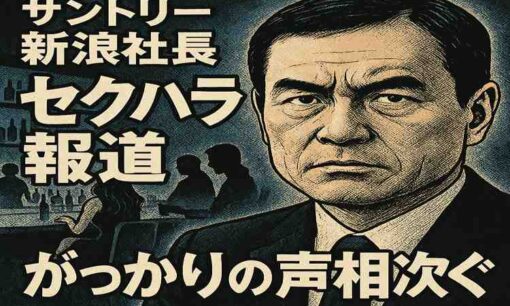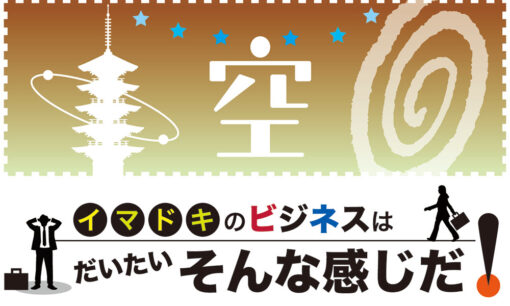大分県佐伯市で、海にまつわる民話を題材としたアニメーション「佐伯の船霊さま」の上映会とフィールドワークが開催された。これは、一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」の一環として、2月12日に佐伯市立蒲江翔南学園で実施された。
民話を通じて学ぶ海の文化
上映会では、「佐伯の船霊さま」の語り手である橋本正恵氏(有限会社丸二水産)が登壇し、漁師町ならではの遊び道具として「タカラガイ」を紹介。子どもたちは興味津々に手に取り、触れることで昔ながらの文化に親しんだ。上映後には、児童たちが積極的に感想を述べ、「漁師さんが働き者であることがよくわかった」といった声が寄せられた。
また、物語に登場する「バクチの木」について、橋本氏は「願掛けをする御神木のような存在であり、地域のシンボルとして大切にされている」と説明。さらに、海ノ民話のまち実行委員会の古田浅男氏は「この物語は漁師たちの生きる知恵を伝えるものであり、佐伯市蒲江に生まれたことを誇りに思ってほしい」と語った。
フィールドワークで深まる理解
上映後には、フィールドワークが実施され、佐伯市教育委員会社会教育課の清家隆仁氏が「船霊信仰」の背景について講義を行った。船霊信仰は、新しい船を造る際に大漁祈願や航海の安全を願って始まったもので、かつては船の操舵室に「船霊さま」を祀っていた。しかし、造船技術の進化により木製の船が強化プラスチック製へと変わり、またGPSの導入によって遭難が減ったことで、次第に信仰は薄れていったという。
さらに、佐伯市蒲江には、海産資源を求める一族や漁の技術を伝える一族、戦乱を逃れた一族などが移住してきた歴史があることも紹介された。清家氏はまた、干支を用いた方角や時間の表し方について説明し、「とり舵(左舷)」の語源が西を表す「酉(とり)」に由来することを解説。児童たちは普段聞き慣れない航海用語に熱心に耳を傾けていた。
参加者の声
参加した児童たちからは、「船の中に船霊さまがいることや、バクチの木があることを初めて知った」(小学4年生女子)、「民話に興味がなかったが、アニメを観て興味がわいた。家で調べてみたい」(小学6年生男子)といった声が上がった。
また、「ごみを捨てずに蒲江の海を守っていこうと思った」(小学2年生男子)、「佐伯にこんな民話があるなんて驚いた。帰って母に話したい」(小学5年生女子)など、民話を通じて地域の文化や環境への関心を深めるきっかけとなった。
イベント概要
今回のイベントは、一般社団法人日本昔ばなし協会が主催し、日本財団の「海と日本プロジェクト」と共催で実施された。開催日は2025年2月12日で、会場となったのは佐伯市立蒲江翔南学園だった。参加者は、同学園に通う小学生約140名で、授業の一環として上映会とフィールドワークが行われた。
上映会では、まず「海ノ民話のまちプロジェクト」についての概要説明がなされた後、「佐伯の船霊さま」のアニメ上映が行われ、続いて佐伯市の漁業や民話に関連した解説が行われた。講師として登壇したのは、海ノ民話のまち実行委員会の橋本正恵氏(有限会社丸二水産)、古田浅男氏、首藤弘治氏の3名だった。
その後のフィールドワークでは、佐伯市の海と漁師文化について、佐伯市教育委員会社会教育課の清家隆仁氏が講義を行い、船霊信仰の背景や佐伯市蒲江に伝わる歴史などについて詳しく解説した。
本イベントは、地域に伝わる海の民話を通じて子どもたちに海の文化や漁業の大切さを学んでもらうことを目的にしている。今後も「海ノ民話のまちプロジェクト」は、各地の海にまつわる民話を掘り起こし、次世代に伝えていく取り組みを続けていく方針だ。